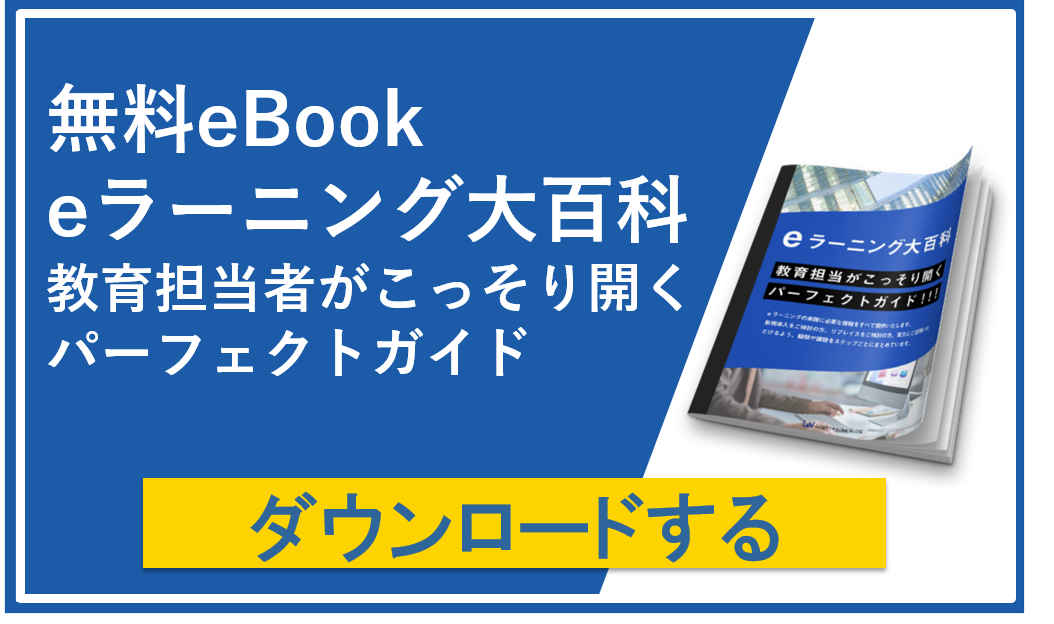「長年使ってきた研修システムが古くて限界…」
「eラーニングを導入したいが、何から手をつければ?」
「自社だけでなく、協力会社や関連会社まで含めた研修管理が複雑すぎる…」
多くの企業が直面するこれらの課題に、エネルギー業界のリーディングカンパニーである東京ガス株式会社はどう立ち向かったのでしょうか。
同社では、自社従業員だけでなく多数の協力企業や関連会社の従業員(合計約8万ID)を対象とした多様な研修を実施しています。その複雑な研修管理の変革を目指し、2024年2月、株式会社ライトワークスのLMS「CAREERSHIP」(東京ガス独自の愛称「CAMPUS(キャンパス)」を命名)を導入、研修DX(デジタルトランスフォーメーション)を力強く推進しています。
本記事では、東京ガス様が抱えていた課題から、LMS導入による具体的な成果、そして大規模運用ならではの大きな変化や今後の展望まで、導入から運用までを牽引したリビング業務改革部 人材育成センター 研修第3チームの栁下様に、その舞台裏を詳しく伺いました。
外部組織を含めた多様な受講生を対象にLMS導入を検討されている担当者の方にとって、きっと多くのヒントが見つかるはずです。
お話を伺った方(部署名・肩書は2025年4月取材時のもの)
東京ガス株式会社 リビング業務改革部人材育成センター研修第3チーム
チームリーダー 栁下修輝 様
人材育成の課題・解決方法を一冊にまとめました ⇒ LMS導入成功事例集を無料で読んでみる
目次
課題と背景:20年選手の『継ぎはぎ』システムが限界に
―― まず、栁下様のお役割と部署について教えていただけますか?
栁下様:私が所属するリビング業務改革部は、東京ガスの地域サービス窓口である東京ガスライフバル様をはじめとした協力企業の活動を支援する部署で、その中で人材育成センターは主に研修・教育面でのバックアップを担っています。
私自身は総務経理と研修の支援リーダーを担当しています。研修のデジタル化やeラーニング推進にあたり、教材の企画や導入プロセスの検討に関わってきました。設計や施工などのインストラクター経験もあります。

<人材育成センター研修第3チーム チームリーダー 栁下修輝 様>
―― 東京ガス様では弊社のLMSに「CAMPUS(キャンパス)」という愛称を設定してご利用いただいています。具体的には、どのように活用されていますか?
栁下様:「CAMPUS」は協力企業向けだけでなく、東京ガス全社で利用する研修プラットフォームとなっています。東京ガス社員から協力企業の従業員まで、あらゆる研修の申し込みから受講管理までを一元的に行っています。
私たちの部署では協力企業向けが8割、社員向けが2割程度の利用割合ですが、人事部や経理部などが実施する階層別研修や自己啓発研修など、社員向けの教育でも全面的に「CAMPUS」が活用されており、まさに全社的な学習基盤となりつつあります。
―― 「CAMPUS」を導入される前は、どのような研修管理をされていましたか?
栁下様:20年ほど、社内で独自開発した「SUTDY II」というシステムを使っていました。基本的には研修の申し込みと完了状況を管理するだけのシステムでしたね。
―― 長年利用されてきた中で、どのような課題があったのでしょうか?
栁下様:まさに「限界」でした。古いシステムなので、機能追加の要望があるたびに改修を重ね、結果的に「継ぎはぎ」だらけの状態になっていました。もはやブラックボックス化していて、新しいニーズ、特にコロナ禍で急速に高まったeラーニングへの対応は不可能でした。
さらに、外部サーバーの契約更新期限が迫っており、コスト面でも限界が見えていました。
―― では、コロナ禍でのeラーニングは、具体的にどう対応されたのですか?
栁下様:コロナ禍以前にも、一部で自作のスライドをめくる形式のeラーニングはありましたが、動きも音声もなく、受講者の満足度は高くありませんでした。本格的にeラーニング導入を検討し始めたのは、やはりコロナ禍が大きなきっかけです。
そこで2021年に、「STUDY II」とは別に、eラーニング配信に特化した外部システムを暫定的に導入しました。1年がかりでコンテンツを内製し、2022年から運用を開始したのです。
―― 2つのシステムを併用することで、新たな問題も生まれたのでは?
栁下様:おっしゃる通りです。募集は「STUDY II」、eラーニング受講は別システム、という状況になり、受講データの移行作業や、受講者へのURL個別案内など、運営側の手間が非常に増えました。研修履歴もシステム間で分散してしまい、一元管理ができません。
「この非効率な状況を何とかしたい」「老朽化したSTUDY IIも刷新しなければ」…そうした課題感が、本格的なLMS導入検討へと繋がっていきました。
「CAREERSHIP」導入の決め手は『標準機能への割り切り』と現実的な提案
―― 新しいLMSを選定する上で、特に重視した条件は何でしたか?
栁下様:まず、独自システムの改修(STUDY III)も検討しましたが、開発・維持コストを考えると現実的ではありませんでした。当時、全社的に基幹システムをSaaS(クラウドサービスの一種)へ移行する流れがあったことも大きいです。
その上で、最も重視したのは「多様な受講者をカバーできるキャパシティ」です。東京ガスの研修は、東京ガス社員だけでなく、数多くの協力企業、子会社、さらには他のガス事業者の方々まで、本当に多種多様な方が利用します。これら約8万IDものユーザーを安定して管理・運用できる実績があることが大前提でした。
―― 様々なLMSがある中で、ライトワークスの「CAREERSHIP」を選ばれた決め手は何だったのでしょうか?
栁下様:多くのベンダーが「あれもできます、これもできます」とカスタマイズを前提に提案してくる中、ライトワークスさんは標準機能を丁寧に説明し、導入後の運用イメージを具体的に持たせてくれました。費用を抑え、スムーズに導入・運用するには、過度なカスタマイズは避けるべきだと考えていたので、この姿勢は非常に好感が持てました。
また、大規模運用に対応できるシステムは限られていましたが、その中でもライトワークスさんの提案は、コスト感が現実的だった点も評価しました。
さらに、他社はカスタマイズが前提のため実際の操作を体験できなかったのですが、ライトワークスさんは「標準機能でのトライアル」を提供してくれたこともポイントです。実際に操作しながら「標準機能でここまでできるのか」と導入後の不安を払拭できました。

<東京ガスのLMS「CAMPUS(キャンパス)」のトップ画面見本>
結果として「SaaSの標準機能に、業務プロセスを合わせる」という我々の方針に、ライトワークスさんの提案が最も合致していたのです。
導入後は「外注依存」から脱却し、学習機会も劇的に改善
―― CAREERSHIP導入で、最も大きな変化は何でしたか?
栁下様:eラーニングの運用が、劇的に楽になりました。以前は外部委託が中心で、年度初めに教材コンテンツの内容を固めて発注、修正する度に費用と時間がかかり、タイトな納期に追われていました。正直、「このくらいの修正なら、まあいいか…」と改善を諦めることもあったんです。
それが今は、教材の準備を完全に内製化できています。教材の作成からシステムへのアップロードまで自分たちで行うので、「もう外部委託の納期と費用に悩まない!」という解放感は大きいですね。
例えば4月開始のコースも、極端に言えば3月末まで内容を練ることができます。ガス料金改定のような急な変更にも、タイムリーに教材へ反映できるスピード感は、大きなメリットです。
―― eラーニングの内容や提供方法も変わりましたか?
栁下様:座学中心だった研修は、基本的にeラーニングに切り替えました。研修センターに来ていただく意義は「聞くだけ」ではなく「手を動かす」ことにあると考え、研修センターでの研修は実習中心へとシフトしています。

<研修センターには実際に使われているガス設備が並ぶ>
例えば「ガス基礎」研修であれば、以前は2日間の集合研修でしたので、特に新年度が始まる4月は東京ガスの供給エリア内から受講者が集中し、申し込みは「チケット争奪戦」のような状況でした。
この2日間の集合研修を、座学部分(約5時間)のeラーニングと、希望者向けの実習コースに分離しました。eラーニングは通年公開にしたので、受講者は自分のペースで、隙間時間を使って学習できます。
何より、「いつでも研修が受けられる」ようになったことで、4月の申し込み殺到がなくなり、受講者・申込担当者双方の負担が大幅に軽減されました。「学びたい時に学べる」環境を提供できるようになったのは大きな進歩です。
―― 学習効果の面ではいかがでしょう?
栁下様:新入社員の場合、最初の受講ではピンとこなくても、「現場を経験してから復習すると、ああ、こういうことだったのか!と腑に落ちる」という声が多く聞かれます。
そこで、eラーニングは年度内であれば何度でも見返せるようにしています。以前の月単位の運用ではできなかった「振り返り学習」が可能になり、知識の定着に確実に繋がっていると感じますね。
―― 資格取得のテスト管理も効率化されたと伺いました。
栁下様:はい。資格取得のためのテストは、長年OCR(マークシート)方式でしたが、これを機にiPadでの実施に切り替えました。「CAMPUS」上で問題作成から採点、合否判定まで完結できます。
マークシートの準備、配布、回収、読み取りといった手間から解放され、テスト結果は社内の資格管理システム「License」とも連携できるので、管理業務が大幅に効率化されました。インストラクターが、より本来の教育業務に集中できるようになった効果は大きいですね。
―― CAREERSHIP導入から約1年(取材時点)経ちましたが、周囲の反応はいかがですか?
栁下様:大規模なシステム変更なので、正直トラブルも覚悟していましたが、驚くほどスムーズに移行できました。
もちろん、受講者からは当初、「前のシステムの方が使いやすかった」という声もありました。業務に合わせて徹底的にカスタマイズされていた旧システムに比べれば、当然ギャップはあります。しかし、それも次第に慣れていただき、今ではそうした声もほとんど聞かれなくなりましたね。特に、eラーニング化による利便性向上は、多くの方に歓迎されています。
―― eラーニングの内製体制についてはいかがですか?
栁下様:当社には専任の教材制作チームがあるわけではありません。eラーニング教材は、インストラクターが、自身の研修業務と兼務する形で作成しています。
私が動画編集ソフトの使い方などをレクチャーしましたが、インストラクターは「どうすれば伝わるか」を熟知しているので、あとは創意工夫でどんどん質の高いコンテンツを作ってくれています。特別なスキルがなくても、「自分たちでやってみよう」という意欲があれば、内製化は十分に可能だと実感しています。
―― 他のガス会社との交流もある中で、御社の取り組みはどう見られていますか?
栁下様:他地域の大手ガス会社の研修部門の方と情報交換すると、研修のデジタル化、特に内製化については「うちでは絶対にできない」と言われることが多いですね。外部委託が前提という考えが根強いようで、「なぜ東京ガスはできているのか?」とよく聞かれます。
私自身は決して管理が得意な方ではないので「自分が率先して進めよう」という考えで取り組んでいます。まず自分がやって見せて、興味を持った人が自然とついてきてくれた、という状況です。
「研修管理」から、全社的な「知見のプラットフォーム」へ
―― 人材育成センターとして、今後「CAMPUS」をどのように活用していきたいですか?
栁下様:デジタル化による研修の効率化と高度化は、今後ますます重要になります。高齢化や人手不足が進む中、特に技能伝承は大きな課題です。
映像コンテンツを充実させ、個々のスキルレベルに合わせて「手際よく進められる人はどんどん技量を引き上げて、苦手な人にはインストラクターが手厚く対応する」といった個別最適化された学びを提供していきたいですね。
また、研修施設の有効活用もテーマです。「CAMPUS」と実習設備を組み合わせ、個人で技量の研鑽を積む場所として、より多くの学習機会を提供できないかと考えています。

<実際の住宅構造を模した研修設備>
特に、設置施工分野の人手不足は喫緊の課題であり、限られたリソースで効率的かつ効果的に技術者を育成していく上で、「CAMPUS」の役割は大きいと感じています。
―― 「CAMPUS」は研修センター以外でも活用が広がっているそうですね?
栁下様:はい、これは大きな変化です。以前は、自社の情報セキュリティ研修やコンプライアンス研修などは、各部署バラバラのシステムで実施されていました。受講者はその都度違うシステムへのログインを求められ、管理者も全体像を把握しづらい状況でした。
それが今、人事部が主導する形で「社員研修はCAMPUSで一元管理しよう」という動きが進んでいます。2025年4月からは自己啓発の研修も「CAMPUS」に移行し始めています。
さらに、単なる研修ツールとしてだけでなく、動画配信プラットフォームとしての活用も始まっています。例えば、従来は容量の問題で難しかった詳細な作業マニュアル動画なども、「CAMPUS」上で手軽に配信できるようになりました。
「CAMPUS」は、研修だけでなく会社からの情報提供も含め、東京ガス全体の「知見共有インフラ」としての役割を担い始めており、様々な部署から「便利になった」と喜ばれています。
この先も、組織横断的な研修にグループ機能を活用したり、動画配信をもっとインタラクティブにしたりと、やれることはたくさんあるはずです。ただ、それを企画・実行する時間がなかなか取れないのが悩みですね。今後、さらに活用を進めていきたいと考えています。
研修のデジタル化は待ったなし「少しずつでも前へ」
―― 最後に、研修のデジタル化に取り組む企業へメッセージをお願いします。
栁下様:人手不足や高齢化が進む現代において、研修のデジタル化はもはや避けて通れません。特に技能伝承は、待ったなしの課題です。限られたリソースで効果を最大化するには、デジタル技術の活用が不可欠です。
当社では「CAREERSHIP」導入により、研修管理の一元化、eラーニング内製化によるコスト削減と柔軟性向上、テスト管理のデジタル化などを実現できました。もちろん、まだ課題は山積みですが、大切なのは少しずつでも前に進むことだと思います。
特に内製化については、「専門家でないと難しい」と思われがちですが、創意工夫と意欲次第で道は開けます。ぜひ、「自分たちでできることはないか」という視点で、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。
―― 貴重なお話をありがとうございました。東京ガス様の先進的な取り組みは、多くの企業の指針となることでしょう。
栁下様:こちらこそありがとうございました。
【取材・文】株式会社ライトワークス