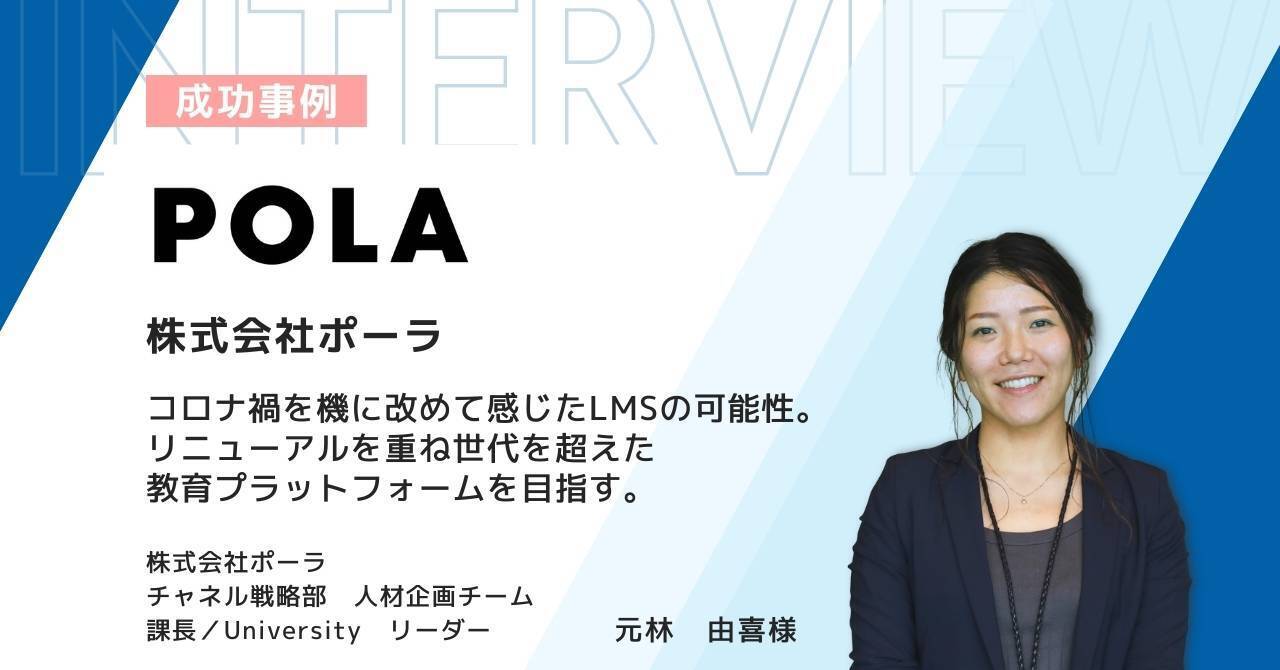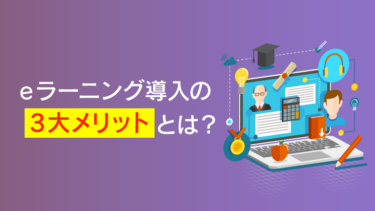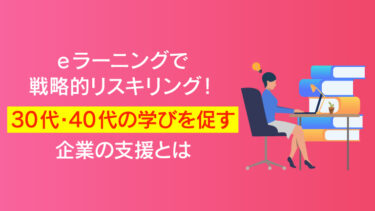多くの企業で導入されているeラーニングですが、「効果がない」「社員が活用してくれない」といった悩みや、導入前に「実践的なスキルやノウハウは身につかない」と判断してしまう声が少なくありません。
しかし、eラーニングが「意味がない」ものになるかどうかは、eラーニングそのものではなく「効果を最大化できない」運用方法にあるケースがほとんどです。
eラーニングの効果を高めるためには、自社に適したeラーニングシステムの導入が必要不可欠です。eラーニングシステムを利用することで、教材の用意・配信・受講状況や成績の管理などをシステムで一貫して行えます。
そこで本記事では、20年以上にわたり企業向けeラーニング教材を制作してきたライトワークスが、これまでの知見に基づきeラーニングが「意味がない」といわれる理由や改善方法、効果を高めるためのポイントについて解説します。eラーニング導入を検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
企業向けeラーニングシステム10件をポイントごとに比較! ⇒ 「eラーニングシステム徹底比較Book」を無料ダウンロード
eラーニングシステムは、インターネットを通じてオンライン上で教材を配信するためのシステムです。社内研修のコストを抑えられるだけでなく、DX推進やリスキリング、自律学習にも欠かせない手段となりつつあります。この記事では、企業向けeラ[…]
AIで要約
- eラーニングが効果的でないと感じる主な原因は、学習管理の不足や目的の不明確さ、対面研修向きの内容をeラーニングで行っていることなどです 。
- 研修効果を高めるには、15分以内の短時間コンテンツの作成やeラーニングシステムの活用、eラーニング研修に関する社内ルールの策定などが重要です。
- 社員のモチベーション向上のためには、eラーニングシステムによる学習管理や学習成果の人事評価への反映、集合研修との組み合わせが有効です。
eラーニングの効果が出ない主な原因
eラーニングはインターネットを介していつでもどこでも学べるのが魅力ですが、ただ実施するだけでは教育効果は得られません。ここでは、eラーニングで教育の効果が出ない主な原因を見ていきます。
社員の自主性に任せきりで学習管理ができていない
eラーニングを導入したものの、社員が自発的に学ぶことを期待し学習管理ができていないと、学習効果は得られません。個々の学習状況がわからなければ、遅れている社員への声掛けや理解度に応じたフォローなど適切なサポートができないからです。
また、社員の自主性に任せていると、学習内容が偏ったり、学習を先送りにしたりする可能性もあります。
このような事態を防ぐためには、eラーニングシステムを活用し学習の進捗状況や理解度、受講履歴、テスト結果などを管理することが重要です。データを基に学習コンテンツの体系的整理やパーソナライズされたカリキュラムを提供すれば、効率的な学習を促進できます。
「eラーニングはどのような使い方をすれば、しっかり効果を得られるのだろうか?」時間・場所を問わず学習を進められるeラーニングは、企業の教育・研修担当者の負担や研修コストを軽減し、効率的に人材育成を行う方法として注目されています。[…]
eラーニングで学習する目的が不明確
eラーニングを導入することで企業と社員が何を実現したいのかが不明確なままだと、期待する学習効果は得られません。企業にとっては、どのようなコンテンツを作成し、どのように学習を進め、効果を測定するか教育方針を決められませんし、学習者にとっては「やらされ感」を生みモチベーションが下がる可能性があります。
そのため、導入前に「なぜeラーニングを導入するのか」目的を明確にし、学習者と共有することが重要です。会社としてeラーニングを導入する目的と、個々の社員が学習を通じて得たい成果を結びつけることで、学習意欲は格段に向上するでしょう。
対面研修で行うべき内容をeラーニングで教育している
eラーニングで研修を実施する際に、「対面研修で行うべき内容をそのままeラーニングに移行してしまった」というケースは少なくありません。しかし、eラーニングと対面研修では、学習効果を高めるためのアプローチが異なります。
対面研修は講師や他の学習者と直接コミュニケーションが取れるため、ディスカッションやロールプレイングなど実践的なスキル習得に向いています。一方、eラーニングは一人で受講するのが一般的なため、対話を必要とする研修には不向きです。
そのため、座学で学べる内容はeラーニングで行い、実技指導が必要な研修は対面研修で行うなど、使い分けるとよいでしょう。eラーニングの特性を活かし、集合研修の前後の予習・復習に活用するのも効果的です。併せてeラーニングでテストを実施すると、学習内容の理解度を深められます。
「集合研修は本当に必要なものだけにしたい」このようにお考えの人材開発部門の方は多いのではないでしょうか?eラーニングが普及した今、企業の教育管理者が、人材育成のプログラムを極力オンライン研修化し、集合型の研修を減らしたいと考えるの[…]
企業向けeラーニングシステム10件をポイントごとに比較! ⇒ 「eラーニングシステム徹底比較Book」を無料ダウンロードする
社員がeラーニングは「意味がない」と感じる理由と解決策
企業や社員にとってeラーニングは「意味がない」と感じられる理由として、以下の6つが挙げられます。
- コンテンツの時間が長い
- 流し見や飛ばし見ができ学習内容が定着しない
- 特定のデバイスやOSしか対応していない
- eラーニングの内容が実務に活かせない
- 労働時間外に受講せざるを得ない
順番に見ていきましょう。
コンテンツの時間が長い
他者の目がある集合研修と異なり、1人で画面を見続けるeラーニングは、1コンテンツあたりの時間が長すぎると集中力が保てなくなります。特に忙しいビジネスパーソンにとって、業務の間に長いコンテンツを見るのは困難です。
さらに、コンテンツの内容が複雑だったり、受講者に前提知識がなかったりすると、いちから調べる手間がかかり受講時間が大幅に長くなる可能性があります。
【解決策】短時間で受講できるコンテンツを作る
人間が集中力を保てる時間は15分程度といわれているため、コンテンツの視聴時間は長くても15分程度に収めましょう。忙しい社員がすき間時間に学習(マイクロラーニング)できるよう、1~5分程度のコンテンツを作るのも効果的です。
「マイクロラーニングは自社でも作れるらしい。作り方さえ分かれば、当社も挑戦してみたい」本稿は、そんな企業の人材開発部門の担当者や教育管理者のためにご用意したノウハウ記事です。人材が企業の資産とされる今、人材育成は事業の行く[…]
流し見や飛ばし見ができてしまい学習内容が定着しない
eラーニングはいつでもどこでも学べるのが魅力ですが、一般的なeラーニングは読み飛ばしや流しっぱなしなどの不正受講ができるのがデメリットです。
【解決策】不正受講防止機能のあるeラーニングシステムを選ぶ・インパクトのあるコンテンツを作る
流し見や飛ばし見を防ぐためには、早送りやシークバー操作の禁止といった不正受講防止機能のあるeラーニングシステムを選びましょう。
特定のデバイスやOSしか対応していない
eラーニングが特定の環境でしか受講できないと、習熟度の低下や不満につながります。例えば、「特定のデバイスやOSでないと受講できない」「専用ソフトが必要」「会社のPCからでなければ受講できない」などの場合、受講のハードルが上がってしまうでしょう。
また、eラーニングのシステムが扱いづらい場合も、学習意欲の低下につながります。
【解決策】マルチデバイス対応・直感的な操作が可能なeラーニングシステムを選ぶ
社員がどのような環境からでもアクセスできるよう、スマートフォン、タブレット、PCなどさまざまなデバイスに対応したマルチデバイス対応のeラーニングシステムを選びましょう。誰でも直感的に操作できるよう、分かりやすいインターフェースのeラーニングシステムを選ぶことも重要です。
「クラウド型のeラーニング」とは、インターネット上のサーバーを活用して実施するeラーニングのことです。スマートフォンやタブレットなどを利用し、受講生が都合のよいタイミングで教育できます。管理者側も時間や場所を問わず学習状況や成績などをチェ[…]
eラーニングの内容が実務に活かせない
eラーニングで学んだ知識やスキルが一般的過ぎたり、現場のニーズから乖離していたりすると、「学んだ内容を仕事に使えなかった」と学習の意義を疑問視される原因になります。
コンテンツが冗長な場合も、受講者が流し見や飛ばし見をして学習内容が定着せず、実務に活かせない可能性があります。
また、eラーニングは「動画を視聴する」という性質上、インプットがメインとなる傾向があります。アウトプットの機会が少ないと、具体的に実務にどう活かすのかわからず、モチベーションの低下につながるでしょう。
【解決策】実務的な内容を学べるコンテンツを提供する
学習内容を実務に活かせるよう、実務に即したコンテンツを作成しましょう。実際の業務で起こり得る場面を想定したケーススタディやロールプレイングを盛り込むと、学習者が現場での応用方法をイメージしやすくなります。
コンテンツが冗長にならないよう、動画やアニメ、実践的な演習などを取り入れたり、テスト機能を入れたりと、インパクトを持たせることも有効です。
さらに、eラーニング受講後に集合研修を行い、グループワークやディスカッション、ロールプレイングなどでアウトプットさせると学習内容を深く理解できます。
eラーニングでの学習時間が労働時間に含まれない
企業の指揮命令による集合研修の受講は、「労働時間」としてカウントする一方、eラーニング研修については労働時間外での受講を基本とする企業が珍しくありません。社員は自分の時間を割いてeラーニングに取り組まざるを得ないため、学習へのモチベーションが低下してしまうでしょう。
【解決策】eラーニング受講に関する社内ルールを策定する
eラーニングでの学習が業務命令の場合は、受講時間を勤務時間にカウントするのが理想的です。社員が自由意志で学習する場合は、業務時間に含めなくてもよいでしょう。
認識の齟齬を防ぐためにも、eラーニング導入前に「強制受講か任意受講か」「人事評価に影響するか」「受講できる時間帯」など、ルールを策定しておくのが必要不可欠です。
オンラインで受講できる「eラーニング」は、多くの企業で普及しつつあります。eラーニングは社員が自分のペースで学べることがメリットですが、より効果を高めるためには適切に運用することが必要です。特にeラーニングの時間設定については、ど[…]
eラーニング研修の効果を高めるコツ
eラーニング研修の効果を高めるために、以下の4つのコツを押さえておきましょう。
- eラーニングシステムで学習管理やフォローを適切に行う
- eラーニングへの取り組みを人事評価に反映する
- 他の研修手法と組み合わせて実施する
- 定期的に効果を測定する
順番に見ていきます。
eラーニングシステムで学習管理やフォローを適切に行う
eラーニングの効果を最大化するには、eラーニングシステムでの学習管理とフォローが鍵となります。eラーニングシステムを活用すれば、受講者それぞれの受講状況や理解度をリアルタイムで確認し、テストの結果を反映したフォローを行えます。
受講者自身も習熟度を把握しやすくなる他、目標設定や進捗を共有することで、学習意欲が高まるでしょう。さらに、個々の理解度や進捗状況に合わせた学習パスを提供すれば、自分のペースでモチベーション高く学習を進められます。
自社に最適なeラーニングシステムを探すなら ⇒ 「企業向けeラーニングシステム比較eBook」を無料で読む
eラーニングへの取り組みを人事評価に反映する
eラーニング研修は、受講状況やテストの成績、学習時間など、学習成果を数値化しやすいことが特徴です。これらを人事評価の項目に反映させることで、学習意欲のさらなる向上につながるでしょう。
他の研修手法と組み合わせて実施する
eラーニングはインプット中心の研修のため、グループワークやOJT研修など、対面でアウトプットできる研修と組み合わせるのが効果的です。「基礎知識の習得や習熟度の強化はeラーニング」「実践的な研修は集合研修」のように使い分けると、社員が学習効果を実感しやすくなるでしょう。
ハイブリッド研修とは、対面とオンラインでの研修を組み合わせた研修方法のことを指します。コロナ禍を経て研修のオンライン化が進み、その後はオンライン研修と対面研修のそれぞれのメリットを活かしたハイブリッド方式を取り入れる企業も出てきました。[…]
定期的に効果を測定する
eラーニングの効果を最大化するためには、定期的に効果を測定し改善することが必要不可欠です。学習内容が実務に活かせているか、学習目標は達成されているかなどを、アンケートやテスト、実務での行動変容の観察などを通じて確認しましょう。
測定結果は、コンテンツの改善や、学習管理・フォロー体制の見直しに活かされます。例えば、理解度が低い箇所があれば、コンテンツを修正したり、補足説明を追加したりします。
また、eラーニングシステムの活用状況や学習者のエンゲージメントに課題が見られた場合は、個別フォローの強化や、研修設計そのものを見直すきっかけにもなります。
「eラーニングを導入したいが、本当に効果があるのかわからず、費用対効果のめどが立たない…」「すでに導入しているが、従業員が活用しきれておらず、成果が曖昧になっている…」eラーニングは多くの企業で導入されていますが、その効果の測定や[…]
自社の教育施策に合うeラーニングシステムを選ぶポイント
eラーニングの効果を最大化するためには、自社の教育施策に合致したeラーニングシステムの選定が不可欠です。チェックすべき主なポイントは下記の通りです。
- 導入目的の実現に必要な機能が搭載されているか
- 利用者数や利用頻度に対して料金形態が妥当か
- 誰でも簡単に操作できるか
- セキュリティ体制が強固か
- サポート体制が手厚いか
上記ポイントを総合的に判断し、自社の教育目標達成に貢献するeラーニングシステムを選定しましょう。
自社に合うeラーニングシステムを選ぶポイントやおすすめの製品を詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
「eラーニング」は、運営形態や受講方法、コンテンツの組み立て方といった幅広い観点で種類が分かれています。種類が多岐にわたるため、自社の状況にマッチするeラーニングを選ぶにあたって迷う企業もいるでしょう。「どの種類のeラーニングを選[…]
自社に最適なeラーニングシステムを探すなら ⇒ 「企業向けeラーニングシステム比較eBook」を無料で読む
eラーニング導入企業の成功事例
ここでは、eラーニングシステムの導入・活用によってeラーニング運用を成功させた事例として、2社をご紹介します。
株式会社ポーラ
株式会社ポーラは、接客者の育成強化・研修データの蓄積による社内活用を目的にeラーニングシステムを導入しました。
同社のeラーニング教材は、新人向けの基礎知識から接客力向上を目的としたもの、新製品情報など、自社オリジナルの動画コンテンツがメインとなっています。
運用の結果、知識習得はeラーニング、実技は対面と役割を分け、eラーニング受講後に集合研修でアウトプットするブレンディッドラーニングを確立しました。これにより、研修場所や時間の拘束がなくなり、接客者がお客様との時間を優先できるようになりました。
また、教材をマルチデバイス対応で配信できるため、いつでもどこでも学べる環境が実現しました。その結果、一人当たりの学習コンテンツ量と修了者の割合が大幅に増えました。
「お客さま一人ひとりの美を引き出し、自分の人生を自ら演出する」ことを実現するために、ポーラ店舗やサロンでお客さ…
ENEOS株式会社
ENEOS株式会社は、全国11,000店を超えるサービス・ステーション(SS)における顧客満足(CS)向上のため、スタッフの教育水準の均一化と効率化を目的にeラーニングを導入しました。
同社のeラーニング教材は、エンジンオイルやタイヤといった専門的な商品知識から、販売オペレーション、CS経営の基礎に至るまで、お客様対応に必要な知識を網羅した自社オリジナルコンテンツが中心です。これらの教材はPCだけでなくタブレットにも対応しており、全国どの店舗のスタッフでも手軽に学べる環境を整備しています。
運用の結果、座学研修の大部分をeラーニングが担う教育体制を確立しました。「eラーニングを受講しなければ店頭に立てない」というルールのもと、スタッフはまず体系的な知識を習得し、その上で実技演習やOJTに進みます。
これにより、教える側の負担や教育レベルのばらつきといった課題を解消しました。eラーニング導入後、スタッフは自信を持ってお客様に商品を提案できるようになり、お客様からのクレームは大幅に減少。丁寧な接客が顧客からの信頼獲得につながっています。
※所属は取材当時のもの 施策の効果 eラーニングを受講しないと店頭には立てません。販売オペレーション、タイヤや…
「従業員の研修コストがかさんで頭が痛い」「全国の拠点で教育の質にばらつきが出てしまう」「人材育成やキャリア形成の良い打ち手を探している」人材育成の担当者の方は、このような課題をお持ちではありませんか?多くの[…]
自社に最適なeラーニングシステムを探すなら ⇒ 「企業向けeラーニングシステム比較eBook」を無料で読む
まとめ
eラーニング研修は、活用方法次第でコストを押さえて効果の高い研修を実施することができます。しかし、やり方によっては「eラーニング研修は意味がない」と感じるケースが少なくありません。
eラーニング研修の効果が出ない主な原因は下記の通りです。
- 社員の自主性に任せきりで学習管理ができていない
- eラーニングで学習する目的が不明確
- 対面研修で行うべき内容をeラーニングで教育している
このような課題を解決するためには、「eラーニングシステムで学習管理を行う」「導入目的を明確にし社内で共有する」「座学で学べる内容はeラーニング、実技指導が必要な研修は集合研修で行う」といった対応が求められます。
また、eラーニング研修を導入したものの、社員が「意味がない」と取り組みに消極的な場合があります。主な原因と解決策は下記の通りです。
・コンテンツの時間が長い
→【解決策】15分以内で受講できるコンテンツを作る、マイクロラーニングを導入する
・流し見や飛ばし見ができ学習内容が定着しない
→【解決策】不正受講防止機能のあるeラーニングシステムを選ぶ、動画やアニメなどを使いインパクトのあるコンテンツを作る
・特定のデバイスやOSしか対応していない
→【解決策】直感的な操作が可能かつマルチデバイス対応のeラーニングシステムを選ぶ
・eラーニングの内容が実務に活かせない
→【解決策】実務に即したコンテンツを作成する、eラーニング受講後に集合研修を行い学んだ内容をアウトプットさせる
・労働時間外に受講せざるを得ない
→【解決策】eラーニング受講時間を勤務時間にカウントするかなど、受講に関する社内ルールを策定する
さらに、eラーニング研修への社員のモチベーションを上げるコツとしては、下記が挙げられます。
- eラーニングシステムで学習管理やフォローを適切に行う
- eラーニングへの取り組みを人事評価に反映する
- グループワークやOJT研修など対面で行う研修と組み合わせて実施する
- 定期的に効果を測定し、学習管理、フォロー体制、コンテンツの内容などを見直す
eラーニング研修の効果を上げるにはeラーニングシステムが必要不可欠ですが、数あるベンダーの中から自社に合う製品を選ぶのは簡単ではありません。自社に合う製品を選ぶ際は、下記ポイントをチェックするとよいでしょう。
- 導入目的の実現に必要な機能が搭載されているか
- 利用者数や利用頻度に対して料金形態が妥当か
- 誰でも簡単に操作できるか
- セキュリティ体制が強固か
- サポート体制が手厚いか
上記ポイントを総合的に判断し、自社の教育施策に合うeラーニングシステムを選びましょう。
eラーニング導入の成功事例として、下記2社を紹介しました。
- 株式会社ポーラ
- ENEOS株式会社
eラーニングは、OJTやグループワークなどの研修と組み合わせることで効果を上げられます。研修内容によってeラーニングと集合研修を使い分けるのも有効です。工夫次第で効率的に研修を実施できるので、この機会にぜひ導入を検討してみてください。