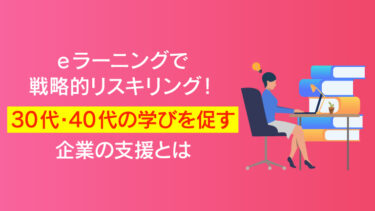「eラーニングはどのような使い方をすれば、しっかり効果を得られるのだろうか?」
時間・場所を問わず学習を進められるeラーニングは、企業の教育・研修担当者の負担や研修コストを軽減し、効率的に人材育成を行う方法として注目されています。
学校法人産業能率大学総合研究所が2024年に実施した「通信教育およびeラーニングの活用実態調査」1によると、eラーニングを利用した学習により、情報や知識を獲得できていると感じる企業は6割以上です。一方で、eラーニングによる学びが現場で実践できたり、個人の行動が変化したりという行動変容の効果を実感する企業は3割程度となっています。
もっとeラーニングの効果を引き出す使い方をしたいという教育・研修担当者の方は多いのではないでしょうか。
この記事では、eラーニングの具体的な使い方を企業の成功事例と共に紹介します。eラーニング導入の基礎知識や最新トレンド、運用に向けたステップ・ポイントなども紹介しますので、eラーニング活用の参考としてください。
企業向けeラーニングシステム10件をポイントごとに比較! ⇒ 「eラーニングシステム徹底比較Book」を無料ダウンロード
「eラーニングを導入して数年が経つが、どうも効果的に活用できている気がしない」そんな不安を抱くことはありませんか?LMS(Learning Management System、学習管理システム)を使って教材コンテンツを配信[…]
AIで要約
- eラーニングの効果を最大化するには、動画教材やマイクロラーニングなどの最新トレンドを取り入れ、目的に応じた適切な運用を行うことが重要です。
- さまざまな企業が社内研修、新入社員研修、コンプライアンス教育、店舗・現場教育などにeラーニングを取り入れ、成功しています。
- 短時間学習やアウトプット機会の確保、オフライン学習との組み合わせが、eラーニングの効果を高める重要なポイントです。
eラーニングとは?基礎知識と最新トレンド
eラーニングとは、パソコンやスマートフォン、タブレットなどの電子デバイスを使って、インターネット経由で行う学習のことです。
従来のeラーニングは社内のパソコンなどでしか利用できませんでしたが、昨今はマルチデバイス化が進み、スマホやタブレットでどこでも学習が可能となっています。
eラーニングはインターネットで配信されるため、受講者が大人数であったり、複数拠点であったりしても一斉に同じ教育を実施できます。また、対面の集合研修では少なくないコストがかかる講師・会場・交通費用を抑え、担当者の事務負担も軽減できるなどのメリットがあり、多くの企業に活用されています。
ここでは、eラーニングの基礎知識と最新トレンドについて確認します。
eラーニングの目的
まず、企業と従業員がeラーニングを利用する主な目的を確認しましょう。
企業の目的
- 従業員へのいつでも、どこでも学習できる環境の提供
- 従業員への平等な研修機会の提供
- 講師による研修の質・内容のバラつき防止
- 人材育成のコスト削減
- 教育担当者の負担軽減・業務効率化
上記以外では、新入社員研修において、コスト・工数削減や学習習慣を身に付けさせるなどの目的で活用する企業も増えています。
また、大人数の受講に対応できるeラーニングは、全従業員に徹底させることを目的にコンプライアンスやハラスメント対策の教育にも活用されています。
従業員の目的
- 業務に役立つ知識を、自分のタイミングで学ぶ
- スマホ学習による、隙間時間の有効活用
- スキルアップ・キャリアアップにつながる効率的な学習
- 反復学習による知識の定着
スキルアップ・キャリアアップのための学習については、教育担当者がeラーニングや集合研修を組み合わせ、個々のスキル獲得に最適な学習コースを作成することで、より効率的に学習を進めることも可能です。
eラーニングのメリット・デメリット
いつでも、どこでも、何度でも学べるeラーニングは多くのメリットをもたらします。しかし、eラーニングならではのデメリットもあるため、導入前には双方を理解する必要があります。
まず、企業のメリット・デメリットを見てみましょう。
企業のメリット
- 受講者に均質な学習を提供できる
- テキスト代や会場レンタル費用、会場までの交通費などの費用を削減できる
- 教育担当者の負担を軽減できる
- 修正・アップデートが随時可能で、最新の教材をすぐに配信できる
- 学習履歴を管理できる
- 個々に最適な教材や学習内容を提供できる
企業のデメリット
- 初期費用や、継続利用のための費用が発生する
- 導入時には運用に向けた準備や、教材購入・作成の手間がかかる
- 教材配信や学習管理のためのeラーニングシステムが必要
- 従業員がeラーニングを利用しない可能性がある
eラーニング教材だけでは、配信・受講はできません。教材を配信、運用・管理するためのeラーニングシステムが必要です。
また、eラーニングの進捗は個々の意欲に大きく左右される上、集合研修のような強制力はありません。そのため、導入したeラーニングを従業員が利用しない可能性も懸念されます。教育担当者は、魅力的なコンテンツの用意、学習進捗・成績を人事評価へ反映させるなど、受講者の意欲を高める対策を考える必要があります。
次に、従業員のメリット・デメリットを見てみましょう。
従業員のメリット
- 好きな場所・タイミングで利用できる
- 自分のペースで学習できる
- 多くの学習機会を得られる
- 学習の進捗が分かりやすい
- 映像や音声のある動画教材なら、さらに理解を深められる
従業員のデメリット
- 集合研修のようにその場で質問ができない
- 受講者同士の交流ができない
- インターネット環境や、eラーニング利用のための端末が必要
- 学習意欲がなければ活用し切れない
デメリットへの対策としては、eラーニングのメリットを生かしつつ、集合研修やロールプレイ、講師・受講者同士の交流などオフライン学習の要素も取り入れる「ブレンディッドラーニング」が有効です。対面での学びの時間を確保し、受講者の意欲を高めます。
関連 ▶ ブレンディッド・ラーニングとは 研修とeラーニングのうまい組合せ方
AI活用も!eラーニング最新トレンドを紹介
eラーニングの原型となるコンピューターを利用した教育が始まったのは、1950年代のことです。その後、1995年に発売されたWindows95の普及によるマルチメディア教材の登場、2000年代の高速・大容量インターネットサービスの一般化を経て、学習方法の一つとして定着しました。最近ではパソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットなどマルチデバイスでの学習が主流となっています。
ここでは、eラーニングの教材や学び方などについて、最新トレンドを紹介します。
最新トレンド1:動画教材
従来のeラーニングでは、テキストや画像を中心とした教材を使用し、知識の習得を行っていました。
しかし昨今は飲食店や工場、医療といった現場に従事する人に向け、動画教材で作業手順などのノウハウを伝える実践型eラーニングが増加傾向にあります。
動画教材は、視覚的に理解しやすく臨場感もあり、受講者の理解度を高めることができます。
最新トレンド2:マイクロラーニング
マイクロラーニングは、学習内容の重要な部分を数分程度の教材としてまとめたもので、現在、eラーニングの主流となっています。
スマホ利用や隙間時間の活用のニーズが高まり、短時間で効率的に学習可能な教材が求められているためです。
最新トレンド3:アクティブラーニング
講師が受講者に話を聞かせる一方向的な講義ではなく、受講者が能動的に考え参加するアクティブラーニングが、eラーニングにも取り入れられつつあります。
SNS連携や、仮想空間でのディスカッションなど、従来のeラーニングにはない学習スタイルも実現されています。
最新トレンド4:AI活用
さまざまな分野でAIの活用が広まっており、eラーニングも例外ではありません。
例えば、AIが個々の学習状況やテストの成績などを分析し、eラーニング教材をレコメンドしてくれるeラーニングシステムもあります。
受講者は自分に必要な学習を効率的に進めることが可能になり、管理者はレコメンドに係る作業の負担がなくなった分、他の業務に注力できます。
以上のように、eラーニングは最新技術を取り込み、ますます進化しています。
スマホ学習に最適!マイクロラーニングの導入・運用方法を知る ⇒ 「マイクロラーニング大全」を無料ダウンロードする
【事例あり】eラーニングの具体的な使い方
eラーニングの効果的な使い方は、実施する研修や教育によって異なります。ここでは、具体的な使い方を企業事例と共に紹介します。
社内研修
eラーニングは以下のような多様な社内研修ニーズに対応し、多くの従業員に平等な研修機会を提供します。
- 階層別研修(若手、中堅、管理職など)
- 業務知識・スキル習得(OJTの補完にも)
- グローバル人材育成(語学、D&Iなど)
- DX研修 など
企業事例:トヨタ紡織株式会社
自動車内装品をはじめとした、自動車部品の製造を行うトヨタ紡織株式会社では、国内の技術専門教育について、約7割をeラーニングに置き換えました。
eラーニングを活用しながら実地教育も適切に織り込み(ブレンディッドラーニング)、教育の目的に応じて理解促進のために最適な教育を選択しています。
従来は対面での教育が主流でしたが、2020年度のコロナ禍以降、eラーニング化が一気に進みました。単なる紙媒体から電子データへの移行ではなく、コンテンツ内容の見直しも行われました。
その結果、現在は422講座がeラーニングで受講可能となり、デジタル教育のメリットを実現できています。
自動車のインテリア・エクステリア、ユニット部品、航空機のシートなどを製造するトヨタ紡織株式会社(以降、トヨタ紡…
新入社員研修
新入社員のオンボーディングを効果的に行うと、社会人生活や業務に早く順応でき、定着率向上が期待できます。そのためには、以下のような研修が必要です。
- 内定者研修や入社前教育
- ビジネスマナー研修
- 担当業務についての研修
- 自社事業や企業文化の理解 など
短期間で多くの教育が必要な新入社員研修は、多忙な教育担当者の負担を軽減することも重要です。eラーニングを活用して効率的に進めましょう。
企業事例:株式会社テンポイノベーション
店舗物件の転貸借に特化した不動産事業を行う株式会社テンポイノベーションは、新入社員の早期戦力化・定着率向上と研修担当者の負担軽減が課題となっていました。
そこで社内に分散していたナレッジを整理し、10カ月で300本の動画教材化に成功。新入社員研修に、アニメーション動画を用いたeラーニングを導入しました。
新入社員は成果を出すスピードを上げ、自信を持って業務にあたれるようになりました。動画教材導入後の1年間で退職した新入社員は、ほとんどいないということです。
また、研修担当者の負担も軽減しました。動画教材を活用することで、イメージの行き違いや説明コストが激減。時間に余裕ができ、新入社員のサポートやケアに回せるようになったのです。
このような取り組みにより、課題となっていた新入社員の定着率向上と研修担当者の大幅な負担軽減を達成しました。
店舗物件の転貸借に特化した不動産事業を展開する株式会社テンポイノベーションは、新入社員の早期戦力化・定着率向上…
コンプライアンス教育
1人の従業員の不正や違法行為が企業全体の価値を下げてしまうケースもあるため、コンプライアンスは全従業員に徹底させる必要があります。eラーニングは、大人数への配信に対応し、世界各地の拠点でも実施できることから、コンプライアンス教育の方法として最適といえるでしょう。
同じく全従業員が学ぶべきとされる、情報セキュリティ教育、ハラスメント対策などの研修にもeラーニングの活用をおすすめします。
企業事例:株式会社タカラトミー
玩具や雑貨などの開発・製造・販売を行う株式会社タカラトミーは、おもちゃの会社として、子どもたちの見本となるような存在であり続けたいという思いの下、コンプライアンスを根付かせるための活動の一環として、eラーニングを活用しています。
同社ではeラーニングを11カ国・8言語対応の多言語で配信し、法令知識の効率的な学習はもちろん、最新の社会情勢や経営状況を踏まえた内容を、海外拠点も含む全従業員が受講できるようにしました。
必要に応じて集合研修も併せて実施し、コンプライアンスの重要性を周知徹底しています。
タカラトミーグループでは、LMS(学習管理システム)を活用してグループ全社員との繋がりを構築し、個々の社員がコンプライア…
店舗・現場教育
飲食店や工場などの現場では、知識はもちろん、技術や作業手順の習得も必要です。eラーニングは指導者の力量に左右されず、教育の質を保てます。
動作を伴う手順やこつの学習には、動画を用いたeラーニング教材が有効です。業務マニュアルのリアルタイム共有や更新も簡単で、常に最新の情報を提供できます。
企業事例:株式会社ルネサンス
会員制フィットネスクラブや温浴施設などを運営する株式会社ルネサンスは、顧客対応最優先のスタイルにより、新人スタッフの教育にかけられる時間が足りないという課題を抱えていました。
そこで、教育担当者が顧客対応や他の業務に当たっている間、新人スタッフはeラーニングで企業理念や接遇、コンプライアンス、職種ごとの業務手順などを自主学習してもらうことで、時間を有効活用できるようになりました。
新人スタッフはeラーニングで業務のベース作りをしてからOJTに臨む仕組みとなり、現場で生きる知識や技術を効率的に身に付けられています。同時に、教育担当者が新人教育時間にかける時間や労力の削減にも成功しました。
店舗を運営する企業に共通する課題「新人教育を効果的・効率的に実施し、早期戦力化を実現していくこと」について、どのようにス…
eラーニングの実施に必要なもの
ここでは、eラーニングの導入に当たって不可欠な3つのものを解説します。
eラーニングシステム
eラーニング教材の配信や管理を行うには、eラーニングシステム(「LMS(Learning Management System):学習管理システム」とも呼ばれます)が必要です。eラーニングシステムの主要機能には、以下のようなものがあります。
- 教材配信・受講
- 教材作成
- アンケートやテスト配信・自動採点
- 学習コース作成・管理
- 学習状況の把握、成績管理
- 集合研修やeラーニングの受講申込み・自動リマインド など
eラーニングシステムは、教育担当者の負担を軽減しながら、受講者に効果的かつ効率的な学習の提供が可能なツールです。個々の学習進捗や学習時間、テスト結果などさまざまなデータを把握しやすく、学習の効果測定にも活用できます。
eラーニングシステムは、さまざまなベンダーが提供しています。コストの低さが注目されがちですが、自社が求める機能があるかどうか、eラーニングコンテンツやサポート体制は充実しているかなども重視して検討しましょう。
たとえば、ライトワークスが提供する「CAREERSHIP GROWTH」は、利用者1,000人以下の企業向けに最適化された、eラーニングシステムとコンテンツが一体化したオールインワンサービスです。
リーズナブルな価格設定ながら機能は充実しており、300タイトル1,000本以上のeラーニング教材を利用できます。
「システム」と「コンテンツ」の一体化で管理がラクに! ⇒ 「CAREERSHIP GROWTH」について詳しく見る
その他、eラーニングシステムの比較や選定のポイントを、以下の記事で詳しく解説しています。
eラーニングシステムは、インターネットを通じてオンライン上で教材を配信するためのシステムです。社内研修のコストを抑えられるだけでなく、DX推進やリスキリング、自律学習にも欠かせない手段となりつつあります。この記事では、企業向けeラ[…]
eラーニング教材
eラーニングシステムを使って配信できる教材の種類はさまざまで、以下のようなものがあります。
- 動画:集合研修のような講義内容を配信する動画や、作業手順を収録したもの、脚本・演出を施しドラマ仕立てで作成されたもの、アニメーションなど
- 写真・イラスト・音声:写真やイラスト入り教材に、音声を追加して視覚・聴覚で情報収集ができるもの
- PowerPoint:PowerPointで作成したスライド教材。音声やアニメーション、動画と組み合わせたものもある
- ライブ授業:リアルタイムで実施されている研修・セミナーの内容をライブ配信
- ドリル:テスト問題形式の教材で、学習内容の定着を確認できる
現在、主流となっている動画教材
動画教材は、文字だけ、音声だけの教材と比較して、内容を理解しやすいのが特徴です。再生速度を変えたり、スキップや早送り・早戻ししたりもできるので、「苦手」の克服や気になる部分を確認しやすいのもメリットといえます。
動画教材を採用する場合、短時間で要点をまとめたり、テーマごとに動画を分けたりしてマイクロコンテンツ化すれば、多忙な受講者でもちょっとした隙間時間に活用しやすくなります。
動画教材の内製・外注
動画教材は、市販のものを購入/レンタルする他、内製または外注で、自社独自の教材を製作することもできます。内製すれば教材製作のノウハウが蓄積され、業務内容の変更などにも柔軟かつ迅速に対応できます。また、外注よりもコストを抑えやすいのも、内製のメリットです。
一方で、教材作成のスキルが不足していると、教材の完成度が低くなったり、教育担当者の新たな負担が増えただけとなったりする恐れがあります。状況によっては外注の検討が必要でしょう。
外注による最大のメリットは、専門的な知識とスキルで高品質な教材を提供してもらえる点です。また、教材製作に時間を費やさなくてよいので、担当者の負担も軽減できます。
ただし、外注は内製よりも制作費用が高くなる傾向にあります。また、内容の修正・変更に即時対応してもらえなかったり、追加料金が発生したりする場合もあります。依頼先を慎重に検討しないと、期待した品質の教材にならない、社内情報が漏えいするなどのトラブルに発展する可能性もあるので、注意が必要です。
教材を手軽に内製! ⇒ ライトワークスのeラーニングパッケージプラン「CAREERSHIP GROWTH」の教材作成機能 を詳しく見る
オリジナルeラーニング教材を「まなびのプロ」が制作 ⇒ ライトワークスのeラーニング教材制作サービスを詳しく見る
受講者への支援
受講者の支援も、eラーニング実施に当たって欠かせない要素です。学習への強制力があまり強くないeラーニングは、受講者自身の意欲をどれだけ高められるかが導入の成功を大きく左右します。
そこで、昨今は受講者の学びを支援する、「チューター」や「メンター」のニーズが高まっています。
チューターやメンターは、受講者の質問や学習に関する悩みに答える存在です。受講のリマインドや、課題添削を行う場合もあります。
学習面はもちろん、学習に向けたモチベーションアップ・維持のためのケアも行うチューター・メンターは、eラーニングの活用において、重要な役割を果たします。
スムーズなeラーニング導入・運用のための5ステップ
eラーニング導入・運用のステップは、大きく分けて5つです。計画から運用までの流れを解説します。
ステップ1. 学習計画の立案
まずは、学習計画を立案します。今後必要な研修や教育の内容を整理し、ゴールの設定と達成に向けた具体的なスケジュールを立てます。立案した学習計画は、受講者に共有します。
ステップ2. eラーニング教材やテスト問題・アンケートの準備・登録
eラーニング教材やテスト問題、集合研修の前後に配信する課題などを用意し、eラーニングシステムに登録します。
テストは、eラーニングによる学習の定着度を確認するために有効です。また、受講者のeラーニングへの満足度を図るアンケートは、管理者と受講者のコミュニケーション促進につながり、コンテンツや運用をブラッシュアップするために役立ちます。
ステップ3. 受講者登録、コース設定
eラーニングシステムでは、受講者の情報を一元管理できます。スムーズな運用に向け、受講者の氏名や年齢、性別、メールアドレス、所属や受講コースなど、必要な基本情報を登録しましょう。
必要に応じて、複数の教材や研修を組み合わせて学習コースを作成し、受講者とのひも付けも行います。
ステップ4. システム公開と周知
eラーニングシステムの運用体制が整ったら、システムを公開します。システム公開については、一斉メールなどで必ず受講者に周知しましょう。
ステップ5. 学習進捗管理とフォロー
eラーニングシステムには、個々の学習進捗を管理したり、テストの成績を閲覧し理解度を確認したりできる機能を持つものがあります。これらの機能を活用して受講者をフォローし、学習計画に沿って滞りなく学習を進められるように管理しましょう。
進捗が遅れている、成績が思わしくないという受講者には、メールや声かけにより学習誘導を行います。質問や問い合わせの窓口も設けましょう。
eラーニングの効果的な運用ポイント7選
eラーニング導入のメリットを実感するには、効果を引き出す運用を意識する必要があります。最後に、eラーニングを効果的に運用するための、7つのポイントを紹介します。
ポイント1:短時間集中型の学習の推奨
学習時間は「長ければ長いほどよい」というわけではなく、短時間で集中して学んだ方が、効率的に知識や技術を習得できるケースも多いものです。eラーニングによる学習の推奨時間は、1セット15~30分、1日当たり60~90分程度としましょう。
人が集中力を持続できる時間は15分ともいわれていますので、15分を目安に休憩を入れながら学習するのも有効です。例えば、知識を覚える「インプット15分」とテスト問題を解く「アウトプット15分」を、1日当たり各2セットずつ行うなど、時間配分を決めるとメリハリが付けやすくなります。
ポイント2:学習目標の明確化と最適なコンテンツの選定
eラーニング教材は、ベンダーが初期にセッティングしたものや自社で制作した独自のコンテンツなど、さまざまな種類があります。そのため、学習目標が定まっていないと「何から始めたらよいか」「最適なコンテンツは何か」が分からなくなってしまいます。
学習目標は、「資格取得」や「技術の習得」「テストで合格ラインを超える」など、具体的で明確なものにすることが大切です。
またeラーニング教材は、目標達成に役立つ内容であるかと同時に、学習画面のデザインや操作性において使いやすい教材かどうかも確認し、受講者にとって最適なコンテンツを選定しましょう。
ポイント3:マルチデバイス対応のシステムの選定
マルチデバイス対応のeラーニングシステムなら、社内のパソコンだけでなく、個人所有のスマホやタブレットなどでも利用可能です。移動時間や休憩時間など、隙間時間を学習に活用できます。
受講環境を限定しないで学べる手軽さから、「ちょっと確認しよう」「この時間に学べる内容はないか」と、受講者の学習意欲も高まるでしょう。
ポイント4:アウトプット機会の設計
eラーニング教材でインプットするだけでなく、アウトプットの機会も積極的に設けると、知識がより定着し、業務でも学習内容を生かせます。
例えば、テストの実施やレポート提出によってインプットの成果を測り、受講者の弱点を把握することができます。インプット内容を自分の言葉に置き換えて相手に伝えるディスカッションも、学習内容の理解を深めるのに役立ちます。
ポイント5:オフライン学習との組み合わせ
eラーニングにはオンライン学習ならではのメリットがありますが、コミュニケーション不足や受動的な学習に陥りやすいというデメリットも存在します。こういったデメリットを補うには、集合研修やOJTなどのオフライン学習を組み合わせた「ブレンディッドラーニング」が有効です。
受講者同士がオフラインの場で情報交換や近況報告などをし合うことが、学習へのモチベーションの維持・向上に貢献します。
ポイント6:個別フォローアップやモチベーション維持策
eラーニングシステムで学習の進捗や成績をチェックし、必要に応じて個別のフォローアップも行います。リマインドメールを送信する、対象者に直接声をかけるなどして、受講を促しましょう。
併せて、受講者がeラーニングを継続的に活用できるよう、モチベーション維持のための対策を実施するとよいでしょう。
たとえば、以下のような施策が学習意欲の向上・維持に役立ちます。
- 進捗に応じたバッジや修了証の付与
- 学習状況のランキング表示
- 学習内容を業務で実践した体験の共有
- 受講者コミュニティ(社内SNSなど)の活性化 など
ポイント7:学習データの分析と改善への活用
個々の学習状況やよく使用されているコンテンツ、テストやアンケートの結果など、eラーニングシステム内には膨大な学習データが蓄積されます。これらのデータを分析し、教育内容や方法の改善を行えば、受講者がさらに活用しやすいeラーニングシステムに近づけます。
eラーニング導入後は、最新情報の反映や教材の更新だけでなく、受講者が積極的に利用したくなるコンテンツやシステムへのブラッシュアップを定期的に行いましょう。
企業向けeラーニングシステム10件をポイントごとに比較! ⇒ 「eラーニングシステム徹底比較Book」を無料ダウンロード
まとめ
eラーニングは、パソコンやスマホ等の電子デバイスを用いて、インターネット経由で行う学習のことです。
企業・従業員はそれぞれ以下のような目的を持って、eラーニングを利用します。
企業の目的
- 従業員へのいつでも、どこでも学習できる環境の提供
- 従業員への平等な研修機会の提供
- 講師による研修の質・内容のバラつき防止
- 人材育成のコスト削減
- 教育担当者の負担軽減・業務効率化
従業員の目的
- 業務に役立つ知識を、自分のタイミングで学ぶ
- スマホ学習による、隙間時間の有効活用
- スキルアップ・キャリアアップにつながる効率的な学習
- 反復学習による知識の定着
また、eラーニングには以下のようなメリット・デメリットがあります。
企業のメリット
- 受講者に均質な学習を提供できる
- テキスト代や会場レンタル費用、会場までの交通費などの費用を削減できる
- 教育担当者の負担を軽減できる
- 修正・アップデートが随時可能で、最新の教材をすぐに配信できる
- 学習履歴を管理できる
- 個々に最適な教材や学習内容を提供できる
企業のデメリット
- 初期費用や、継続利用のための費用が発生する
- 導入時には運用に向けた準備や、教材購入・作成の手間がかかる
- 教材配信や学習管理のためのeラーニングシステムが必要
- 従業員がeラーニングを利用しない可能性がある
従業員のメリット
- 好きな場所・タイミングで利用できる
- 自分のペースで学習できる
- 多くの学習機会を得られる
- 学習の進捗が分かりやすい
- 映像や音声のある動画教材なら、さらに理解を深められる
従業員のデメリット
- 集合研修のようにその場で質問ができない
- 受講者同士の交流ができない
- インターネット環境や、eラーニング利用のための端末が必要
- 学習意欲がなければ活用し切れない
eラーニングの最新トレンドとして、以下の要素が挙げられます。
- 動画教材
- マイクロラーニング
- アクティブラーニング
- AI活用
eラーニングの効果的な使い方を、企業事例と共に紹介しました。
- 社内研修(トヨタ紡織株式会社)
- 新入社員研修(株式会社テンポイノベーション)
- コンプライアンス教育(株式会社タカラトミー)
- 店舗・現場教育(株式会社ルネサンス)
eラーニングの実施に必要なのは、以下の3点です。
- eラーニングシステム
- eラーニング教材
- 受講者への支援
eラーニングは、以下の5つのステップで運用をスタートします。
ステップ1. 学習計画の立案
ステップ2. eラーニング教材やテスト問題・アンケートの準備・登録
ステップ3. 受講者登録、コース設定
ステップ4. システム公開と周知
ステップ5. 学習進捗管理とフォロー
最後に、効果的な運用のための7つのポイントを解説しました。
- 短時間集中型の学習の推奨
- 学習目標の明確化と最適なコンテンツの選定
- マルチデバイス対応のシステムの選定
- アウトプット機会の設計
- オフライン学習との組み合わせ
- 個別フォローアップやモチベーション維持策
- 学習データの分析と改善への活用
教育担当者の負担を軽減しながら効果的な学習を提供できるeラーニングは、企業・従業員双方に多くのメリットをもたらします。成功事例を参考にしながら、より効果の高いeラーニング使い方を検討してみてはいかがでしょうか。
- 学校法人産業能率大学総合研究所「通信教育およびeラーニングの活用実態調査」 ,(閲覧日:2025年5月19日) ↩︎