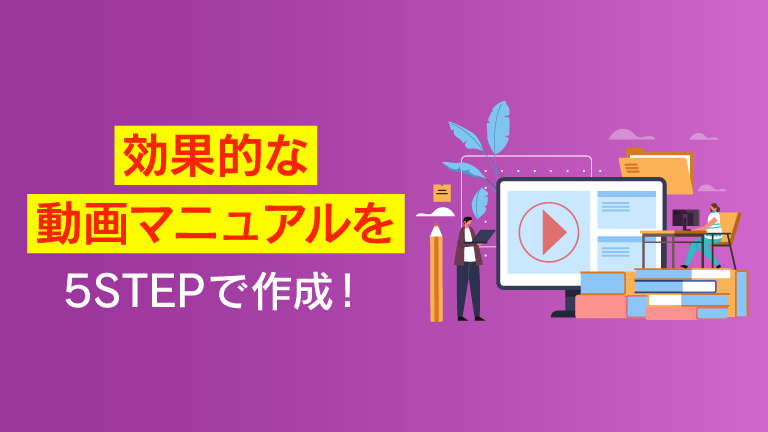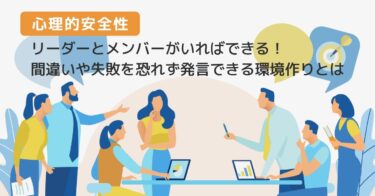「誰もが直感的に理解できる動画マニュアルを導入したい」
紙やPDFによる業務マニュアルは、状況により「使いにくい」「分かりにくい」と感じることもあります。このような時には動画マニュアルがおすすめです。
株式会社スタディストが実施した第1回「動画マニュアル実態調査1によると、業務中に動画マニュアルを使用したことがある回答者(2,206人)のうち、およそ7割が、「動画マニュアルで業務の理解が進むと感じる」と回答しています。
企業の教育担当者としては、従業員が手軽に、そして効率的に業務を学べる動画マニュアルの作成のため、作成手順や役立つツールについて知っておきたいところです。
この記事では、動画マニュアル作成の手順やツールの特徴、作成時の注意点などについて解説します。内製・外注のメリット・デメリット、企業の活用事例も紹介しますので、実用性の高い動画マニュアル作成の参考にしてください。
「スキル管理、何から始めれば…?」を解決! ⇒「スキルマップの基礎ブック」を無料でダウンロード
「従業員一人ひとりに必要な教育プログラムをこちらで用意するのには限界がある」このように感じておられる人材開発部門の担当者、教育管理者の方はいらっしゃいませんか。人事部のクライアントは従業員です。「個」が重視される時代、企業[…]
AIで要約
- 動画マニュアルは、紙媒体より理解しやすく、接客方法・マナー、調理、機械の操作など動きのある内容の解説に向いています。
- 動画マニュアルの作成には、企画・構成、台本作成、撮影・録音、編集、公開・配信の手順があります。無料・有料の編集ツールが利用可能です。
- 導入メリットとして、研修の効率化、外国人材の育成促進、教育担当者の負担軽減、コスト削減などが挙げられます。
動画マニュアルが有効な分野とは?
動画マニュアルとは、業務の内容や手順などを映像と音声による動画で示したものです。画像や文章のみの説明では分かりにくく、理解に時間がかかってしまうような内容も、動画なら短時間で必要な情報を収集できます。
動画マニュアルは、伝えたい内容に動きのあるものに向いています。例えば調理の手順や接客方法・マナー、機械の操作手順などは、文章のマニュアルよりも理解が深まります。
ベテランから若手への技能伝承、作業現場での安全教育・指導といった場面では、直感的に理解しやすい動画マニュアルが特に有効です。
「分かりやすいマニュアルで、未経験者を早く一人前に育てたい」従業員が新しい業務に携わる際、マニュアルがあれば安心して取り組めます。他にも人材の早期育成、業務の属人化防止、業務品質の均一化など、マニュアルにはさまざまなメリットがあり[…]
動画マニュアルの作成手順とポイント
ここでは、動画マニュアル作成の手順を解説します。各ステップのポイントも知り、多くの従業員が活用できる動画マニュアルを実現しましょう。
企画・構成
まずは、どのような動画マニュアルを作るのか、構成を練ります。企画段階では、以下の内容を明確にします。
- テーマ
- 活用シーン
- ターゲット層
- 全体の流れ
- 各項目の目的・内容
マニュアルは情報に不足がないことが大切ですが、1つの動画に多くの情報を詰め込み過ぎると、「この動画は何を伝えたいのか」が分からなくなってしまいます。動画は1テーマにつき1つ、長くても3分程度に収めるのが理想です。
台本作成
動画マニュアルは、台本を作成してから撮影すると撮り直しのリスクを避けられます。構成に沿って集めた情報も参考にしながら、細かく撮影内容を決めましょう。
台本は、文章と絵コンテの大きく2つの形式があります。どちらの形式を選んでも問題ありませんが、以下の内容が分かることが重要です。
- 動画マニュアルの流れ
- 時間ごとの動きや内容
- 挿入する図表やテロップ
- ナレーション、せりふ
台本作成時は、ターゲット層も意識します。新入社員や外国人従業員、ベテラン従業員など、利用者のスキルや理解度に合わせて、解説の順序や内容を工夫しましょう。
撮影・録音
作成した台本に沿って、撮影・録音を行います。手ぶれ防止のために、カメラを固定するスタンドがあると便利です。昨今はスマートフォンのカメラも機能性が上がっているので、スマートフォンで撮影しても問題ありません。
スマートフォンのカメラは、さまざまな音を拾ってしまいます。そのため、録音には外付けマイクを使うと、せりふやナレーションがクリアに聞こえます。
撮影場所や時間帯によっては、映像が暗くなることもあります。必要に応じて照明を使用するだけでも、動画のクオリティーが上がります。
撮影時には、1つのシーンをさまざまな角度から撮るなどの工夫をしましょう。引きの映像だけでなく、拡大した映像もあると、重要な部分を示しやすくなります。
また、映像とナレーションは同時に撮影せず、撮影した映像に別撮りしたナレーションを付けた方が、動作と説明のタイミングを合わせやすく、撮り直しのリスクが低くなります。
編集
撮影・録音した映像や音声を編集し、動画マニュアルを完成させます。編集に使用するツールは、無料・有料のものがあります。次章でそれぞれの特徴を解説しますので、参考にしてください。
編集時には動画が長過ぎないか確認し、必要に応じてカットします。また、以下のような編集テクニックを活用し、飽きさせない工夫をすることも大切です。
- テロップや見出しは、分かりやすい書体や文字の大きさにする
- 図解や矢印を使い、要点を伝える
- 動画と静止画を組み合わせ、メリハリを付ける
- 動画の内容がより伝わるナレーションを挿入する
- BGMを活用する
編集した動画は、関係者からフィードバックを得て改善すると、よりよい仕上がりになります。チームメンバーや、マニュアルを使用する予定の部署の人などに事前に確認してもらい、適宜修正しましょう。
公開・配信
動画マニュアルが完成したら、公開・配信します。一般ユーザー向けの動画マニュアルは、YouTubeなどの動画投稿サイトで公開するケースも多いですが、社内向けの動画マニュアルは、社内システムと連携し、サーバーやクラウドにアップするのが一般的です。
社内のパソコンやタブレットだけでなく、スマートフォンでも閲覧できるようにすると、従業員は好きなタイミングでいつでも動画マニュアルを確認できます。アクセス権限をどう設定するかも、公開・配信前に決めておきましょう。
メリット多数!動画マニュアルを統合型LMS(学習管理システム)CAREERSHIPで配信 ⇒ 動画ストリーミング配信機能について詳しく見る
【無料・有料】動画マニュアル作成ツールの特徴
動画マニュアル作成に用いる編集ツールはさまざまな種類があり、無料・有料の両方があります。それぞれのツールの特徴を解説します。
無料ツール:PowerPointやiMovieなど
無料で利用できる動画マニュアル作成ツールには、PowerPoint2(インストール済みの場合/Microsoft社)やiMovie3(Apple社)などがあります。また、有料ツールの機能を制限した無料版が利用できるサービスもあります。
無料のツールは、使用感を気軽に試せるのがメリットです。スマートフォンで撮影した動画を挿入できるだけでなく、専用アプリをダウンロードして、スマートフォンでの編集も可能とするツールが増えています。
ただし、有料ツールと比べると機能が少なかったり、サポートが充実していなかったりするのは、無料ツールのデメリットです。また、ツールによっては提供企業のロゴが消えない、商用利用できないなどの制限もあるので、社内での動画マニュアル作成・使用に支障がないか事前に確認する必要があります。
有料ツール:多様なニーズに対応するサービス
有料ツールは無料ツールよりも機能が充実しており、動画編集のスキルがなくても、スムーズにマニュアルを作成できます。月額で利用料を支払うものと、買い切りでライセンスを取得するものの大きく2つに分かれ、費用はサービスによって異なります。
企業でのマニュアル作成を想定したツールは、月額では数万円~、買い切りでは30万、40万円~と安価でないケースが多いです。その代わり、音声から字幕や翻訳を自動で生成したり、手順に沿って操作すれば数分で動画マニュアルが完成したりと、機能性が高いのが特長です。
また、操作手順や不明点について、メール・電話・チャットなどで簡単に問い合わせができる窓口が設置されています。ツールを活用するために手厚くサポートしてくれるので、費用対効果は高いといえるでしょう。
スマートフォンでの撮影・編集に対応しているツールが一般的ですが、中には「編集はパソコンのみ」という場合もあるため、スマートフォンやタブレットでの編集を想定している場合は、事前確認が必要です。
動画マニュアル作成のメリット
動画マニュアルには多くのメリットがあります。ここでは主なものを5つ紹介します。
紙のマニュアルと比較して理解しやすい
写真やイラスト、文字だけで構成される紙やPDFのマニュアルは、複雑な手順を伝えるのが難しいケースもあります。動画マニュアルは、映像や音声で直感的に内容を伝えられ、紙のマニュアルよりも理解しやすいといえます。
研修の効率化・効果向上
動画マニュアルはいつでも繰り返し確認でき、例えば研修前に公開すれば、従業員は事前に内容を把握でき、研修の効率化を図れます。また、研修後にも分からなかった点を短時間で振り返れるので、学びの効果向上にも寄与します。
外国人従業員の早期育成
昨今は外国人を積極的に採用する企業も増えています。日本語に不慣れな外国人従業員が業務を理解するためには、個々の言語に合わせたマニュアルが必要ですが、外国語への翻訳は容易な作業ではありません。
その点、動画マニュアルは視覚的に作業の手順や業務内容を理解でき、早期育成を実現できます。さらに多言語対応の自動翻訳機能を搭載したツールを使えば、外国人従業員向けのマニュアル作成も支障なく行えるでしょう。
教育・研修担当者の負担軽減
業務未経験の従業員には、丁寧な指導や研修が必要です。しかし、教育担当者は自身の業務もあるため、長時間にわたって指導するのは難しいのが現実です。
動画マニュアルを利用すれば、教育担当者は、従業員が動画マニュアルを見て生じた疑問点を中心に対応すればよいので、指導に割く時間の大幅な削減が可能です。また、業務の重要なポイントがまとめられた動画マニュアルは、従業員が自発的に学びやすく、効率的にスキルを身に付けられます。
コスト削減
紙のマニュアルは、一人一人に配布するために印刷が必要です。インクや用紙などのコスト、印刷・製本にかかる手間や時間は、マニュアル更新のたびに発生します。
動画マニュアルは、マニュアルが必要な従業員がどれだけ多くても、完成した動画へのアクセス権限を付与するだけで配布が完了します。紙のマニュアルにかかるインク・用紙代や製本などのためのコスト削減が可能です。
ペーパーレス化でSDGsに貢献できるのも大きなメリットでしょう。
動画マニュアル作成の注意点と対策
動画マニュアル作成によって期待できるメリットは多くありますが、導入にあたって注意したいポイントが2点あります。対策と共に解説します。
高齢従業員に配慮が必要な場合も
高齢者は若年者に比べ、動画マニュアルの内容理解が困難な傾向にあることを示す実験結果が公表されています4。
実験では、若年者と高齢者を対象に「マニュアルに基づく組み立て課題」に取り組んでもらいました。すると、若年者は静止画マニュアルよりも動画マニュアルを用いた方が課題遂行時間が短かったのに対し、高齢者は動画マニュアルの方が遂行時間が長かったのです。
動画マニュアルは短時間で多くの情報を収集できるのがメリットですが、高齢者にとっては、さまざまな情報の中から必要な内容を迅速に抽出するのが難しいようです。そのため、動画マニュアルを視聴する際に一時停止や早戻しをする回数が若年者よりも多く、課題クリアに時間がかかってしまいます。
高齢従業員に限らず、部分的な確認がしにくいのは動画マニュアルの不便な点です。業務や手順の一部を確認したいときには、該当箇所を探すのに時間を要します。
高齢従業員も活用できる動画マニュアルにするには、動画マニュアルを作業ごとに細かく分けて作成するのが有効です。また、動画マニュアルのチャプターごとの内容を紙やPDFに出力し、一目で確認できる資料を用意するのもよいでしょう。
動画の作成・閲覧環境整備が必要
動画マニュアル作成ツールは、パソコンやスマートフォンに専用ソフト・アプリをダウンロードして使用するのが一般的です。また、閲覧時にも動画を再生できる端末が必要で、クラウドに保存した動画マニュアルを閲覧する場合は、インターネット環境も整っていなければなりません。
動画マニュアル作成・閲覧のための環境整備として、会社が端末を用意する、もしくは従業員の協力を得て、私用の端末を利用するという2つの方法があります。私用の端末での作成・閲覧も可能にしたい場合は、計画段階で周知し、承諾を得るようにしましょう。
動画マニュアルは内製/外注どちらがよい?
動画マニュアル作成は、自社に担当者を置いて内製するだけでなく、専門業者に外注する方法もあります。内製と外注、それぞれのメリット・デメリットを把握し、自社に合った方法を見つけましょう。
内製のメリット・デメリット
内製のメリットは、以下の通りです。
費用を抑えられる
動画マニュアルの内製は、外注よりも費用を大幅に抑えられます。機材の準備は必要なものの、その後は従業員の人件費のみで作成が可能です。
修正・更新がすぐにできる
動画マニュアルの内容を変更したいと思った場合、外注すると時間がかかる上に追加費用も発生します。その点、内製ならすぐに修正・更新ができ、費用もかかりません。
ノウハウが蓄積される
動画マニュアル作成に従業員が携われば、構成や台本作りから動画の撮影方法、ツールを活用したマニュアル作成までのノウハウが、社内に蓄積されます。
ノウハウを生かしてよりよい動画マニュアルにブラッシュアップしたり、別の動画マニュアルをスムーズに作成したりできるのも、内製のメリットです。
一方、内製すると以下のようなデメリットが生じる場合もあるため、注意が必要です。
担当者の負担が大きくなる
動画マニュアル作成担当者は、通常業務にプラスして、機材の準備や撮影・録音、ツールの使い方の習得、編集作業など一連の作業を行うため、負担が大きくなる可能性があります。
通常業務を優先すれば動画マニュアル作成の進行が遅れ、反対に作成に注力すると、通常業務に支障を来しやすいのは、内製で注意したい点です。
期待するクオリティーに達しない
内製する場合、動画制作初心者が作成の担当者になるケースも多いため、完成した動画マニュアルのクオリティーが期待したものとは異なる可能性も出てきます。
クオリティーの高くない動画マニュアルは、時間をかけて作成したにもかかわらず、従業員の活用が想定以下になるかもしれません。
外注のメリット・デメリット
外注のメリットは、以下の通りです。
クオリティーの高い動画マニュアルを公開できる
動画制作を専門とする企業は、機材や編集ツール、ノウハウなどが備わっているので、外注すればクオリティーの高い動画マニュアルを作ってもらえます。
プロならではのアイデアや編集方法で、従業員も積極的に活用したいと思える動画マニュアルに仕上げ、閲覧による効果を最大化できるでしょう。
従業員の負担にならない
外注しても動画マニュアル作成の担当者は必要なものの、内製するほど大きな負担にならないのもメリットです。
担当者の役割は、主に委託先との打ち合わせや確認などで、台本作成や撮影・録音、編集など多くの作業は、委託先で進めてもらえます。そのため、担当者は通常業務に集中でき、動画マニュアル作成に遅れが出ることもありません。
動画マニュアル作成の外注で懸念されるデメリットは、以下の通りです。
費用がかかる
動画制作会社に外注すると、内製するよりも高額な費用がかかります。動画マニュアルを作成する場合、撮影と録音、編集作業を依頼するだけでなく、ディレクションや台本作成、撮影機材の準備なども任せるケースが多いです。
制作費用は委託先によりますが、数分の動画マニュアルでも1本当たり10万円程度はかかります。動画の本数や時間が増えたり、より高いクオリティーを求めたりすると、費用はさらに高額になります。
委託先を探す時間・労力が必要
多くの動画制作会社の中から、予算内で制作できる会社、安心して依頼できる会社を見つけるには、事前のリサーチが欠かせません。気になる会社をピックアップし、問い合わせや見積もり依頼をして委託先を決定するまでには、時間と労力を費やします。
社内の重要な情報を委託先に伝えなければいけないこともあるので、信頼できる会社かどうかの見極めは非常に重要です。守秘義務を徹底しているかはもちろん、要望に沿った動画マニュアルを作成するための提案をしてくれるかも、問い合わせの際に確認しましょう。
スケジュール通りに進まない
委託先が決まって動画マニュアル作成が始まっても、動画マニュアル作成にあたり内容を理解してもらうためには、一定の時間を要します。また、繁忙期には自社で決定したスケジュール通りに引き受けてもらえない可能性があります。
外注する場合は、動画マニュアルの完成までに時間がかかることを想定し、スケジュールに余裕を持たせます。また、盛り込んでほしい内容を分かりやすく説明したり、撮影のために事前に現場を確認してもらう日を設けたりして、スムーズに作業を進行させましょう。
「まなびのプロ」による動画マニュアルの制作も可能! ⇒ライトワークスの教材制作サービスを詳しく見る
動画マニュアルの効果測定と改善
動画マニュアルは一度作成したら終わりではなく、従業員が十分に活用できるよう、ブラッシュアップしていく必要があります。効果測定と改善の方法として、大きな3つのポイントを紹介します。
視聴状況の確認、アンケートの実施
視聴状況や動画マニュアルによる効果、改善点などは、次のような評価指標で確認できます。
- 視聴回数・頻度
- 動画マニュアルによる業務効率化の度合い
- 動画マニュアルへの満足度 など
従業員向けにアンケートを行い、4~6段階で評価してもらうとよいでしょう。加えて自由記述で改善してほしい点を具体的に示してもらうと、適切な修正・更新に役立ちます。
アクセスログ分析による改善点の抽出
アクセスログとは、サーバーやネットワーク、ソフトウエアへの接続履歴や、ユーザーの操作などを記録したデータです。アクセスログを分析すると、従業員がいつ、どこから動画マニュアルを閲覧したか、動画のどのあたりを視聴したかなどが分かります。
閲覧数の多い・少ない層、何度も見られているシーンなど、アクセスログ分析で明らかになった結果から改善点を抽出するのも、1つの方法です。
効果的なPDCAサイクルの構築
PDCAサイクルとは、業務・品質の改善に向け「Plan(計画)」、「Do(実行)」、「Check(評価)」、「Action(改善)」という4つを繰り返す手法です。
「評価で可視化された課題を改善し、新たな目標のためのアクションプランを立て、実行する」というサイクルを構築できれば、必要な情報を分かりやすく伝え、多くの人に活用される動画マニュアルに近づけるでしょう。
動画マニュアルを作成・活用している企業の事例
最後に、動画マニュアル作成・活用の企業事例を紹介します。
住友商事株式会社
大手総合商社の住友商事株式会社では、世界各国で展開するビジネスの規模が拡大するにつれて労働災害件数も増加傾向となる中、グローバルな労働安全教育の必要性を認識し、準備を進めました。
受講者には言語や慣習の壁を超えて基礎知識を学習してもらう必要があるため、画一的な概念系のテキスト・コンテンツではなく、映像をベースとしたeラーニング教材を使用した教育を行うことにしました。
動画教材の制作は、同社のシナリオ案をベースとして、受講者が労働災害に「リアルな危機感」を持てるよう、事故の怖さや痛さをしっかり伝えることにこだわって進められました。
リアリティに対する受講者の評価は高く、「事故の怖さを実感した」、「フォークリフトと人が激突するシーンがどこでも起きうることだと思った」という感想をもらえました。
労働災害に対する理解を深めた従業員から、「自分たちが事故にあわないためにどんな対策があるのか」「これは労災に該当するか」といった問い合わせも来るようになりました。
同社は、今後もリアリティと教育コンテンツとしての高い完成度の両方を兼ね揃えた教材を制作していきたいとしています。
この事例の詳細は以下のリンクからご覧いただけます。
企業が、世界各国、さまざまなビジネス分野で事業を拡大していくなかで、労働災害発生リスクも増加しています。大手総…
蓮台寺温泉 大地の彩 花月亭(株式会社喜久多)
株式会社喜久多が経営する静岡県下田市の旅館、蓮台寺温泉「大地の彩 花月亭」は、新人スタッフのスキル向上に向けた、接客プロセスの動画マニュアル作成を行いました。
花月亭には紙媒体のマニュアルは存在していました。しかし、内容は一般的なもので自社サービスの実態にマッチしておらず、新人スタッフの育成は、担当の指導者が時間をかけて細かく行っていました。
動画マニュアルでは、チェックインからご案内、食事のセット・提供など、接客スタッフの一連の業務が学べます。実態に合わせて作成されたシナリオに沿った動画は、顧客満足に影響を与えるポイントを、音声やテキストで強調しているのも特徴です。
動画マニュアルは、スタッフがいつでも閲覧できるようインターネット上に限定公開されています。また、施設内のマニュアルが必要な場所では、表示されたQRコードをスマートフォンで読み込むことで、関連動画の閲覧が可能です。
花月亭は動画マニュアル作成により、従業員ごとのサービスのばらつきをなくし、サービス品質の向上を実現しました。また、新人スタッフが規定のスキルに到達するのに1週間から1カ月かかっていましたが、動画マニュアルにより3日から1週間で到達できるようになるなど、多くのメリットを得ています。
株式会社テンポイノベーション
店舗物件の転貸借事業を展開する株式会社テンポイノベーションでは、各チームに対する新入社員研修に約100時間を費やしていました。加えて、営業担当が一人前のレベルに到達するまでに2〜3年かかり、定着率も不安定な状態でした。
そこで、新入社員の早期戦力化・定着率向上と研修担当者の負担軽減を実現するため、体系的な新入社員研修の動画教材を制作することにしました。
動画教材の導入により、研修の質を高いレベルで均一化でき、常に同じクオリティーの研修を提供できるようになりました。さらに、動画にアニメーションを活用することで、イメージの行き違いや説明コストが激減しました。
このように、動画教材の導入後は研修担当者の負担が大きく軽減され、彼らが自分の業務に時間を使えるようになりました。
また、新入社員の離職がほとんどなくなりました。要因の一つとして、動画教材の活用による成長の早さや自信の高まりもあると考えられています。
同社は、事業成長の基礎となる人材育成は会社として注力すべきと考えており、動画教材の導入で人材育成の基礎を築けたことは、長い目で見て良い選択だったとしています。
この事例の詳細は以下のリンクからご覧いただけます。
店舗物件の転貸借に特化した不動産事業を展開する株式会社テンポイノベーションは、新入社員の早期戦力化・定着率向上…
まとめ
動画マニュアルは、業務や手順の正確な理解、効率的な学びを促進します。調理、接客、機械の操作手順など動きのある内容を伝える方法として最適です。特に技能伝承、作業現場における安全教育といった場面で有効です。
動画マニュアル作成の手順は、以下の通りです。
- 企画・構成
- 台本作成
- 撮影・録音
- 編集
- 公開・配信
動画マニュアル作成ツールは、無料で利用できるものと有料のものがあります。無料ツールは手軽に機能を試せる点、有料ツールは多様なニーズに対応するサービスがある点が特長です。
動画マニュアル作成のメリットは、以下の通りです。
- 紙のマニュアルと比較して理解しやすい
- 研修の効率化・効果向上
- 外国人従業員の早期育成
- 教育・研修担当者の負担軽減
- コスト削減
動画マニュアル作成時には、以下の2点に注意が必要です。
- 高齢従業員に配慮が必要な場合がある
- 動画の作成・閲覧環境整備が必要
動画マニュアルは、内製と外注のどちらかで作成します。
内製のメリット・デメリットは以下の通りです。
メリット
- 費用を抑えられる
- 修正・更新がすぐにできる
- ノウハウが蓄積される
デメリット
- 担当者の負担が大きくなる
- 期待するクオリティーに達しない
一方、外注には以下のようなメリット・デメリットがあります。
メリット
- クオリティーの高い動画マニュアルを公開できる
- 従業員の負担にならない
デメリット
- 費用がかかる
- 委託先を探す時間・労力が必要
- スケジュール通りに進まない
動画マニュアル作成・配信後の効果測定と改善には、以下の3つの方法が有効です。
- 視聴状況の確認、アンケートの実施
- アクセスログ分析による改善点の抽出
- 効果的なPDCAサイクルの構築
最後に、動画マニュアル作成・活用に関する企業事例を紹介しました。
- 住友商事株式会社
- 蓮台寺温泉 大地の彩 花月亭(株式会社喜久多)
- 株式会社テンポイノベーション
クオリティーの高い動画マニュアル作成と、閲覧しやすい環境の整備ができれば、新入社員や外国人従業員、高齢従業員まで、幅広い層に活用されます。作成担当者の負担も考慮しながら、使いやすい動画マニュアルを目指しましょう。
人材育成の課題・解決方法を一冊にまとめました ⇒ LMS導入成功事例集を無料で読んでみる
- 株式会社スタディスト「第1回『動画マニュアル実態調査』3割がマニュアルを倍速視聴/8割が動画と画像を組み合わせたものを希望」,(閲覧日:2025年2月17日) ↩︎
- Microsoft「Microsoft PowerPoint」,(閲覧日:2025年3月3日) ↩︎
- Apple「iMovie」,(閲覧日:2025年3月3日) ↩︎
- 川上凜,田中伸之輔,長澤裕太郎,遠藤祐輝,原田悦子「動画マニュアルの優位性は高齢者にも見られるか?(1)『マニュアルに基づく組立課題』における年齢群間比較」,『日本認知心理学会第15回大会発表論文集』,2017,P1-19. ↩︎
参考)
観光庁「宿泊業の生産性向上事例集2」,2019年3月公表,https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/kihonkeikaku/jizoku_kankochi/kankosangyokakushin/saiseishien/content/001621212.pdf(閲覧日:2025年2月17日)