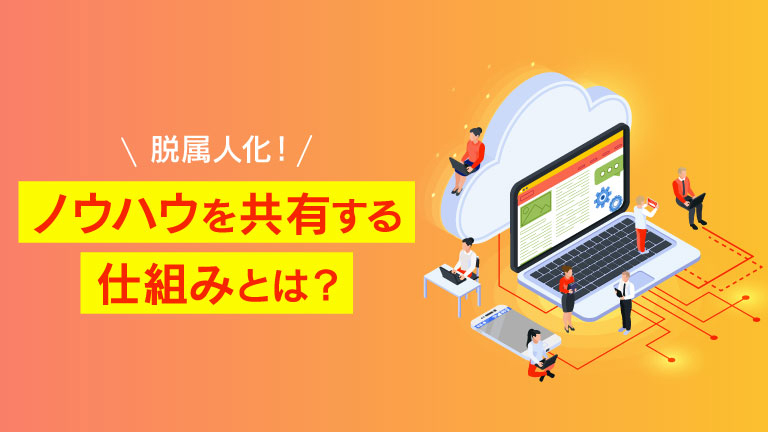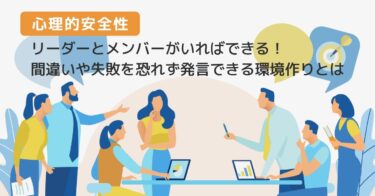「分かりやすいマニュアルで、未経験者を早く一人前に育てたい」
従業員が新しい業務に携わる際、マニュアルがあれば安心して取り組めます。他にも人材の早期育成、業務の属人化防止、業務品質の均一化など、マニュアルにはさまざまなメリットがあります。
しかし、株式会社フィンテックスが2024年4月に公表した「業務マニュアルの使用状況とイメージの調査レポート」1によると、「現在使用しているマニュアルに点数をつけるとしたら何点ですか?」という質問への回答で、「76-99点」は14.8%、「100点」は4.6%でした。
回答の約80%が75点以下であり、多くの従業員がマニュアルに課題を感じていることが分かります。
マニュアルは、単に業務の手順や内容を解説するだけでなく、分かりやすさや使いやすさを工夫して作成する必要があります。そして作成後は、活用方法やメリットを従業員に十分に理解してもらうことが重要です。
この記事では、マニュアル作成の重要性やメリット、作成の手順などをご紹介します。作成・活用のポイントや企業事例も知り、自社の業務や教育の効率化につながるマニュアル作成の参考になれば幸いです。
「スキル管理、何から始めれば…?」を解決! ⇒「スキルマップの基礎ブック」を無料でダウンロード
「従業員一人ひとりに必要な教育プログラムをこちらで用意するのには限界がある」このように感じておられる人材開発部門の担当者、教育管理者の方はいらっしゃいませんか。人事部のクライアントは従業員です。「個」が重視される時代、企業[…]
AIで要約
- マニュアルは、従業員の早期育成や業務効率化、教育負担の減少に役立ちます。
- マニュアルが不十分だと、ミスの増加や生産性の低下につながりやすいです。
- マニュアルは作成後、周知徹底し、定期的な改善が重要です。
なぜマニュアル作成が重要なのか?
マニュアルがあれば、教育担当者の不在時も、従業員は自律的に業務に取り組めます。
まずは、マニュアルとは何か、マニュアル作成のメリット、マニュアルの未整備によって起こる問題を確認しましょう。
マニュアルとは?手順書との違い
マニュアルとは、業務や従業員の教育、危機管理などについて具体的な手順やノウハウ、ルールを分かりやすくまとめた資料のことです。
マニュアルと混同しやすい「手順書」とは、以下のような違いがあります。
マニュアル:高い成果の獲得や目標達成のために、業務全体の流れや方法、ルール、その作業を行う理由などをまとめたもの。業務効率化やナレッジ共有に役立つ。
手順書:業務品質の安定を目的に、特定の作業の具体的な方法を示したもの。マニュアルよりも扱う範囲が狭い。
マニュアルの役割とメリット
マニュアルの役割とメリットは、以下の通りです。
教育負担の減少と業務効率化
業務の手順や注意点、よくある疑問の解決方法などが記載されたマニュアルがあれば、従業員は各自で業務の手順や注意点を把握し、滞りなく業務を進められます。
教育担当者は付きっきりで業務を教える必要がなく、従業員がマニュアルを読んだ上で生じた疑問を中心に対応すればよいため、効率良く育成を進められます。未経験者も早期に独り立ちが可能です。
このような作業のスピードアップや教育負担の減少により、業務効率化が期待できます。
業務の属人化防止とナレッジの共有
特定の従業員しか詳しい手順やノウハウを知らない業務があると、担当者が不在になった際に代わりに進められる人材がいないため、業務に支障を来す可能性があります。
業務に必要な知識や技術、個々の持つノウハウなどの情報をまとめ、誰でも業務を遂行できるように整備されたマニュアルは、業務の属人化防止と、業務に役立つナレッジの効率的な共有のために有効です。
業務品質の安定
統一されたマニュアルがなく、個々が自分の業務メモに従って業務を遂行すると、経験の差や手順の違いなどにより業務品質に差が生じやすくなります。反対に、メンバーが同じマニュアルにのっとって正しい手順や方法を実践すれば、一定の業務品質を保つことが可能です。
マニュアルには、従業員一人一人の能力や経験などにかかわらず、業務品質を一定のラインで安定させることができるというメリットがあります。
コンプライアンス強化
昨今はコンプライアンス(compliance:法令順守)が叫ばれており、企業は従業員の意識と業務の状況を適切に管理する必要があります。そのためにも、マニュアルが役に立ちます。
例えば、個人情報の取り扱い方法や職場の安全管理、法令違反の防止など、コンプライアンスに関する事項をマニュアルに織り込むとよいでしょう。それにより、従業員のコンプライアンス違反を未然に防止できます。
コンプライアンス強化につながるマニュアルの整備は、取引先や顧客からの信頼度を高めるためにも有効です。
関連eラーニング教材 ▶ コンプライアンス研修
マニュアルの未整備によって起こる問題
内容が更新されない、足りない情報が多いといった不十分なマニュアルしかなかったり、そもそもマニュアルがなかったりする場合、以下のような問題が発生しやすくなります。
ミスの発生
マニュアルが最新の状態でないと、マニュアル通りに業務を進めた従業員がミスを起こす確率が上がります。
また、マニュアルがない場合、指導者によって教育内容にばらつきが生じたり、個々が自己流で業務に取り組んだりするケースが増え、ミスの発生につながります。
生産性の低下
長らく情報が更新されていないマニュアルは、内容の不備や旧来の非効率な方法の記載により、従業員の生産性を低下させる可能性があります。
マニュアルがない場合は個々が独自の方法で業務を進めるしかなく、試行錯誤に多くの時間や労力が費やされる分、生産性が低下しやすくなるでしょう。
教育コストの増加
マニュアルの内容が不十分だったり、マニュアルがなかったりすると、従業員は疑問点や不明点を自分で調べて解決することが難しくなり、教育担当者への質問回数が増加します。教育担当者はその都度対応をしなければならず、業務がスムーズに進みません。
他の従業員に業務を引き継ぐ際にも、口頭やメモでのやり取りなどに時間がかかり、教育コストが増加してしまいます。
以上のような問題を避けるため、企業には「従業員がしっかり活用できるマニュアル」の作成が求められます。どのようなマニュアルを用意すべきか、次章で見ていきましょう。
「誰もが直感的に理解できる動画マニュアルを導入したい」紙やPDFによる業務マニュアルは、状況により「使いにくい」「分かりにくい」と感じることもあります。このような時には動画マニュアルがおすすめです。株式会社スタディストが実[…]
企業向けマニュアルの種類と作成目的
企業で活用されるマニュアルは、大きく4種類あります。ここでは、それぞれのマニュアルがどのようなものなのか、作成目的とともにご紹介します。
業務マニュアル
業務マニュアルは、業務の概要や流れなどをまとめたものです。作成の目的は「業務の全体像をつかむこと」で、業務の効率化や属人化防止、生産性向上など、さまざまな役割があります。
企業のどの部門にも必要ですが、総務や人事、経理などの管理部門(コーポレート部門)では、特にマニュアルが重要な役割を果たします。採用や研修、給与計算、社会保険関連や異動・退職の手続きなど、1つ1つの業務量はそこまで多くはないものの、業務が多岐にわたるためです。
これらの業務の中には発生頻度が低いものも多々あり、加えて、社内イベントなどのように着手から終了までに長い期間を要する業務も定期的に発生します。口頭では引き継ぎが難しい内容も少なくないため、マニュアル作成が欠かせません。
教育マニュアル
新入社員研修や階層別研修、OJTなどで使用される教育マニュアルは、効率的な人材育成を目的として作成されます。
教育担当者の負担を軽減するだけでなく、研修・指導の均質化につながり、研修対象者の理解度や習熟度の向上にも役立ちます。
危機管理マニュアル
危機管理マニュアルは、災害や事故、不祥事など企業におけるリスクに対し、顕在化の防止と発生時の対応について方針や取るべき行動を示したものです。リスクの予見・発生時に、迅速かつ適切な対応を取り被害を最小限にとどめることを目的に作成されます。
地震・火事などの自然災害対策の他、情報漏えいなどの情報セキュリティ事故、労働災害、ハラスメントなどの対策をまとめたものも危機管理マニュアルに分類されます。
規定集/規程集
就業規則、人事制度、評価制度など、企業のルールを明確に示す規定集(規程集)は、組織の安定やコンプライアンスの徹底を目的に定めます。
社内規定を明確化し従業員が同じルールに従うことで、公平性が保たれ、トラブルの発生防止にもつながります。
eラーニング教材を効果的に作る方法を詳しく解説! ⇒ 「eラーニング作り方の教科書」を無料でダウンロードする
分かりやすく使いやすいマニュアルの構成要素
企業は、「従業員に分かりやすい内容であること」「活用しやすいこと」を意識してマニュアルを作成する必要があります。有用性の高いマニュアルに仕上げるための、5つの構成要素を見てみましょう。
目的
業務の標準化や新入社員の早期戦力化など、マニュアルによって達成したい目的を明確に定めます。
目的が明確なマニュアルは、「マニュアルで解決したい問題」「この業務が必要な理由」といったマニュアル作成の背景もはっきりします。従業員が内容を理解しやすくなり、活用しようという意欲も高まります。
対象読者
対象読者によってマニュアルの内容は変わるので、「誰に向けたマニュアルなのか」を明記します。例えば、同じ業務のマニュアルでも、新入社員・未経験者向けと経験者向けでは、求めるレベルや掲載すべき情報が異なります。
また、対象読者を明記しておけば、従業員は「自分がどのマニュアルを読めばよいか」がすぐに分かります。
手順、ルール、注意事項
業務の手順やルール、注意事項は、マニュアルのメインとなる内容です。
特定の業務について、スムーズに手順やルールを理解でき、誰が行っても安定した業務品質を確保できるよう具体的かつ簡潔な説明にします。
分かりやすく、興味を引くマニュアルに仕上げるには、フローチャートや図解を活用したり、吹き出しや目立つ色を使って要点や重要事項を記載したりするのもよいでしょう。理解度を確認するチェックリストの導入も有効です。
用語解説
マニュアルによっては、専門的な用語が多くなる可能性があります。業界用語や社内用語などの専門用語は分かりやすい表現に言い換えると、内容を理解しやすくなります。
職種・業種によっては、関連法令を引用して背景や経緯を補完するといった工夫も必要です。
検索機能
マニュアルは一通り目を通すだけでなく、分からないことがあったり、もう一度確認したいと思ったりした際などに、繰り返し利用されます。
このとき、目次やキーワード検索機能によって必要な情報に素早くアクセスできると、より効率的に活用でき、従業員のマニュアルへの満足度もアップします。
マニュアル作成のステップとポイント
マニュアル作成には多くの時間と労力を要するため、効率的に進めることが重要です。ここでは、マニュアル作成のステップと各ステップのポイントを解説します。
企画・内容の検討
まずは、マニュアルの内容を検討します。企画段階で以下の事項を決めておくと、その後の流れがスムーズです。
- マニュアル作成の目的
- 対象読者
- 担当者
- 使用するフォーマットやツール
対象読者は、新入社員や未経験者、より高度な知識・技術を得たい経験者など、範囲も明確にします。マニュアルの対象となる関係部署との連携も、企画段階で行っておくとよいでしょう。
また、マニュアル作成は担当者を1人に限定せず、チームで作成しましょう。マニュアル作成の作業は通常業務の合間を縫って行うので、1人の負担を小さくし、効率を上げるためです。
加えて、担当者が1人の場合、その人の思い込みや独自の考えがマニュアルに反映されてしまう可能性があります。これを避けるためにも、プロジェクトとしてチーム全員で全体像を把握しながら作業を進めましょう。
スケジュールの決定
内容が決まったら、マニュアル作成のスケジュールを決定します。「いつから使用するのか」「いつまでに完成していなければならないか」を明らかにし、運用予定時期から逆算してスケジュールを調整します。
例えば、新入社員向けの業務マニュアルの場合、一般的に3~4月までに完成させておく必要があります。この時期に間に合わせるには、4-3.以降のステップをどのように進めていけばよいかを計算し、余裕を持って完成させられるスケジュールを組みましょう。
情報収集
必要な情報を簡潔かつ正確にまとめた、分かりやすいマニュアルに仕上げるには、情報収集が欠かせません。現場担当者をはじめ、業務に関わる部署や従業員にヒアリングをするなど、より多くの情報を集めましょう。
収集した情報は、関連法令や社内規定に違反していないかを必ず確認した上で整理することも大切です。
タイトル、見出し、構成の整理
情報収集までのステップを完了したら、テーマに沿ってタイトルや見出し、構成を考えます。
例えば、新入社員向け教育マニュアルの場合、大きなテーマは「新入社員にビジネスマナーや自社の業務・ルールなどを理解してもらい、社会人としての基礎をつくること」です。
全体の構成については、まず「ビジネスマナー」や「社内規定」「業務内容」「ツールの使い方」など、マニュアルに必要な個別の要素を挙げます。そして最適な順序で解説できるように組み立て、目次を見たときに各項目で何を説明しているかが分かる見出しを考えます。
このように作業を進めることで、作成目的やテーマに基づいた、一貫性のあるマニュアルを作成できます。
マニュアルの執筆
収集・整理した情報を基にマニュアルを執筆する際には、5W1Hを意識した文章、図表やイラストの導入など、分かりやすい表現にします。内容によっては事例を用いて具体的に解説することも有効です。
執筆時には、最新情報が反映されているかも確認します。ただし、ビジネス環境は日々変化するため、完璧なマニュアルを追求すると終わりのない作業となってしまいます。公開・配布後も必要に応じて随時更新することを前提に、100点を目指さず、どこかで区切りを付けましょう。
公開・配布
完成したマニュアルは、スケジュールに沿って公開・配布します。マニュアルは業務未経験者だけでなく、現在対象の業務に就いている人にも、業務の見直しや新たな発見につながる有用な資料となります。
マニュアルの公開・配布方法は、デジタルと紙媒体の大きく2つです。昨今は若手従業員向けにデジタル化する企業も増加しており、スマホやタブレットなど、さまざまなデバイスで閲覧できるマニュアルの整備が進んでいます。
また、企業・組織内のみで利用可能なイントラネットを介して公開することも1つの方法です。
デジタルと紙媒体、2つの公開・配布方法を併用すると、より多くの従業員に活用してもらえる可能性が高まります。
マニュアル作成・管理に役立つツール
さまざまなツールを活用すると、マニュアル作成や管理の負担を軽減できます。ここでは3つのツールをご紹介します。
Officeテンプレート
Microsoft OfficeのWordやExcel、PowerPointは使い慣れている方も多いかと思いますが、白紙からのマニュアル作成は容易ではありません。
Officeテンプレートは、Wordなどのアプリケーション内にあらかじめ用意されている、定型的なフォーマットです。引継ぎ書やガントチャートのテンプレートを活用して、見積書や請求書、レポート、事業計画書などを作成できます。
テンプレートを活用すれば、目次や索引作成の手間を省ける他、各ページのレイアウトにも迷わず、スムーズなマニュアル作成を実現できます。
Officeテンプレートは、各アプリケーションやMicrosoftのホームページから無料で検索・利用が可能です。
参考)Microsoft「Office テンプレート」,(閲覧日:2025年2月3日)
マニュアル作成ツール
マニュアル作成ツールは、業務マニュアルをはじめとした各種マニュアルを効率的に作成できるツールです。内容に適したテンプレートを選択し、ガイドに沿って作業を進めるだけで、簡単に短時間でマニュアルが完成します。
一般的なマニュアル作成ツールには、以下のような機能があります。
- テンプレート
- バージョン管理
- 共同編集
- マルチメディア対応
- AIアシスト
- 自動翻訳
- 字幕自動作成 など
なお、マニュアル作成ツールの多くは、無料トライアル期間の後、月または年単位で利用料がかかります。無料トライアルを利用して、ツールの機能が自社に合っているか確認するとよいでしょう。
社内Wikiツール、ナレッジマネジメントツール
社内Wikiツールは、企業内におけるさまざまな情報を保管し、円滑な情報共有やコミュニケーションを促すツールです。また、ナレッジマネジメントツールは、個々の従業員が蓄積した知識やノウハウ(=ナレッジ)をデータ化して企業内で共有し、有効活用を図るツールです。
企業の生産性向上につながる、ベテラン従業員のノウハウや個人が持つ有益な情報を共有し、マニュアル作成に生かすことができます。
さらに、検索・閲覧が簡単で、更新や管理をしやすいという特長もあります。マニュアルだけでなく、スケジュールやTodoリストの共有、掲示板でのコミュニケーションが可能な製品もあり、企業内で活用の幅が広いことも、これらのツールを利用するメリットです。
無料のツールも存在しますが、多くの場合、無料トライアル期間の後、月額・年額でのライセンス契約が必要です。
ナレッジマネジメントツールについてはこちらの記事もご覧ください。
ナレッジマネジメントツールとは、従業員の知識やスキルをデータ化して共有・活用するためのツールです。ツールの目的・種類別に…
マニュアル運用を成功させるためのポイント
作成したマニュアルを、多くの従業員に長く活用してもらうためには、運用方法の工夫も必要です。成功に導くポイントは、以下の通りです。
マニュアルの存在の周知徹底、利用促進
分かりやすいマニュアルがあっても、従業員がその存在を知らなければ活用されなくなってしまいます。完成したマニュアルの公開・配布時には、「このようなマニュアルができました」という周知を徹底することが重要です。
さらにマニュアルの活用方法をテーマにした研修を行うと、周知と同時に利用促進も見込めます。
また、新たにマニュアルを作成したときだけでなく、変更や修正が生じた際にも、一斉メールやチャットなどで都度周知し、最新のマニュアルを活用してもらえるよう呼び掛けましょう。
自社に適したマニュアル作成ツールの選定
マニュアルの作成・管理のためのツールは、自社に適したものを選定します。
例えば、テレワークが多い企業や若手従業員が増加中の企業が、スマホや自宅のパソコンなどからの閲覧に対応していないツールを選んでしまうと、従業員がマニュアルを活用しきれない可能性があります。
反対に、年齢層が高く、スマホやパソコンに触れる機会の少ない業種や部署が、デジタルのみでマニュアルを公開しても閲覧する人は限られます。
また、マニュアル作成時はもちろん、更新作業のためにも、マニュアル作成担当者が使いやすいツールや媒体を選定しましょう。
定期的なアンケートによる利用状況の把握と改善
マニュアル公開・配布後には、定期的なアンケートで利用状況を把握します。
例えば、「どのようなときに活用しているか」「利用しやすいと感じるポイントは何か」の他、「利用していない理由」「どのようなマニュアルならもっと『利用したい』と感じるか」など、マニュアルに対する具体的な意見を集めると、改善に生かせます。
冒頭でもご紹介した「業務マニュアルの使用状況とイメージの調査レポート」2では、「業務マニュアルを見る頻度」について、最も多い回答は「2~3か月に1回程度」(22.2%)でした。
次いで多かった回答は「月に1回程度」「1年以内には見ない」(どちらも19.2%)で、約20%はマニュアルの利用頻度が年1回にも満たないという結果でした。
価値あるマニュアルを多くの従業員が活用し、さまざまなメリットを得るためにも、利用状況の把握と改善は欠かせません。
マニュアル管理担当者の設置
マニュアルは一度作成したら終わりではなく、業務やルールの変更に対応したり、従業員が活用しやすいものにブラッシュアップしたりするために、定期的な更新が必要です。
そのためマニュアルの管理や更新を行う担当者を設置します。担当者が不在でも管理や更新作業が滞らないよう、何人かで役割を分担して管理すると安心です。また、引き継ぎが発生した際にスムーズに行えるよう、「こういうときに更新する」といった更新のルールもあらかじめ決めておきましょう。
マニュアル作成・活用の企業事例
最後に、マニュアル作成・活用の企業事例をご紹介します。
株式会社イーソーコドットコム
倉庫や物流施設などの空間活用に向けたサービスを展開する株式会社イーソーコドットコムでは、営業担当者向けのマニュアル制作プロジェクトを立ち上げています。
同社では、新入社員はジョブローテーション研修でおよそ半年間かけてさまざまな業務を学びます。配属決定は10月のため、研修で学んだ業務を時間がたってから行うこともあります。
また、配属先によって、メインに加えてサブで関わる企業が発生するケースもあり、兼務となる場合は思い出さなければいけない業務がより多くなります。中には、頻度は少ないものの手順通りに行わなければいけない業務も存在し、こうしたシーンにおいてマニュアルは重宝されます。
そこで、役職者を中心に営業担当者全体で打ち合わせを重ね、電話対応や初接客に役立つトークスクリプトを作成し、新人営業担当者のよりどころとしています。
同社はマニュアルの更新に加え、新人営業担当者が1年目、2年目から即戦力として活躍できるよう、また3年目以降もよりレベルアップできるよう、状況に合わせて段階ごとに異なるトークスクリプトパターンを追加するなどの工夫をしています。
新人営業担当者はもちろん、経験を重ねた営業担当者もさらに成長できるようなマニュアル作成によって教育体制の強化に努めています。
株式会社東具
POP広告やディスプレイなど、インストアの販促ツールの企画・制作などを行う株式会社東具は、近年多発する自然災害に備え、災害対策マニュアルを用意しています。
同社は大阪本社、東京支店、福岡支店、物流センターの4つの拠点を構えており、それぞれに規模や環境が異なります。そこで、愛知県の事業者用防災マニュアルを参考に、拠点ごとに内容を最適化したマニュアルを作成しました。
マニュアルでは、基本方針や災害時の組織体制の他、緊急連絡網も定めています。従業員全員と連絡を取ることが困難な状況でも、組織図に沿った連絡網を活用し、安否確認や緊急動員が可能です。
また、同社は災害予防対策として、9月1日に非常用備品の数量や保存状態を確認し、災害対策室長に報告する取り組みも行っています。
さらに、年1回以上の防災訓練や防災教育、災害対策マニュアルの定期的な見直し・修正などで従業員の防災意識を高めています。
まとめ
マニュアルとは、業務や従業員の教育、危機管理などについて具体的な手順やノウハウ、ルールを分かりやすくまとめた資料のことです。混同しやすい「手順書」とは以下のような違いがあります。
マニュアル:高い成果の獲得や目標達成のために、業務全体の流れや方法、ルール、その作業を行う理由などをまとめたもの。業務効率化やナレッジ共有に役立つ。
手順書:業務品質の安定を目的に、特定の作業の具体的な方法を示したもの。マニュアルよりも扱う範囲が狭い。
マニュアル作成のメリットは、以下の通りです。
- 教育負担の減少と業務効率化
- 業務の属人化防止とナレッジの共有
- 業務品質の安定
- コンプライアンス強化
マニュアルがない、あっても内容が不十分といった場合は、以下のような問題が生じやすくなります。
- ミスの発生
- 生産性の低下
- 教育コストの増加
企業向けマニュアルは、主に以下の4種類があります。
- 業務マニュアル
- 教育マニュアル
- 危機管理マニュアル
- 規定集/規程集
分かりやすく使いやすいマニュアルに仕上げるためには、5つの構成要素を意識して作成します。
- 目的
- 対象読者
- 手順、ルール、注意事項
- 用語解説
- 検索機能
マニュアル作成は、以下のステップで進めます。
- 企画・内容の検討
- スケジュールの決定
- 情報収集
- タイトル、見出し、構成の整理
- マニュアルの執筆
- 公開・配布
マニュアル作成・管理に役立つツールには、以下のようなものがあります。
- Officeテンプレート
- マニュアル作成ツール
- 社内Wikiツール、ナレッジマネジメントツール
マニュアルの運用を成功させるポイントは、以下の4点です。
- マニュアルの存在の周知徹底、利用促進
- 自社に適したマニュアル作成ツールの選定
- 定期的なアンケートによる利用状況の把握と改善
- マニュアル管理担当者の設置
最後に、マニュアル作成・活用に関する企業事例をご紹介しました。
- 株式会社イーソーコドットコム
- 株式会社東具
分かりやすいマニュアルを作成できれば、多くの従業員が活用し、パフォーマンス向上につながります。便利なマニュアル作成ツールの利用も検討しながら、業務や従業員の教育を効率化するマニュアル作成を目指しましょう。
人材育成の課題・解決方法を一冊にまとめました ⇒ LMS導入成功事例集を無料で読んでみる
- 株式会社PR TIMES「株式会社フィンテックス 【2024年度実施】業務マニュアルの使用状況とイメージの調査レポート」,『PR TIMES』,(閲覧日:2025年1月14日) ↩︎
- 株式会社PR TIMES「株式会社フィンテックス 【2024年度実施】業務マニュアルの使用状況とイメージの調査レポート」,『PR TIMES』,(閲覧日:2025年1月14日) ↩︎
参考)
株式会社イーソーコドットコム「入社5年目・藤田「新人営業マンを支えるマニュアル構築」」,『イーソーコドットコム』,https://e-sohko.net/journal/fujita_24/(閲覧日:2025年1月15日)
株式会社東具「災害対策マニュアルの作成」,『TOGU』,https://www.togu.co.jp/company/sustainability/report/detail/38(閲覧日:2025年1月15日)