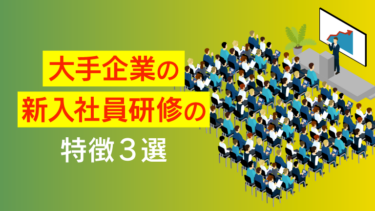「新入社員を早く戦力化したいが、現場や教育担当の負担は増やしたくない」
建設業や製造業は現在、新人教育において大きな課題を抱えています。現場は人手不足で、早急な人員の補充が望まれている反面、未経験の新入社員を配属されると教育に手が取られてしまい、かえって業務が逼迫(ひっぱく)するというジレンマに陥ってしまうのです。
この問題を解決するには、これまで現場が担ってきた実践的な教育の一部を新入社員研修で実施し、より早期に新入社員を一定レベルまで戦力化する必要があります。
株式会社アーキ・ジャパンが2020年に実施した調査によると、建設業の研修担当者が抱える悩みとして最も多かったのが「配属後に研修内容が活かしきれていない」(31.9%)でした1。今、建設業や製造業においては、いかに効果的・効率的に現場で必須とされる知識やスキルを習得できるかという視点で、新入社員研修を設計することが求められているのです。
この記事では、建設業と製造業それぞれにおいて、新入社員の早期戦力化を図るため、現場に入るまでに学ぶべき知識やスキルや、研修効果を高めるポイントを解説しています。さらに実際の建設業と製造業の企業の新入社員研修の例も紹介しているので、研修内容の見直しをお考えの企業の方は、ぜひ参考にしてください。
現場に出た新入社員が「もっと研修で学びたかった」スキルとは? ⇒ 新入社員研修アンケート調査結果を無料で見る
「新入社員のやる気を引き出したい。どのような研修が効果的だろうか?」入社3年以内の離職も珍しくない現在、新入社員研修は企業と新入社員との関係づくりの重要なスタートラインとして位置付けられます。いわゆるZ世代が興味を引かれるような、[…]
AIで要約
- 製造業や建設業の新入社員研修では、人手不足解消のため、早期に戦力となるための実践的な知識・スキル習得が重要です。
- カリキュラム内容例として、業界基礎知識、安全管理、コンプライアンス、コミュニケーションなどがあります。
- 研修効果を高めるには、研修の目的共有、自社事例や動画学習・マニュアルの活用、継続学習が大切です。
建設業・製造業の現状と課題から見る 新入社員研修の目的
現在、建設業と製造業はそれぞれに現場の課題を抱えています。新入社員研修を企画するにあたって、それらの課題解決を目的としてカリキュラムを組まなくてはなりません。まずは2つの業界の直面する課題と、研修の目的を理解しておきましょう。
他社はどう解決?製造業をはじめ、各業界の課題とその解決策がこの1冊に!⇒「LMS導入成功事例集」を無料でダウンロードする
【建設業】2024年問題と新入社員の早期戦力化
建設業界で新入社員研修について見直す大きな契機となったのが、2024年4月をもって、全ての職場に「働き方改革関連法」が導入されることになった、いわゆる「建設業の2024年問題」です。
働き方改革関連法では、原則として月45時間・年360時間という時間外労働の上限が設定されています。現在では企業規模の大小を問わず、建設業界でもこの時間内で必要な業務を終わらせなくてはならなくなりました。
そこで問題となるのが、新入社員の教育に充てる時間です。これまでは現場に入ってから実地で教わりつつ成長すればよいという考え方だったのが、今では現場の従業員にそのような時間的ゆとりがありません。
そこで新入社員研修で実践的な知識や安全管理の意識をしっかりと身に付けさせて早期戦力化を図り、教育する側の負担を少しでも軽減する必要に迫られています。
幅広い教材ラインナップで新入社員のオンボーディングをサポート! ⇒ ライトワークスの新入社員研修向けeラーニングを見てみる
【製造業】深刻な人手不足への対策
現場の人的リソースが不足しているのは、製造業も同様です。
キャディ株式会社が2023年に実施した調査によると、「人員不足に課題がある」と回答した製造業従事者は9割に上りました。人手不足の対応策として有効なDXについても、同調査によると「2024年度のDX投資予算が前年度より増加した」という回答は全体の3割未満にとどまっています2。
DXが遅れると、業務の手法やプロセスが旧来のままで現場の負担が軽減されず、モチベーション低下や離職を招きます。
さらに製造業における若年就業者数(34歳以下の就業者の数)は、2002~2023年の22年間で125万人減少しており3、若手への技術の継承や離職防止といった観点での従業員の意識向上も重要な目的です。
特に熟練の従業員から若手人材への技術継承においては、コミュニケーションの円滑化が鍵を握ります。
労働政策研究・研修機構が2018年に実施した調査では、「技術継承がうまくいっている」と回答した企業にその理由を尋ねたところ、「計画的にOJTを実施しているから」(59.5%)に次いで「指導者と指導を受ける側とのコミュニケーションがよく図られているから」(39.0%)が多い結果となりました4。
そのため製造業の新入社員研修では、工場勤務の基礎となる知識に加えて、コミュニケーションスキルを向上させるカリキュラムも効果的です。
建設業/製造業の新入社員研修カリキュラムの内容例
次に、建設業と製造業それぞれの具体的な新入社員研修のカリキュラムの内容例を見ていきましょう。
【建設業】新入社員研修で身に付けたい4つのスキル
建設業の新入社員研修では、施工管理の基礎知識に加えて、安全管理や法制度についても学ぶ必要があります。ここでは代表的な建設業の研修カリキュラムの内容例を紹介します。
スキル1:基本のビジネスマナー・施工管理の基礎的知識やスキル
まずは社会人として求められる基本のビジネスマナーを身に付けつつ、施工管理の知識やスキルを習得します。
建設現場における施工管理とは、工事が計画通りかつ安全・円滑に進むよう、全ての工程を管理する業務をいいます。品質管理、原価管理、工程管理、安全管理のそれぞれで必要な知識を身に付けなくてはなりません。
工事全体を見渡して進めていく施工管理の仕事は、所要時間や使用する材料を意識しつつ完成度の高い作品を製作するワークなどで疑似体験することもできます。
新入社員の即戦力化に役立つ! ⇒ ライトワークスの新入社員研修向けeラーニングを詳しく見る
スキル2:5Sと安全管理
建設業や製造業に共通する概念に、5Sがあります。5Sとは、整理・整頓・清掃・清潔・しつけの5つを徹底する考え方です。この場合の「しつけ」とは、他4つを習慣づけることを指します。
必要なものが常に決まった場所に置かれていて、何がどこにあるのか一目で分かるようにしておくと、現場作業の無駄を無くして、生産性が向上します。また、道具や機械を常に点検し、手入れが行き届いた状態にしておくことは、安全管理の観点でも重要です。
乱雑な現場では、そこで働く従業員の安全への意識も低下しがちで、事故が起きやすくなります。そのため、新入社員にも5Sに基づいた行動習慣を徹底して身に付けさせなくてなりません。
スキル3:法制度やコンプライアンス
近年、建設業においても徹底した法令順守の姿勢が重視されるようになりました。新入社員は個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)などの法律について学ぶとともに、建設業の業務において気を付けるべき点を理解しておかなくてはなりません。
2017年には日本建設業連合会が「建設業界の情報セキュリティ5大脅威」を公表しました。これによると、リスクレベルの第1位~5位は以下のような内容となっています5。
第1位:パソコン等の情報機器紛失・盗難
第2位:ブログ等SNSへの投稿による現場写真漏えい
第3位:図面等重要書類の紛失・盗難による情報漏えいと事故報告遅延
第4位:メール誤送信による図面データ等の漏えい
第5位:標的型攻撃メールによるコンピュータウイルス(ランサムウェア)感染
いずれも従業員にコンプライアンス教育が徹底されていれば、防げる事故といえるでしょう。
例えば、第5位の「標的型攻撃メールによるコンピュータウイルス(ランサムウェア)感染」は、不審なメールへの適切な対処を知っているかどうかが事故防止の鍵になります。社歴に関わらず、誰もがターゲットとなり得るので、新入社員研修でしっかりと知識を身に付ける必要があります。
スキル4:現場でのコミュニケーション
建設の現場では、社内外を問わず多くの人とコミュニケーションを取りながら協力して工事を進めていかなくてはなりません。
上司や先輩への報告・連絡・相談をする際にも、論理立てて端的に説明することで、相手に無駄な時間を取らせずに済みます。多忙を極める建設の現場で生産性を落とさないためには、相手の視点に立ったコミュニケーションが必要です。
また施工管理業務では、施主(工事の発注者)や現場の職人、役所・近隣住民など多様な年代・立場の人と信頼関係を築かなくてはなりません。研修では、全ての関係者が同じ目的の下に働くチームであることを意識し、前向きな態度でコミュニケーションを取ることも学びます。
現場に出た新入社員が「もっと研修で学びたかった」スキルとは? ⇒ 新入社員研修アンケート調査結果を無料で見る
【製造業】新入社員研修で身に付けたい5つのスキル
製造業の新入社員研修カリキュラムには、5Sなど建設業の研修と通じるテーマもあります。ここでは製造業の新入社員が学ぶべき代表的なスキルについて解説します。
スキル1:基本のビジネスマナー
製造業の新入社員研修においても、まずは社会人としての基本的なビジネスマナーについて学びます。
正しい名刺交換や電話応対、メールの送り方などを知っておくことで、業務で関わるあらゆる人から信頼を得られ、業務上のやり取りを円滑に進められるようになります。現場に出てから戸惑うことがないよう、動画学習やロールプレイングなどでしっかりとスキルを定着化させましょう。
新入社員の即戦力化に役立つ! ⇒ ライトワークスの新入社員研修向けeラーニングを詳しく見る
スキル2:工場についての基礎知識
製造業で新入社員を早期戦力化するには、工場でよく使われる専門用語や工場の業務フローについての知識を、業務に入る前に身に付けておいてもらうのがポイントです。
製造業で働いた経験が無い人には耳慣れない用語や略語が多いため、研修で各用語の意味を知っておかないと、先輩から仕事を教わる際にスムーズに理解ができません。
また生産管理と品質管理の仕組みや、国際基準のISOで定められた工程や手順を守らなければならないことなど、工場で働く上で必要な基礎知識を学ぶ必要があります。
スキル3:5Sと安全管理
整理・整頓・清掃・清潔・しつけの5Sと、安全管理は、工場での業務に入る前に知っておきたい基本的な知識です。
5Sの徹底は作業を効率化し、無駄な作業や危険な状況に対する新入社員の問題意識を高めるのに役立ちます。また工場の安全管理においては、自社のヒヤリハットの事例集などを紹介して、具体的にどのようなポイントに気を付けなくてはならないか共有しておくとよいでしょう。
大きな機械や設備を扱う工場では、たった一人の従業員の気の緩みが大事故にもつながりかねません。新入社員研修では5Sの習慣と安全管理の意識が何よりも大切であることを伝えましょう。
スキル4:品質管理のQCD
QCD(Quality・Cost・Delivery)は製造業では避けて通ることのできない概念です。
品質を追求しすぎるとコストがかかりすぎたり、納期に遅れが出たりといった問題が生じ、低コストや短納期にこだわると品質が低下します。製造業の新入社員は、QCDのどれか1つだけでも欠けると顧客満足度が低下することを知っておかなくてはなりません。
常に品質とコストと納期のバランスを考えて生産管理に臨む必要があると、ワークなどを通して研修で新入社員の意識付けを行うことが大切です。
スキル5:コミュニケーション
基本的な報連相や敬語、上司や先輩への質問の仕方など、新入社員にはコミュニケーションスキルの向上が求められます。
一定の知識やスキルは研修で学べますが、新入社員は現場の従業員から直接指導を受ける場面が必ず出てきます。指導する側の従業員の負担をできるだけ軽減し、スムーズに教育を行うには、新入社員がビジネスにおけるコミュニケーションのルールを知っていることが重要です。
また日頃から率先してあいさつを行うなど、周囲とコミュニケーションを円滑にしておくことの重要性についても学びます。
製造業の若手の早期戦力化に!⇒ LMSを活用して競争優位を確立する方法を詳しく見る
建設業/製造業の新入社員研修の効果を高めるポイント
建設業と製造業の新入社員研修では、新入社員の知識やスキルを強化し、早期戦力化を実現しなくてはなりません。ここでは研修効果を高めるためのポイントを解説します。
研修の目的を新入社員に共有しておく
研修効果を高めるためには、新入社員側の学習への意欲や、主体的に学ぶ姿勢が重要です。
新入社員にはあらかじめ研修の目的を共有し、「なぜこの知識やスキルが必要なのか」を理解した上で研修に臨んでもらうようにしましょう。業務に直結する内容であることが理解できれば、新入社員の学ぶ姿勢も真剣なものとなります。
また早期戦力化が求められている現状と併せて、研修でしっかりと学ぶことで、現場でいち早く活躍できるようになるというメリットを伝えると、新入社員のモチベーションも向上します。
事例は自社の業務がイメージできるものにする
研修の中で、具体的な労災事故やコンプライアンス違反などの事例を取り上げる際は、できるだけ自社の実際の業務に沿った事例を挙げましょう。
例えば、同じ製造業でも、電機メーカーの新入社員研修で自動車メーカーの事例を挙げては、現場でその知識を生かすイメージをしにくいでしょう。できる限り、実際の業務や職場環境がイメージできる事例から学ぶことが、新入社員の早期戦力化のポイントとなります。
研修資料の作成にあたっては、現場の従業員の意見も取り入れて、新入社員に身に付けてほしい実践的な知識の習得に役立つ事例を盛り込みましょう。
以下の記事は、リアリティにこだわった教材で、従業員の安全や防災への意識向上に成功した企業の事例です。ぜひ参考にしてください。
企業が、世界各国、さまざまなビジネス分野で事業を拡大していくなかで、労働災害発生リスクも増加しています。大手総…
動画学習やマニュアルを活用する
建設や製造の実践的内容について学ぶときは、動画学習を効果的に取り入れましょう。
未経験の新入社員にとって、施工や製造の現場に関する事柄はテキストだけではイメージしにくいかもしれません。現場で注意すべきポイントや、図面の読み方などは、動画だとより理解しやすくなります。
また、実践的知識をまとめたマニュアルを用意しておくと、研修修了後にも役立ちます。
研修で一通りを学んでも、実際に現場に入ると新たな疑問や悩みが出てくるものです。その都度、他の従業員が手を止めて教えていると全体の生産性が下がってしまうため、マニュアルによって、ある程度は新入社員が自力で疑問を解決できるようにしておくとよいでしょう。
動画コンテンツやマニュアルがあれば、時間が空いたときに何度でも見直すことができ、反復学習によって知識が定着化しやすいのもメリットです。
以下の記事は、社内のナレッジを整理して制作した300本の動画教材を活用し、新入社員の定着率向上と研修担当者の大幅な負担軽減に成功した企業の事例です。ぜひ参考にしてください。
店舗物件の転貸借に特化した不動産事業を展開する株式会社テンポイノベーションは、新入社員の早期戦力化・定着率向上…
フォローアップ研修などを実施する
新入社員研修が終了した後も、継続的な学びの機会を設けることが大切です。
新入社員研修からしばらく時間が経つと、研修を受けた当時は理解できていたことでも実践の機会がなければ忘れてしまったり、日常の業務に追われる中でモチベーションが低下してしまったりといった問題が生じます。
また、市場の変化やデジタル化による技術革新により、身に付けるべき最新知識やスキルは日々増えていきます。
そのため、新入社員研修の数カ月後にフォローアップ研修を実施したり、新入社員が自身で必要な知識を習得できるeラーニングシステムを導入したりと、継続的な学びの機会を提供しましょう。
建設業/製造業の新入社員研修事例
次に、実際の建設業・製造業で導入されている新入社員研修の事例について見ていきましょう。
【建設業】東急建設株式会社
東急グループの総合建設会社である東急建設株式会社は、建築設計部門のグループワークを中心とした新入社員研修が特徴です。
チームで協力して構造模型を作ったり、与えられた課題に沿って建物を設計したりと、新入社員が座学で学んだ知識を実際に活用する機会が豊富に設けられています。
ポイントは、現実的な条件に基づき実際に建設されることを前提とした設計であることです。構造模型は限られた材料で、十分に耐久性のあるものを作ることが求められ、制約のある設計業務がイメージしやすくなります。
また構造設計や意匠設計など、それぞれの専門の知識を生かして仲間と協働することで、建設におけるチームワークの重要性も学べます。
経験豊富な先輩社員から、建設時に問題となる点なども指摘してもらうことができ、新入社員研修の段階で、現場で学ぶような知識やスキルの習得が可能です。
【建設業】千代田化工建設株式会社
プラント建設など総合エンジニアリングを手がける千代田化工建設株式会社では、国内外でいくつもの大規模プロジェクトが進行しています。そのため新入社員教育の一環として、それらのプロジェクトに配属され、現場を経験するOJTのカリキュラムが組まれています。
「安全やコスト、スケジュールを意識して進行させる」「各拠点のグループ会社の人々と信頼関係を築いてチームワークを発揮する」といった現地でのプロジェクトマネジメントのノウハウが同社の強みです。新入社員はこれらを研修で実地に体得することで、今後の業務で必須となるスキルが身に付きます。
特に海外研修においては、語学力やビジネスマナーだけではなく、現地の従業員と共に過ごし、現地の文化や風習を大切にすることを学びます。海外にも多くの拠点を持つ同社では、それもまた実務において重要なスキルです。
【製造業】太陽工業株式会社
膜(ドームやテントなど)の加工技術を生かしたさまざまな製品を製造・販売する太陽工業株式会社では、新入社員研修においても膜を使用した製作研修を毎年実施しています。
2024年度には、「災害時の避難所での使用を想定した膜製品の発案と設計、さらに数日間の工場研修で自身が考えた製品を実際に製造する」という研修が実施されました。
新入社員が膜材加工を実際に経験して、同社が強みとする膜材加工の繊細な技術を体感すること、そして工場という製造の最前線での経験は、配属後に業務に取り組む上での力となります。
さらに2024年度の製作研修では、新入社員は大阪本社にて自身で製作した製品のプレゼンテーションにも取り組みました。これにより新入社員は、メーカーの仕事の一連の流れを研修で経験することができます。
【製造業】セイコーエプソン株式会社
プリンターやプロジェクターを製造する電機メーカー、セイコーエプソン株式会社は、新入社員研修にものづくり実践研修を取り入れています。
実際にものづくりを経験することで、お客様の満足度追求のために何ができるかを考え、メーカーとしての心構えを身に付けるのが狙いです。また研修全体を通してグループで活動し、チームワークを築く方法も学んでいきます。
ものづくり実践研修をはじめとした集合型研修を終えた後には、新入社員研修は育成リーダーの指導の下でOJTに入ります。入社3~5年目の先輩社員が育成リーダーとなり、担当する新入社員個人に合わせた育成計画書を作成して、マンツーマンの指導を行います。新入社員の教育に真剣に取り組むことで、同時に指導役の若手社員も成長させるのが狙いです。
さらに、入社1年後に全体で再度フォローアップ研修を、入社3年後には人事部による面談を実施して、若手人材のエンゲージメント向上を図るなど、定着化への取り組みにも力を入れています。
以下のリンクから、建設業・製造業以外の事例もご確認いただけます。
「新入社員のやる気を引き出したい。どのような研修が効果的だろうか?」入社3年以内の離職も珍しくない現在、新入社員研修は企業と新入社員との関係づくりの重要なスタートラインとして位置付けられます。いわゆるZ世代が興味を引かれるような、[…]
現場に出た新入社員が「もっと研修で学びたかった」スキルとは? ⇒ 新入社員研修アンケート調査結果を無料で見る
まとめ
建設業・製造業の現場ではそれぞれ以下のような課題を抱えています。
- 【建設業】2024年問題と新入社員の早期戦力化
- 【製造業】深刻な人手不足への対策
新入社員研修では、早期育成によって人手不足を解消するため、実践的な知識を学ばせたり、技術継承に必要なコミュニケーションスキルを身に付けさせたりすることが求められています。
建設業の新入社員研修で学ぶべき内容は、主に以下の4つです。
- 基本のビジネスマナー・施工管理の基礎的知識やスキル
- 5Sと安全管理
- 法制度やコンプライアンス
- 現場でのコミュニケーション
また、製造業の新入社員研修で学ぶべき内容は、主に以下の5つです。
- 基本のビジネスマナー
- 工場についての基礎知識
- 5Sと安全管理
- 品質管理のQCD
- コミュニケーション
建設業や製造業の新入社員研修の効果を高めるポイントは、以下の4つです。
- 研修の目的を新入社員に共有しておく
- 事例は自社の業務がイメージできるものにする
- 動画学習やマニュアルを活用する
- フォローアップ研修などを実施する
今回は、建設業と製造業の新入社員研修の具体的な事例として、以下の4つの企業の研修を紹介しました。
- 東急建設株式会社
- 千代田化工建設株式会社
- 太陽工業株式会社
- セイコーエプソン株式会社
建設・製造業界では、業界全体が直面する人手不足を乗り越えるため、新入社員研修に、より重要な役割が求められるようになりました。
その1つが、早期に活躍するための実践的なスキルを習得させることです。これにより、現場従業員の教育負担を最小限に抑えて生産性の維持・向上が可能になります。
人材の確保に課題を感じておられる建設業や製造業の企業の方は、新入社員研修の改善を図ってみてはいかがでしょうか。
- 株式会社アーキ・ジャパン「【建設業界の研修担当者1,048人に回答!】研修内容が活かしきれてない!?研修担当者が抱える悩みや課題が判明!外せない研修や企業のユニークな取り組みとは」, (閲覧日:2025年1月7日) ↩︎
- キャディ株式会社「製造業の9割が『人員不足に課題あり』、 DX推進の課題1位は『予算の制約』も、2024年度の『DX投資の予算増加』は3割未満 -キャディ製造業DX実態調査- 熟練者の不足や高齢者の退職に伴うリスク対策後手に」, (閲覧日:2025年1月5日 ) ↩︎
- 経済産業省, 厚生労働省, 文部科学省「令和5年度 ものづくり基盤技術の振興施策」, 2024年5月31日公表, P41, (閲覧日:2025年1月11日) ↩︎
- 独立行政法人 労働政策研究・研修機構「ものづくり産業における技能継承の現状と課題に関する調査」, P1,105, (閲覧日:2025年2月8日) ↩︎
- 一般社団法人日本建設業連合会「建設業界の情報セキュリティ5大脅威<2017年>」, (閲覧日:2025年1月7日) ↩︎
参考)
東急建設株式会社「新入社員研修」, https://www.tokyu-cnst.co.jp/architecture-design/workstyle/training/(閲覧日:2025年1月7日)
太陽工業株式会社「『膜』を創業の原点とした太陽工業ならではの新入社員研修を実施」, https://www.taiyokogyo.co.jp/news/63903/(閲覧日:2025年1月7日)
千代田化工建設株式会社「海外/国内現場研修レポート」, https://www.chiyodacorp.com/jp/recruit/graduate/career/report.html(閲覧日:2025年1月7日)
セイコーエプソン株式会社「人材育成」, https://corporate.epson/ja/sustainability/our-people/development.html(閲覧日:2025年1月7日)