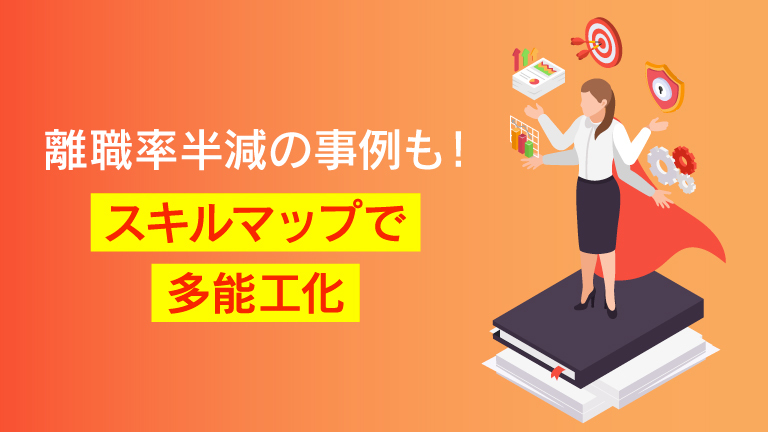「あの作業はベテランのAさんしかできないが、そろそろ若手にも任せたい」
「誰かが休んでも業務が回るよう、多能工化を進めたいが、何から始めればよいのだろう?」
製造業やサービス業、建設業など多くの現場では慢性的な人手不足が続いており、このようなお悩みは少なくありません。
それを解消するため、一人の従業員が複数の業務を担う「多能工化(マルチスキル化)」を検討する企業が増えています。熟練者の退職による技術の断絶、業務の属人化を避けるためにも、業務の標準化・見える化は不可欠といえます。
多能工化を進める上で、取り組みの中核を担うツールが「スキルマップ」です。スキルマップを活用すれば、各従業員のスキルを客観的に可視化でき、誰がどの業務に対応できるのかの把握と計画的な育成につながります。
この記事では、多能工化におけるスキルマップの基本的な役割から、作成・活用の実践ステップや注意点、さらには成功企業の事例までを網羅的に解説します。
多能工化を推進する上でスキルマップをどう作成・活用すべきか、お悩みの人事・研修担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
「スキル管理、何から始めれば…?」を解決! ⇒ 「スキルマップの基礎ブック」を無料でダウンロード
「スキルマップをうまく使えば、従業員が自ら学んで成長できるらしい」今、従業員のスキルや能力を組織力の向上につなげたいと考える多くの企業が「スキルマップ」に注目しています。企業は自律的に行動する従業員を求め、従業員は自分に合[…]
AIで要約
- 多能工化においてスキルマップを活用すると、各業務に必要なスキルやレベルが明確化され、育成計画の精度や組織全体の対応力を高めることが可能です。
- スキルの習得を昇格や報酬に反映させる人事評価制度を設けることで、従業員の学習意欲を効果的に引き出すことができます。
- 作成したスキルマップが形骸化するのを防ぐため、業務内容の変化に合わせて定期的に見直し、常に最新の状態を保つことが重要です。
多能工化(マルチスキル化)とは?定義と注目される背景
多能工化とは、従業員が複数の業務や職種を横断的に担当できるようにする取り組みです。一人一人が多様なスキルを身に付け、柔軟に現場の業務をカバーできる状態を目指します。
多能工化の考え方は、トヨタ自動車株式会社が確立した「トヨタ生産方式」1に由来するともいわれています。トヨタ生産方式は、「自働化」と「ジャスト・イン・タイム(必要なものを、必要なときに、必要な量だけ生産する)」を二本柱として、徹底的に無駄を排除し、利益を最大化することを目指します。
この思想が生まれたきっかけは、豊田紡織株式会社(現:トヨタ紡織株式会社)では作業者1人が複数台の機械を操作していたのに対し、トヨタ自動車工業株式会社(現:トヨタ自動車株式会社)では作業者1人が1台の機械しか操作していなかったことです。この状況が問題視され、作業者1人が複数台の機械を受け持てるように改善が進められました。
こうした多能工化の考え方が、長らく製造業の現場改善手法として定着してきました。さらに近年では建設業や外食産業、ホテル業など幅広い業種で取り入れられています。
その背景には、人手不足の深刻化や、熟練者の退職に伴う技術継承、繁閑差のある現場での人材配置といった経営課題があります。目まぐるしく変化する市場のニーズに対応し、常に最適化された業務フローと人材配置を実現するためにも、多能工化が不可欠となりつつあるのです。
実際に、中小企業庁の「中小企業白書(2018年版)」2でも、多能工化・兼任化に取り組むことで「全体の業務平準化による、従業員の負担の軽減」「繁忙期・繁忙部署における業務処理能力向上」といった効果が報告されています。
人手不足が深刻化する現代において、柔軟で生産性の高い組織を実現する多能工化は今後ますます重要視されていくでしょう。
多能工化の目的とメリット
まずは多能工化の目的とメリットについて、より詳しく解説していきます。
目的・メリット1:業務量の平準化
多能工化のメリットの1つは業務量の平準化です。従業員が複数の業務をこなせるようになるため、特定の部署や従業員に業務負荷が偏る状況を防ぐことができます。
さらに、一部の従業員に業務負荷が集中していた体制からの脱却は、従業員の過重労働防止やメンタルヘルス改善にもつながります。結果として、組織全体の生産性と従業員満足度の向上が期待できます。
目的・メリット2:業務の可視化とリスク管理
現場の業務のブラックボックス化を防ぎ、現場状況が変化した場合のリスク管理がしやすくなる点も多能工化のメリットです。
例えば、急な欠員が発生した際にも柔軟な人材配置が可能となり、業務の遅延や停滞を回避できます。また、繁忙期には人手が足りない部署へ別の部署の人材を応援に向かわせることも可能になるため、現場の安定運営が可能になります。
目的・メリット3:生産性の向上
多能工化は、現場のリソースを最大限に活用し、組織全体の生産性を高めるための有効な手段です。従業員が複数の業務に対応できるようになれば、勤務中の空き時間や待ち時間を減らすことができ、生産性が向上します。
また、特定の業務に負担が集中した場合でも、他のメンバーがスムーズにフォローに入れるため、ボトルネックの発生を防ぎ工程全体の流れが最適化されます。これは、生産ラインに限らず、バックオフィスやサービス業の現場でも同様です。
多能工化で一人一人のスキルの幅が広がることで、業務の選択肢が増え、組織全体の柔軟性と機動力が向上します。効率的な人材配置と業務分担が可能になり、生産性の底上げにつながるのです。
目的・メリット4:チームワークの強化
多能工化を進める過程では、従業員が自部署以外の業務や工程にも関与する機会が増えます。こうした相互支援の体制が広がることで、職場内でのコミュニケーションが活性化され、自然と連携の質も高まります。
異なる業務を経験する中で、従業員同士が業務内容や課題を理解し合うようになり、相互理解と信頼関係が深まります。役職や部署の垣根を越えた協力体制が構築され、強固なチームワークが生まれるのです。
また、チーム全体で業務をカバーする意識が醸成されることで、従業員の帰属意識やエンゲージメント向上にもつながります。多能工化は単なるスキルの拡張ではなく、組織文化の醸成にも寄与する重要な取り組みといえるでしょう。
目的・メリット5:変化に強い組織づくり
市場環境の変化が激しさを増す中、持続的に成長するには変化に強い組織であることが重要です。多能工化は、そうした組織づくりに必要な対応力とレジリエンス(困難な状況から立ち直る力や柔軟性)強化の鍵となります。
一人の従業員が複数の業務を担えるようになると、外部環境や顧客ニーズの変化にも柔軟に対応できます。たとえ急に業務変更や新たなプロジェクトが発生しても、社内のリソースで迅速な対応が可能です。
また、多能工化の推進は従業員の視野を広げ、主体的な提案やアイデア創出にもつながります。固定的な役割にとらわれず、相互補完するフラットで機動力の高い組織へと進化させるためにも、多能工化は欠かせない取り組みといえるでしょう。
スキル定義から定着までプロが伴走!貴社に最適なスキルマップを作りませんか? ⇒ スキルマップ構築支援サービスについて詳しく見る
スキルマップとは?多能工化で活用するメリット
スキルマップとは、従業員が保有するスキルや知識、それらの習熟度を一覧表として可視化するツールです。
多能工化を進める際には、「誰が」「どの業務を」「どのレベルで担当できるか」を明確に把握し、優先順位を考えながら人材育成を進めることが求められます。
スキルマップを活用すれば、各業務に必要なスキルやレベルが明確化されるため、育成計画の精度や組織全体の対応力を高めることが可能です。
ここでは、スキルマップを多能工化において活用する4つのメリットについて解説していきます。
メリット1:業務遂行に必要な能力の明確化と可視化
多能工化を進めるには、まず各業務で求めるスキルや知識を明確にすることが不可欠です。
スキルマップを使えば、業務ごとに必要なスキルやレベルを一覧化し、現場で共有することができます。これにより、「どの業務に、どのスキルが必要か」「対応できるレベルに達しているのは誰か」といった情報を可視化でき、育成対象の設定や人材配置の判断が容易になります。
また、業務の全体像が整理されることで、業務の属人化解消にもつながります。
メリット2:効率的かつ効果的な人材育成
スキルマップを活用すれば、各従業員が習得すべきスキルと現状のギャップが一目で分かります。これにより、個々の習熟度に応じた育成計画が立てやすくなり、教育内容を最適化できます。
さらに、スキルマップとeラーニングシステムやLMS(Learning Management System:学習管理システム)を連携すれば、必要なスキルを効率良く身に付けられる環境の構築が可能です。
例えば、LMS上でスキルマップと受講履歴、評価結果をひも付けることで、誰がどの研修を受け、どのスキルが強化されたかを可視化できます。さらに、スキルマップとeラーニングなどの研修コンテンツをシステム上でひも付けるなどにより、個別最適な学習支援が可能な場合もあります。
進捗管理や効果測定も行いやすく、人材育成のPDCAサイクルが回しやすくなります。
スキルマップとLMSの連携をスムーズに! ⇒ ライトワークスのスキルマップ構築支援サービスを詳しく見る
メリット3:経営戦略と人材育成との連動
スキルマップは、現場の人材育成に役立つツールであると同時に、経営戦略と人材育成をつなぐ橋渡し役にもなります。将来的に必要とされる人材像や組織目標を明確にし、現在の従業員のスキル状況を照らし合わせれば、採用・配置・育成の方針もデータに基づいた策定が可能です。
また、LMSと連携すれば、スキルデータを一元管理でき、タレントマネジメントや後継者育成といった戦略的な人材配置にも活用できます。
メリット4:従業員のキャリアアップ・スキルアップとモチベーション向上
スキルマップを活用することで、従業員は自身のスキルレベルや成長の段階を客観的に把握できるようになります。「自分には何ができて、何が不足しているか」が明確になるため、目標設定がしやすくなり、キャリア形成の道筋も見えやすくなります。
また、スキル習得の進捗が可視化されることで、達成感や自己効力感を得やすくなり、モチベーションの維持・向上にもつながります。上司や教育担当者からのフィードバックも、明確な基準に基づいて行われるため、指導に納得感を得られます。
スキルマップは、組織だけでなく従業員一人一人の成長を後押しするツールでもあるのです。
多能工化のためのスキルマップの作成・活用:5つのステップ
スキルマップは、多能工化を推進する上で基盤となるツールです。しかし、単に導入するだけでは十分な効果は得られません。自社の目的に合った形で設計・運用し、人材育成に組み込むことで、初めて真価を発揮します。
ここでは、多能工化に向けてスキルマップを作成・活用するための実践的な5つのステップを紹介します。
ステップ1:目的・対象の明確化
スキルマップの作成において最初に取り組むべきは、「何のためにスキルマップを導入するのか」という目的を明確にすることです。例えば、「繁忙期のフォロー体制構築」など目的を具体化し、関係者間で共有することで、目的に沿った一貫性のあるスキルマップを作成できるようにします。
次に、対象とする従業員層や職種の範囲を定めます。全従業員を対象とするのか、特定の部署や階層(新入社員、若手、中堅など)に絞るのかによって、必要となるスキルの粒度や作成方針も変わってきます。
さらに、どのような能力をスキルとして扱うのかも定義しなくてはなりません。業務遂行に必要な専門スキルだけでなく、対人関係能力や思考力などのソフトスキルも含めると、より総合的な視点で多能工化を進めることができます。
ステップ2:関係者への調査と必要なスキルの洗い出し
多能工化に必要なスキルを明確にするには、現場の実態把握が不可欠です。業務の担当者や管理職に対してヒアリングやアンケートを行い、各業務に求められる知識・経験・行動などを収集します。
得られた情報を基に、業務ごとのスキル項目を具体化し、重複や抜け漏れがないよう整理します。この段階では、現場と人事部が連携し、実際の業務に即したスキル項目を共有することが成功の鍵となります。
ステップ3:スキルマップの作成:必要なスキルの可視化
調査によって洗い出したスキル情報を基に、スキルマップを作成します。まずは、業務ごとに必要なスキル項目を体系的に整理し、部署や職種間で評価のばらつきが出ないよう、基準を統一することが重要です。
各スキル項目には、習熟度に応じた評価基準を設定します。その際は、厚生労働省が公開している「職業能力評価基準」3などのテンプレートも活用できます。
職業能力評価基準とは、業種別、職種・職務別に業務遂行に必要な知識・スキル・行動例などを整理したもので、客観的かつ汎用的な基準として多くの企業で活用されています。このようなテンプレートを活用することで、評価の客観性と社内での納得感を高めるスキルマップを時短で作成できます。
以下は、職業能力評価基準の、外食産業における共通能力のうち「顧客ニーズへの配慮とホスピタリティ」を参考に作成したスキル項目と評価基準の例です。
・スキル項目の例
| スキル項目 | 職務遂行のための基準 |
| (1)ホスピタリティと顧客ニーズの理解 | ・お客さまは一人一人、要望や好みが異なることを理解した上で、それに応じたサービスの提供方法を意識している ・ホスピタリティを意識した接客ができるよう、自身の感情を適切にコントロールし、常に良好なコンディションを保っている ・他業種を含むサービスやホスピタリティに関心を持って情報収集を行い、接客改善に活用している |
| (2)ホスピタリティの実践 | ・接客の際は、あいさつなどの基本的な表現に加え、「お気を付けて」など、状況に応じた共感的な言葉を用いて応対している ・お客さまからの問い合わせに対しては常に肯定的な姿勢・態度で接し、万一要望に応えられない場合でも代替案を示すなど建設的な対応をしている ・自ら率先して良質なホスピタリティの伴ったサービスを実践し、部下や後輩のロールモデルとなる態度を示している |
(参考:厚生労働省「外食産業(職業能力評価基準)」(閲覧日:2025年8月22日))
・評価基準の例
| 〇 | 一人でできている (下位者に教えることができるレベルを含む) |
| △ | ほぼ一人でできている (一部、上位者・周囲の助けが必要なレベル) |
| ✕ | できていない (常に上位者・周囲の助けが必要なレベル) |
(参考:厚生労働省「職業能力評価シートについて」(閲覧日:2025年8月19日))
ステップ4:スキルマップを活用して人材育成計画を立案
スキルマップを整備できたら、次は人材育成計画の立案です。多能工化の目的に沿って、「誰に、何のスキルを、いつまでに、どのレベルまで習得させるか」を具体的に設定します。
具体的な教育方法としては以下のようなものがあります。
- eラーニング
- 集合研修、グループワーク
- OJT
- 外部セミナー など
習得させたいスキルやレベルによって最適な組み合わせを検討し、知識と実践の両面から段階的に定着させていきます。
また、スキルを習得する従業員と、育成を担う上司や教育担当者、双方の負担を軽減するためにも、無理のないスケジュールを組み、運用体制を整備することが不可欠です。
なお、このステップでLMSとスキルマップを連携させると、人材育成計画を効率的かつ安定的に進める上で大きな効果を発揮します。スキル管理機能を持つLMSであれば、各従業員の習得状況や学習履歴、評価結果を一元管理でき、システム上で効率良くスキルの可視化と教育の進捗管理ができます。
ステップ5:人材育成計画の評価と継続的な改善
スキルマップを用いた育成計画は立てて終わりではなく、定期的な評価と見直しによって効果を高めていくことが重要です。
業務内容や市場環境は常に変化しているため、スキルマップそのものを定期的にアップデートする必要があります。それを踏まえつつ育成計画の評価と改善のサイクルを繰り返すことで、自社の状況に応じた効果的な多能工化の推進につながります。
多能工化におけるスキルマップ活用のポイントと注意点
スキルマップは多能工化の推進に欠かせないツールですが、活用の仕方を誤ると形骸化や現場の混乱を招く恐れもあります。ここでは、運用に当たって押さえておくべき4つのポイントと注意点を解説します。
ポイント1:実態に合わせてスキルマップの情報を更新する
一度作成したスキルマップをそのまま使用し続けると、現場の実態と懸け離れ、形だけの管理ツールになってしまいます。そのうち更新が面倒になり、誰も見ない「形骸化したスキルマップ」となるのはよくある失敗です。
これを避けるには、業務内容や社内体制の変化に合わせてスキルマップも定期的に見直し、更新することが必要です。
半年や年に一度など、更新サイクルをスキルマップの運用制度の中に組み込み、常に最新の状態を保つことで、現場とのギャップを最小限に抑えられます。
ポイント2:人材育成計画は余裕を持って立案する
多能工化は短期間で成果が出るものではなく、一定の時間とコストを要します。習得させたいスキルの数やレベル、育成対象の人数に応じて、無理のない育成スケジュールを設定しましょう。
詰め込み過ぎると、育成対象者にも教育担当者にも大きな負担がかかり、学習効果やモチベーションの低下を招く恐れがあります。
ポイント3:LMSなどを活用して進捗を把握する
スキルの習得状況を正確に把握し、柔軟に人材育成計画を見直すには、LMSなどのシステムを活用すると効果的です。
Excelなどの手動管理では対応が難しくなりがちな複数スキル・多人数管理も、スキル管理機能を持つLMSなら一元的に管理できます。スキルマップと学習履歴を連携させることで、育成効果の可視化・分析が可能になり、次の施策にもつなげやすくなります。
注意点:適切な評価とモチベーション維持策の実施
せっかくスキルを習得しても、その努力が評価されなければ従業員のモチベーションは維持できません。スキルの習得・強化に応じた評価制度を設け、昇格・報酬などに反映させることが必要です。
また、企業側の都合だけで一方的に多能工化を進めると、従業員の負担増加や離職につながるリスクが高まります。
特に、従業員が「器用貧乏」に陥るリスクには注意が必要です。広く浅く業務をこなせるようになる一方で、専門性が磨かれないことへの不安は、将来のキャリア形成への懸念やモチベーション低下に直結しかねません。
そのため、多能工化によるスキルの「幅」だけでなく、特定の分野における専門性の「深さ」も評価する仕組みを設けたり、スペシャリストとしてのキャリアパスを併設したりするなど、従業員の適性やキャリア志向にも配慮しながら進めることが、従業員のエンゲージメントを高め、持続的な多能工化を可能にする鍵となります。
多能工化におけるスキルマップ活用の成功事例
最後に、実際に多能工化を進めるに当たってスキルマップを活用し、成功している2社の事例を紹介します。
株式会社IBUKI:赤字脱却を支えた教育体制とスキルの見える化
射出成型用金型の設計・製造を手がける株式会社IBUKIは、主要顧客の海外移転による受注減や、従業員の減少・高齢化という課題を抱えて赤字経営が続いていたため、「教育体制の強化」と「スキルの見える化による多能工化の推進」を図りました。
その中心となった取り組みの1つが、社内研修プログラム「育成塾」です。グループディスカッション形式のケーススタディーを組み込んだ研修で、幅広い年代の従業員が参加しています。特に、他社経験のある従業員が講師を務めるセッションは、社内に新しい視点を取り入れる契機となっています。
さらに、スキルマップと社内基幹システムによる「多能工選出システム」を活用し、必要な人材像の明確化と、それに沿った学習機会の提供をすることで多能工化を推進しています。
多能工化の成果が正当に評価されるよう人事評価制度の見直しも行われ、スキルの習得・発揮がキャリア形成に結び付く仕組みが確立されました。
従業員の学びへのモチベーションは大きく向上し、離職率も半減。業務効率も高まり、2022年3月期には売上高が2014年比の約2倍にまで増加し、事業の黒字化を達成しています。
武州工業株式会社:多能工化とIT人材育成で生産性20%向上を実現
自動車用金属部品の板金加工、プレス加工などを手がける武州工業株式会社は、技術継承の課題の解決と、高品質・ローコストを両立させた国内生産の実現のため、多能工化とデジタル化による生産性向上を目指しました。
同社は、1つ上の年次の先輩が新人に教えるといった形のOJTを軸とした教育体制を整備し、技術の属人化を防ぎ、多能工化を実現する仕組みを定着させました。
さらに、スキルマップを活用して誰がどのスキルを保有しているかを可視化し、多能工としての力量を客観的に評価できる体制を整えることで、適切な人材配置が可能になりました。
また、従業員が主体的に多能工を目指すよう、より多くのスキルを発揮すると査定が高くなる給与体系も整備し、多能工化への動機付けを促すシステムとして確立しています。
併せてIT人材の育成・確保にも取り組み、生産管理システムを自社で開発・運用して情報の共有化や作業の省力化を進めました。
これらの取り組みの結果、生産性は20%向上しました。開発した生産管理システムは、中小製造業向けに外販もされています。
「スキル管理、何から始めれば…?」を解決! ⇒「スキルマップの基礎ブック」を無料でダウンロード
まとめ
多能工化とは、一人の従業員が複数の業務を担えるようにする取り組みで、人手不足や業務の属人化を解消し、柔軟な組織づくりを可能にします。
多能工化の目的とメリットは以下の通りです。
- 業務量の平準化
- 業務の可視化とリスク管理
- 生産性の向上
- チームワークの強化
- 変化に強い組織づくり
多能工化を推進するためには、スキルマップの活用が効果的です。スキルマップは従業員が保有するスキルや知識を可視化するツールで、多能工化の基盤となって適切な人材育成・配置の実現に役立ちます。スキルマップを活用する具体的なメリットは以下の通りです。
- 業務遂行に必要な能力の明確化と可視化
- 効率的かつ効果的な人材育成
- 経営戦略と人材育成との連動
- 従業員のキャリアアップ・スキルアップとモチベーション向上
多能工化のためのスキルマップの作成・活用は、以下の5つのステップで進めていきます。
ステップ1:目的・対象の明確化
ステップ2:関係者への調査と必要なスキルの洗い出し
ステップ3:スキルマップの作成:必要なスキルの可視化
ステップ4:スキルマップを活用して人材育成計画を立案
ステップ5:人材育成計画の評価と継続的な改善
また、多能工化におけるスキルマップ活用のポイントと注意点は以下の通りです。
- 実態に合わせてスキルマップの情報を更新する
- 人材育成計画は余裕を持って立案する
- LMSなどを活用して進捗を把握する
- 適切な評価とモチベーション維持策の実施
この記事では多能工化におけるスキルマップ活用の成功事例として、以下の2社を紹介しています。
- 株式会社IBUKI
- 武州工業株式会社
スキルマップの活用は、多能工化を単なる「人手不足改善策の1つ」という位置付けから、人材戦略の中核へと昇華させる鍵となります。さらにスキルマップとLMSを組み合わせることで、より戦略的な人材育成が可能です。
組織の持続的成長につながる施策として、多能工化におけるスキルマップの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
- トヨタ自動車株式会社「トヨタ生産方式」,『TOYOTA』(閲覧日:2025年8月25日) ↩︎
- 中小企業庁「中小企業白書(2018年版)」,P175-176(閲覧日:2025年8月15日) ↩︎
- 厚生労働省「職業能力評価基準」(閲覧日:2025年8月15日) ↩︎
参考)
中小企業庁「中小企業・小規模事業者の人材活用事例集」,2023年6月公表,https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/hitodebusoku/guideline/jirei.pdf(閲覧日:2025年8月15日)