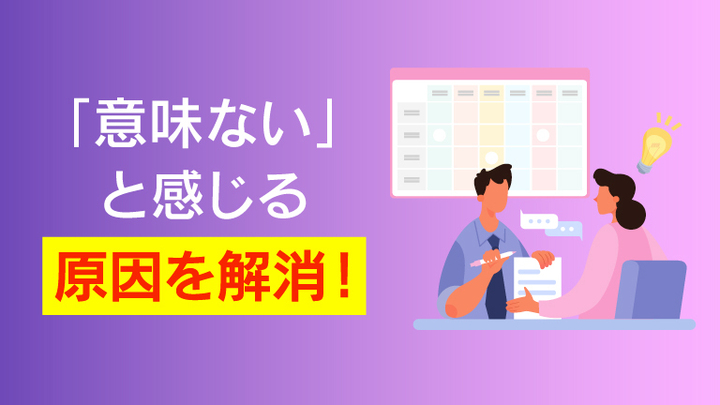「スキルマップを作ったが、活用できずにそのままになっている…」
スキルマップで従業員のスキルを可視化しても、効果がよく分からない、思ったよりスキルの入力に時間や労力がかかるといったことでお悩みではないでしょうか?
「スキルマップは本当に必要なのか」「意味がないのでは」と疑問を抱き、せっかく作ったスキルマップが更新されなくなってしまうケースは少なくありません。
しかし、「VUCA」と呼ばれる変化が激しい時代において、「誰が・何を・どれだけできるのか」を正確に把握することは、企業の持続的な成長に不可欠です。
スキルマップを活用して人材育成計画を遂行することが、将来的な人材不足や事業戦略策定・実行の遅れといった経営リスクの低減につながります。
この記事では、スキルマップが「意味ない」といわれる理由と対策、活用のメリット、成功事例などをご紹介します。ぜひ効果的なスキルマップ導入の参考にしてください。
「スキル管理、何から始めれば…?」を解決! ⇒ 「スキルマップの基礎ブック」を無料でダウンロード
「スキルマップをうまく使えば、従業員が自ら学んで成長できるらしい」今、従業員のスキルや能力を組織力の向上につなげたいと考える多くの企業が「スキルマップ」に注目しています。企業は自律的に行動する従業員を求め、従業員は自分に合[…]
AIで要約
- スキルマップのデメリットに対策することが、スキルマップを実際に「使えるツール」にするポイントです。
- スキルマップ作成の手間は、厚生労働省の「職業能力評価基準」やLMS(学習管理システム)の活用で大幅に削減できます。
- スキルマップを形骸化させず効果的に運用するポイントとして、昇格や配置転換などの人事制度と連動させることが挙げられます。
現代の人材育成に不可欠なスキルマップとは?
スキルマップとは、誰が、どのようなスキルをどのレベルで保有しているかを、定量的に把握できるよう一覧で示したものです。スキルマップは、「力量表」や「スキルマトリックス」とも呼ばれます。
未来予測が困難な不安定な時代だからこそ、企業は戦略的人材育成を行い、変化に強く柔軟に活躍できる人材を育成する必要があります。
個々のスキルとそのレベルが一目で分かるスキルマップは、強化すべきポイントを可視化し、効果的に人材育成を進める上でなくてはならないものなのです。
意味がないと感じる原因:スキルマップの5つのデメリットと対策
戦略的人材育成には欠かせないスキルマップですが、デメリットを大きく感じると作成・運用する意味がないと考えてしまうのは無理もありません。
ここでは、そのデメリットと、スキルマップを「使えるツール」にするための対策を解説します。
デメリット1:スキルマップの作成に手間と時間がかかる
スキルマップを作成するには、業務に必要なスキルの洗い出し・整理、評価基準の設定など、さまざまな作業をする必要があります。
スキルマップ完成までにかかる時間と労力が多大で、担当者の負担になりやすい点は、作成のハードルを高くしています。
【対策】
厚生労働省が公表している無料のテンプレートやLMS(Learning Management System:学習管理システム)を活用すれば、スキル項目や評価基準の設定にかかる時間と労力を、大幅に削減できます。以下で詳しく見ていきましょう。
対策1:厚生労働省「職業能力評価基準」
厚生労働省では、仕事をこなすための知識と技術・技能、さらに「成果につながる職務行動例」を、業種、職種・職務別に整理した「職業能力評価基準」1を定めています。
「職業能力評価基準」では、業種や職種ごとに期待される責任や役割の範囲、難易度によって1~4までの能力レベル区分が設定され、求められるスキルが示されています。その内容を参考にすることで、自社でどのように使用するかイメージができる上、スキル項目をゼロから作成する必要がなくなり、導入までにかかる時間・労力を抑えられます。
また、「職業能力評価基準」を基に能力開発の標準的な道筋を示した「キャリアマップ」2や、「職業能力評価基準」で定められている基準を簡略化した、チェック形式の評価表「職業能力評価シート」3もスキルマップ作成の参考となります。
厚生労働省「職業能力評価基準」(閲覧日:2025年9月9日)
対策2:LMS(学習管理システム)
LMS(学習管理システム)は、eラーニングやオンライン研修を実施する際に、プラットフォームとなるシステムです。
スキルマップの作成・管理機能を備えたLMSを選べば、スキルの入力、学習状況や成績の把握、評価形式の設定・変更などを全てシステム上で行えるので便利です。スキルマップ導入から運用までのプロセスを効率化し、担当者の負担を大幅に軽減できます。
なお、ライトワークスではLMS「CAREERSHIP」のスキル管理機能を導入いただいた全てのお客さまに、職種別・レベル別に必要なスキル項目を設定できるスキルテンプレートを無償で提供しています。
さらに、スキル項目とeラーニング教材とのひも付け、効果測定、改善提案など、スキルマップを形骸化させず効果的に活用していくための運用サポートも行っています。
職種別900件以上のスキル項目! ⇒ ライトワークスの「スキルテンプレート」を無料でダウンロードする
デメリット2:スキル管理のノウハウ・⼈⼿が必要
スキル管理は、そのノウハウを持つ管理者や上長が、時間や労力をかけて関与していくことが不可欠です。そのためスキルマップを基に戦略人事や人材開発を推進できる人材の確保が求められます。
しかし、スキル管理の運用方法は多くの企業で標準化されておらず、ノウハウが蓄積されていないことも少なくありません。
そのため、スキルマップを作成しても活用されずに形骸化してしまう、期待した人材育成の効果が表れないといった状況に陥り、「意味がない」と感じてしまうケースも多く見られます。
【対策】
最も重要なのは、戦略人事・人材開発の推進に必要な人材の育成・確保です。具体的には、人事担当者に研修を実施したり、現場の業務に精通した人材を登用したりするといった方法があります。
一定のスキルを持った人材が、現場の実態を反映した「実用的な」スキルマップを作ることが大切です。
スキル管理のノウハウが不足している場合は、スキル管理の運用・発展をサポートするコンサルティングサービスを活用してもよいでしょう。
スキルマップの作成から運用まで伴走支援! ⇒ ライトワークスのスキルマップ構築支援サービスを詳しく見る
デメリット3:従業員の不満につながる面がある
従業員のスキルを可視化すると、その時点のそれぞれのスキルの有無や習熟度の差が明確になります。目標をクリアしていない従業員は劣等感を抱きやすく、モチベーション低下を招く恐れもあります。
また、スキルの評価基準が曖昧な場合、評価者によって評価にばらつきが出てしまい、不満や不信感につながります。
【対策】
従業員の不満や不安を解消できる仕組みを作りましょう。例えば、目標レベルに届かなかった従業員には、面談などを通じて目標達成やスキルアップにつながる具体的な道筋をアドバイスするなどして、スキル向上に向けたアクションを促しましょう。
また、スキルマップの評価基準は公平で明確な内容を設定します。導入の目的や評価方法と併せて全従業員に共有し、評価に納得できるよう認識の擦り合わせを行うことが大切です。
2-4. デメリット4:スキルアップ・業務遂行自体が目的化する
スキルマップは、効率的なスキルアップに役立ちます。しかし、特定のスキルの習得や業務遂行にばかり意識が集中すると、それ自体が目的化してしまう場合があります。
「何のためにスキルアップ・業務遂行をするのか」という、本来の目的を見失ってしまう可能性があるため、注意が必要です。
【対策】
スキルマップのそもそもの導入目的を定期的に確認すると、本来の目的を見失わず効果的に活用できます。
本来の目的とは、例えば、社会への価値提供や、従業員の成長支援、新入社員などの早期戦力化といった、組織全体、ひいては社会への貢献です。「なぜスキルアップが求められているか」、「何のために必要な業務なのか」という背景を、従業員に分かりやすく伝えましょう。
個人に必要なスキルと併せて、組織全体の成長のために必要なスキルも習得を促すと、目的のすり替わりを防げます。
デメリット5:適正な人事評価を行えない場合がある
評価者がスキルマップを重視し過ぎると、適正な人事評価を行えなくなる可能性があります。
スキルの習得状況以外の評価要素、例えば仕事に対する姿勢や態度、周囲からの信頼度などは、スキルマップ上では把握できないからです。
【対策】
スキルマップは、あくまでも「評価ツールの1つ」という認識を持ちましょう。可視化されたスキルは人事評価の重要な要素ですが、それだけで判断してしまうとスキル偏重の人事評価につながります。
人事評価の際にはスキルマップからは見えない要素にも注目し、総合的に判断するよう心がけることが大切です。
スキルマップが解決する課題と得られるメリット7つ
スキルマップにはさまざまなデメリットがありますが、一方で、スキルマップによって解決できる課題や得られるメリットも多くあります。
ここでは、導入・運用を前向きに検討できるメリットをご紹介します。
メリット1:スキルの可視化と不足スキルの明確化
スキルマップを活用してスキルを可視化すれば、従業員それぞれのスキルセットを定量的に把握できます。自社に不足しているスキルや、強化すべきスキルを明確に特定できることは、スキルマップの大きなメリットです。
メリット2:効率的な人材育成と採用
スキルマップは、効率的な人材育成と採用にも役立ちます。従業員一人一人、そして部署ごとの保有スキルや不足スキルが明確になると、スキル面の弱点を克服するための教育や研修の具体的な計画を立てやすくなります。
新卒や中途採用時にも、社内で不足しているスキルを保有する人材確保に注力でき、ミスマッチ防止にも貢献します。
メリット3:時代の変化への対応
日本では15~64歳の現役世代の人口減少が進んでおり4、企業の人手不足はますます深刻化しています。また、昨今はデジタル化の加速や年功序列制度の衰退、ジョブ型雇用への移行など、ビジネス環境の変化も加速しています。
このような社会や経済の変化に対応するために、より戦略的な人材開発が求められます。スキルマップは企業の現状と将来的な目標を鑑み、計画的な人材育成を実現するためのツールとして有効です。
メリット4:適切な人材配置と生産性向上
スキルマップで一人一人が保有するスキルを可視化すると、得意・不得意分野が明らかになり、高いレベルのスキルや得意分野を生かせる部署・職種への配置が容易になります。
本人の適性を生かした人材配置はミスマッチを防ぐだけでなく、生産性や業務効率の向上にもつながります。
さらに、スキルを発揮できる場での就労は従業員の満足度も向上させるので、離職率低下も期待できるでしょう。
メリット5:新規事業立ち上げへの貢献
新規事業の立ち上げ時には、必要なスキルを保有するメンバーの選出が不可欠です。スキルマップがあれば、各従業員のスキル情報を基に求めるスキルを持つ人材を迅速にピックアップできます。
また、保有スキルに応じた仕事の割り振りも円滑に行えるので、スムーズに新規事業のスタートを切ることができます。
メリット6:人事評価の公平性確保
スキルマップを共通の評価基準として人事評価に活用することで、公平性・正確性を保った客観的な評価を可能とし、評価者独自の基準や個人的な感情による影響を軽減できます。
評価基準を全従業員に共有すれば、人事評価に対する納得感も高めらます。
メリット7:自発的な学びの促進とモチベーション向上
スキルの可視化は、従業員が自身の強み・弱みを客観的に把握する材料にもなります。自身の現状を理解することで、不足しているスキル習得へのモチベーションが向上し、自発的な学びを促進します。
また、従業員にスキルマップと評価基準を共有すれば「正当な評価を受けている」と分かるので、業務に取り組む姿勢にも良い影響を与えます。
なお、ライトワークスがLMS「CAREERSHIP」上で提供するスキルマップでは、各スキルレベルに必要な教材や研修をひも付けることが可能です。
従業員自身が「このスキルを習得するには、この学習が有効である」と認識できるため、自律的な学びを強力に後押しします。「CAREERSHIP」を活用すれば、スキルマップ作成だけでなく、その後のスキルアップまで一貫してフォローが可能です。
スキルと学習の連動で自律的な学びを後押し! ⇒ CAREERSHIPのスキル管理機能を詳しく見る
スキルマップを作成する6ステップ
スキルマップをスムーズに作成するには、どのような流れで進めるとよいのでしょうか。作成ステップを解説します。
ステップ1:目的を明確にする
まずは、「なぜスキルマップが必要なのか」という目的をはっきりさせましょう。
例えば、若手社員のスキルアップ、管理職のマネジメント能力の見直し、業務品質の向上など、具体的な目的を定めると運用がスムーズです。目的を関係者間で共有し、スキルマップの設計に一貫性を持たせましょう。
ステップ2:対象の階層・業務と必要なスキルを洗い出す
目的が定まったら、対象となる階層(全従業員、新入社員、管理職など)や部署、業務などを決定します。
対象範囲が広い場合は、まず特定の部署やチームに限って導入する「スモールスタート」で始め、運用に慣れてから徐々に横展開していく方法が有効です。
ターゲットを絞ったら、その階層や部署・業務などに必要とされるスキルを全てリストアップします。
ステップ3:スキルを整理・体系化する
洗い出したスキルは、関連性の高さでグループに分けて整理します。例えば「スキル」と「知識」に大きく分けて体系化すると、スキルアップに必要な教育支援を具体化しやすくなります。
整理されたスキル項目と、その習得に必要な教育(OJT、Off-JT、eラーニングなど)とのひも付けも併せて行いましょう。
ステップ4:評価基準を設ける
各スキルの習熟度を測るための客観的な評価基準を定めます。例えば、以下のように具体的で明確な段階別の基準を設定すれば、誰が評価しても同じ結果が得られます。
【評価基準の例】
レベル1:指示があればできる
レベル2:一人で遂行できる
レベル3:他者に指導できる
ステップ5:スキルマップの様式を決定し、作成する
整理したスキル項目と評価基準を基に、スキルマップのフォーマットを決定・作成します。スキルマップの様式は、縦軸に「スキル項目」、横軸に「氏名」「評価レベル」を置いた「マトリクス形式」の表が一般的です。
氏名とともに顔写真を入れると、よりパーソナルで身近なツールとして認識できます。どの従業員に関する情報かも一目で分かり、スキルマップのスムーズな活用につながります。
ステップ6:評価と更新
作成したスキルマップで、従業員一人一人のスキル・レベルを実際に評価します。評価結果は人材育成計画の立案や、人事評価、個々のフィードバックなどに役立ちます。
また、スキルマップは一度作成したものを長期間運用するのではなく、ビジネス環境の変化や企業の成長に合わせ、アップデートすることが重要です。スキル項目や評価基準を定期的に見直し、適宜内容を更新しましょう。
スキル定義から定着までプロが伴走!貴社に最適なスキルマップを作りませんか? ⇒ スキルマップ構築支援サービスについて詳しく見る
スキルマップを効果的に運用する4つのポイント
スキルマップを形骸化させず、効果的なツールとして運用する主なポイントを4つご紹介します。
ポイント1:運用の目的と人事制度との連動
スキルマップによって何を実現したいのかが不明確だと、運用する意味を感じなくなり、形骸化してしまう場合があります。「何のためにスキル管理を行うのか」という目的を明確化し、人事制度と連動させることで、スキルマップが組織の仕組みに組み込まれ、運用促進に寄与します。
人事制度と連動させる具体的な方法としては、昇格・昇進や昇給、配置転換等の人事施策にスキルマップの評価結果を反映させることが挙げられます。
ポイント2:評価者の教育
人事担当者や管理職などの評価者が、スキルマップの導入意図や評価基準を理解していないと適切な評価ができません。
評価者全員がスキルマップ導入の背景や評価基準について共通の認識を持ち、評価者による解釈の違いや評価のばらつきを最小限に抑えて公平性を担保することが重要です。
そのためには、適正な評価をするための知識を習得できる評価者向けの教育を実施する必要があります。具体的には、客観的な評価方法や従業員との面談の進め方、フィードバック方法などを学ぶ評価者研修などを行うとよいでしょう。
ポイント3:定期的な見直しと改善
一度作成したスキルマップを長期間使用していると、ビジネス環境の変化や現場の実態に合った運用ができなくなり形骸化しやすくなってしまいます。スキル項目や評価基準は定期的に見直し、ビジネス環境や自社の事業、従業員の状況の変化に応じて改善しましょう。
スキル項目を細分化または統合する場合や、利用目的の変更(例:育成用⇒人員配置用)が生じた場合など、フォーマット自体の変更が必要になるケースもあります。
ポイント4:スキルテンプレートやLMSで負担軽減
スキルマップ作成の初期段階では、スキルの洗い出しなどに時間や労力がかかります。その負担を軽減するには、テンプレートの利用が有効です。
厚生労働省の「職業能力評価基準」5などの無料テンプレートなら、費用面の心配もなく気軽に試すことができます。
また、スキルマップ作成機能があるLMSを活用すれば、スキルマップ作成から運用、評価、学習への連携まで1つのシステムで実施でき便利です。受講者・管理者ともに使いやすくなり、作成・運用を効率化して大幅に負担を軽減できるので、スキルマップの長期的な活用を後押しします。
ライトワークスのLMS「CAREERSHIP」なら、スキル情報だけでなく、研修の受講履歴、キャリア志向、日々の学習データなどを一元的に管理できます。
これにより、経営戦略に基づいた最適な人材配置、次世代リーダー候補の計画的な育成(サクセッションプラン)、将来の事業に必要なスキル保有者の特定なども可能です。
発展的なスキル管理も可能に! ⇒ ライトワークスのスキルマップ構築支援サービスを詳しく見る
スキルマップ活用の成功事例:アサヒグループジャパン株式会社
最後に、スキルマップの活用に成功した企業事例をご紹介します。
アサヒビールやアサヒ飲料など、アサヒグループの国内主要事業を統括するアサヒグループジャパン株式会社は、約3200人の従業員(取材当時)に対し、LMSの月間アクセス数が平均500PVと少なく、LMSを発展的に使うことができていないという課題がありました。
そこで、この状況を打開するため、ライトワークスのLMS「CAREERSHIP」をベースにしたポータルサイト「Career Palette」を導入しました。
導入後、同社の20数種類の職種に対し、それぞれ3つのステージをかけ合わせたスキルマップ「ジョブディビジョンスキル表」を作成し、職種とステージによって必要なスキルを体系化しました。
「ジョブディビジョンスキル表」とeラーニング教材をひも付け、今習得すべきスキルの情報と、それを伸ばすための具体的な教材・メニューを届けることで、個々に最適化された学習体験の提供を可能としました。
このような施策により、LMSのアクセス数は月平均6000PVほどと、「Career Palette」導入前の12倍に増加しました。同社はLMSとスキルマップ活用による、高い効果を実感しています。
2018年にeラーニングシステムを一新すると、月平均PVは12倍に拡大。なぜ、そのような利用率の拡大が実現できたのでしょ…
「スキル管理、何から始めれば…?」を解決! ⇒「スキルマップの基礎ブック」を無料でダウンロード
まとめ
スキルマップとは、従業員の持つスキルやそのレベルを定量的に把握するための一覧表です。
「スキルマップは意味がない」と感じる原因となるデメリットと、その解決策は以下の通りです。
- スキルマップの作成に手間と時間がかかる
⇒テンプレートやLMSの活用
- スキル管理のノウハウ・⼈⼿が必要
⇒戦略人事・人材開発の推進に必要な人材の育成・確保
- 従業員の不満につながる面がある
⇒スキル向上を促す仕組みづくりや公平で明確な評価基準の設定
- スキルアップ・業務遂行自体が目的化する
⇒スキルマップの導入目的を定期的に確認にする
- 適正な人事評価を行えない場合がある
⇒人事評価では「評価ツールの1つ」という認識を持つ
スキルマップの活用で、以下のようなメリットが期待できます。
- スキルの可視化と不足スキルの明確化
- 効率的な人材育成と採用
- 時代の変化への対応
- 適切な人材配置と生産性向上
- 新規事業立ち上げへの貢献
- 人事評価の公平性確保
- 自発的な学びの促進とモチベーション向上
スキルマップ作成のステップは、以下の通りです。
- 目的を明確にする
- 対象の階層・業務などと必要なスキルを洗い出す
- スキルを整理・体系化する
- 評価基準を設ける
- スキルマップの様式を決定し、作成する
- 評価と更新
スキルマップを効果的に運用するポイントは、4点あります。
- 運用の目的と人事制度との連動
- 評価者の教育
- 定期的な見直しと改善
- スキルテンプレートやLMSで負担軽減
最後に、スキルマップ活用の成功事例として、アサヒグループジャパン株式会社について紹介しました。
スキルマップの作成や運用には、確かにデメリットや注意すべき点が存在します。しかし、多くの課題はテンプレートやLMSで作業を効率化したり、運用のポイントを押さえたりすることで乗り越えられます。
変化の激しい現代において、戦略的な人材育成は企業の持続的な成長に不可欠です。この記事を、価値あるスキルマップの作成・運用の参考としていただければ幸いです。
- 厚生労働省「職業能力評価基準」,(閲覧日:2025年8月28日) ↩︎
- 厚生労働省「キャリアマップについて」,(閲覧日:2025年8月28日) ↩︎
- 厚生労働省「職業能力評価シートについて」,(閲覧日:2025年8月28日) ↩︎
- 厚生労働省「新しい時代の働き方に関する研究会 報告書 参考資料」,2023年11月13日公表,P2,(閲覧日:2025年8月29日) ↩︎
- 厚生労働省「職業能力評価基準」,(閲覧日:2025年8月30日) ↩︎