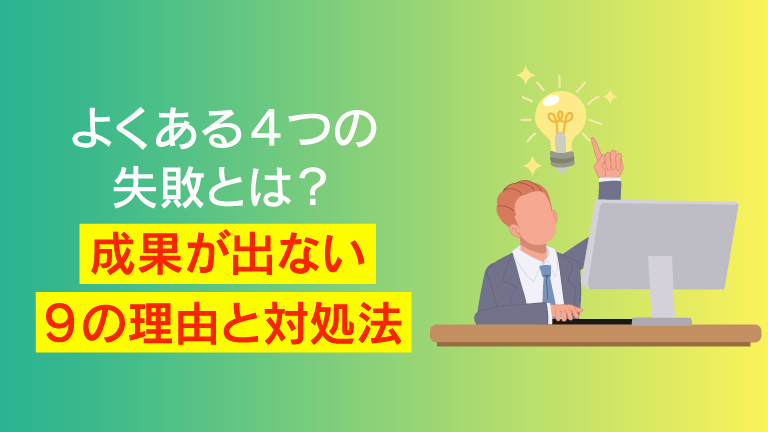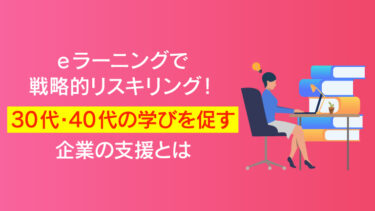「せっかくeラーニングを導入したのに、なかなか効果が出てこない」
オンラインで学べるeラーニングは、ビジネスパーソンの学習スタイルとしてすっかり定着しました。時間と場所を選ばずに受講できて効率的という点から、その効果に大きな期待を寄せて導入した企業も多いでしょう。
しかし、eラーニングの効果が得られていないと感じている企業は少なくないようです。
パーソル総合研究所が人事部門の「教育・研修」「人材開発・キャリア開発」担当者を対象として2021年に実施した調査1では、eラーニングで学習目標の8割以上を達成したと回答した割合は32.0%でした。
対面集合研修の42.0%、オンライン集合研修の46.5%と比較すると、eラーニングは達成度が一番低く、企業側が感じるeラーニング導入の手応えのなさが、決して錯覚ではないことが分かります。
この記事では、eラーニングの導入における失敗の原因や問題点を解明し、それぞれの具体的な対策を解説します。併せて、eラーニングの導入・運用に成功した企業事例も紹介しますので、eラーニング運用に課題を感じている担当者の方はぜひ参考にしてください。
企業向けeラーニングシステム10件をポイントごとに比較! ⇒ 「eラーニングシステム徹底比較Book」を無料ダウンロード
eラーニングシステムは、インターネットを通じてオンライン上で教材を配信するためのシステムです。社内研修のコストを抑えられるだけでなく、DX推進やリスキリング、自律学習にも欠かせない手段となりつつあります。この記事では、企業向けeラ[…]
AIで要約
- 学習者が「自分ごと化」しやすい、アニメーションや事例などを活用した魅力的なコンテンツの準備は、eラーニング導入の失敗を防ぐ有効な対策の一つです。
- eラーニングと集合研修を組み合わせる「ブレンディッドラーニング」は、オンライン学習だけでは難しい、実践的なスキル習得の機会を確保するのに有効です。
- 学習の成果を人事評価へ反映させたり、就業時間内に学習時間を設定したりするなど、会社が学習を支援する仕組み作りが従業員の意欲を高めます。
eラーニング失敗の原因と対策(1)コンテンツに関する失敗:受講者が魅力を感じない、「自分ごと化」できない
eラーニングにおいてまず見直すべきは、そのコンテンツ内容です。ここではコンテンツによる失敗の原因と、その対策について解説します。
原因(1):退屈・一方的な内容で飽きてしまう
情報をただ羅列するだけのコンテンツは、受講者が退屈してしまい学習意欲の低下につながります。特に講師が一方的に話し続けるだけの動画教材は、対面の講義のような緊張感もなく、集中力の維持が難しいでしょう。
eラーニングの場合、退屈・一方的な内容だと受講者が別の作業をしながら視聴したり、動画を飛ばし見したりするケースが増えていきます。結果として、受講はしたものの理解はまったく深まっていないという状態に陥ってしまいます。
原因(2):業務内容やニーズとズレたコンテンツ
コンテンツ内容が実際の業務と結び付いていないことも、学習意欲が低下する原因です。
市販されている汎用のコンテンツのみでは、個々の現場でのニーズに応えられない場合があります。そうすると受講者は「学んでも現場で生かせない」と考え、eラーニングへの意欲や関心を失ってしまうでしょう。
原因(3):コンテンツ制作のノウハウ不足
現場のニーズに応えるには、自社独自のコンテンツの内製が有効です。しかし、そもそも企業側にコンテンツを制作するためのノウハウが不足しているケースも多く見られます。
受講者の興味を引くような内容を企画したり、実際の業務に合ったケーススタディを盛り込んだりするには、コンテンツ制作のノウハウが必要です。
社内にコンテンツ制作の知識と経験が豊富な人材が少なく、一定以上のクオリティのコンテンツを作れない状況が続けば、従業員のeラーニング離れにつながってしまいます。
【対策】:コンテンツの魅力を高め組織課題・学習ニーズに合ったコンテンツを準備する
eラーニング導入を成功させるためには、受講者が飽きずに「自分ごと化」できるコンテンツが不可欠です。以下の4つのポイントを踏まえ、ニーズに沿ったコンテンツを準備しましょう。
| 4つのポイント | 活用したい要素 |
| (1)視覚的な分かりやすさ | アニメーション動画など |
| (2)集中力の維持 | マイクロラーニング(短時間コンテンツ)など |
| (3)現場での実践イメージ | ケーススタディや事例紹介など |
| (4)理解度の確認 | テストやクイズなど |
クオリティの高いコンテンツを内製するには、制作担当者にコンテンツ制作のノウハウを身に付けてもらう必要があります。専任の制作担当者を設置し十分な育成期間を確保する、制作担当者のスキルアップのための勉強会を行うなど、社内体制の整備を行いましょう。
また、コンテンツを用意する方法は、購入や内製だけではありません。コンテンツをカスタマイズしたり、オーダーメイド制作(外注)したりする方法もあります。
オーダーメイドは市販教材の購入や内製よりも費用がかかるケースが多いですが、プロが高品質な自社オリジナルコンテンツを制作してくれます。
例えば、基本知識の学習は市販コンテンツを、現場の作業については内製コンテンツを、多言語対応が必要など内製が難しい内容はオーダーメイドコンテンツを用意するというように、自社の課題やニーズ、予算等に応じて使い分けることがポイントです。
eラーニング失敗の原因と対策(2)集合研修との比較で感じるデメリット:一方通行、交流機会がない
集合研修と比較したときのeラーニングのデメリットへの対策が不十分であることも失敗原因の1つです。ここでは事前に知っておくべきeラーニングのデメリットと、それを解消するための対策を紹介します。
原因(1):双方向性・交流の不足
eラーニングは個々で取り組めて利便性が高い反面、講師や他の受講者との交流はほぼありません。
集合研修では疑問点をすぐ講師に質問したり、他の受講者と意見交換をしたりする機会があり、学習内容の理解が深まります。さらに、双方向のやりとりが刺激となって学習意欲の向上も期待できます。
eラーニングは集合研修と比べて双方向性や交流が不足しやすく、それをカバーするための工夫が必要であると認識しなくてはなりません。
原因(2):実践的なスキル習得の限界
一般的な集合研修では、講義で知識を習得した後に、実務を想定した演習やロールプレイングなどを通して知識を実践的スキルへと昇華させます。
一方、eラーニングは動画などを視聴するインプット中心の学習になるため、実践的スキルを習得しにくい場合があります。
eラーニングでの画面上の説明だけでは、細かなニュアンスの違いをくみ取ったり、臨機応変な対応力を習得したりすることは困難です。無理にeラーニングのみで学習を完結させようとすると、失敗につながりやすくなります。
【対策】:ブレンディッドラーニングや社内SNS機能の活用
集合研修と比べて一方的・交流機会がないというeラーニングのデメリットを解消するには、eラーニングに他の学習手法やコミュニケーション機会を組み合わせることが有効です。
eラーニングや集合研修、OJTなど、複数の学習手法を組み合わせてそれぞれの特長を生かす手法を、ブレンディッドラーニングと呼びます。例えば、eラーニングで理論・知識を学習した後に集合研修でロールプレイングを行えば、双方向性を補い、実践的スキルの習得機会を確保できるでしょう。
また社内SNSを活用すれば、オンラインで自由に意見交換ができ、受講者同士の交流の場をつくることができます。
関連 ▶ ブレンディッド・ラーニングとは 研修とeラーニングのうまい組合せ方
eラーニング失敗の原因と対策(3)運用・管理に関する失敗:受講者の放置、管理者の負担増
利便性の高いeラーニングですが、管理を怠ると十分な成果を得ることはできません。ここではeラーニングの運用・管理の側面から失敗の原因について解説します。
原因(1):受講が従業員任せになり、動機付けがない
eラーニングの受講が進まない原因として、従業員の自主性に任せきりとなっていて、管理者が受講への動機付けを十分に行っていないことが挙げられます。
学習の理由やメリットが不明瞭な状態では、従業員はeラーニングに積極的になれません。eラーニングによる学習が自身の業務やキャリア形成にどのように役立つのか分からない、あるいは評価や昇進とは無関係だと認識していると、eラーニングへのモチベーションが下がってしまうでしょう。
管理者は「従業員にやる気がないから」と従業員側の問題として片付けてしまわず、従業員の心理をくみ取って動機付けのための働きかけをする必要があります。
原因(2):学習進捗や理解度の把握・フォローアップ不足
eラーニングは導入して終わりではなく、継続的に学習状況を把握してフォローアップすることが重要です。
従業員によっては、eラーニングでの学習が滞っていたり、学習内容の理解が不足していたりする場合があります。
そのような状況に気付き、フォローアップにつなげる運用・管理体制が整備されていなければ、従業員がeラーニングでの学習を諦めてしまう、十分に内容を理解できていないまま終了してしまうといった結果が生じます。
原因(3):学習時間確保の難しさ
従業員がeラーニングで学習する時間を確保できる環境を整えられていないことも、eラーニング導入失敗の原因となります。
例えば、業務の合間での学習では、顧客対応などに中断され、集中して取り組めないでしょう。また、就業時間外にプライベートの時間を割いてeラーニングに取り組むとなれば学習意欲の維持が困難です。
「いつでも自分のペースで取り組める」という手軽さゆえに、eラーニングは学習時間を意識的に確保しないと後回しにされやすいといえます。
【対策】:eラーニングシステム(LMS)で管理者の負担軽減と受講者へのフォローアップ強化
eラーニングでの運用・管理の失敗を防ぐには、管理者の業務負担を軽減しつつ、受講者への丁寧なフォローアップを実現する仕組みが必要です。
そのためにはeラーニングの運用を効率的に管理できるeラーニングシステム(LMS)の導入がおすすめです。eラーニングシステム(LMS)には、主に以下のような機能が備わっています。
管理者用の機能
- eラーニングコンテンツの作成・登録・配信
- 必要な学習をコースとして体系化する
- 個別の学習履歴・進捗の管理
- アンケートの配信・自動集計
- 読み飛ばし防止などの不正受講対策
受講者用の機能
- eラーニングの受講
- 学習の進捗や理解度の確認
- アンケート・課題の提出
- 自分の経歴・学習履歴・保持資格などキャリア情報の閲覧
多彩な機能とコンテンツを搭載するeラーニングシステム ⇒ 「CAREERSHIP GROWTH」について詳しく見る
また受講者へのフォローアップは、以下の4つのポイントを意識して実践しましょう。
| ポイント | 方法の例 |
| (1)eラーニングの意義の明確化と周知 | ・学習目的やキャリアとの関連を、メールやチャットなどで周知 ・必修・推奨項目を設定 |
| (2)学習成果の評価 | テスト結果や学習進捗を人事評価に反映 |
| (3)競争・協調を促す仕掛け | ・他の受講者の学習進捗などの公開 ・学習コミュニティや情報交換の場として社内SNS機能を活用 |
| (4)学習時間確保の支援 | ・就業時間内に学習時間を設定 ・学習時間を労働時間として扱う |
LMSとは「Learning Management System(ラーニングマネジメントシステム)」の略で、日本語では「学習管理システム」と訳されます。この記事では、LMSの基本的な仕組みからメリット・デメリット、選定時に気を付け[…]
eラーニング失敗の原因と対策(4)eラーニングシステム・受講環境に関する失敗:受講者も管理者も使いにくい
eラーニングシステム(LMS)が自社のニーズに合っていなかったことが、eラーニングの導入に失敗した原因であるケースも見られます。ここではeラーニングのシステム面や受講環境による原因について解説します。
原因:eラーニングシステム(LMS)の利便性が悪い、使いにくい
eラーニングシステム(LMS)の操作性が悪いと、受講のたびにストレスを感じて学習意欲が削がれていきます。
特に、UI(操作画面のデザインなど製品とユーザーの接点)/UX(使用感、満足感など製品の利用によって得られる体験)が十分に考慮されていないシステムは、直感的な操作ができずにストレスを感じやすくなります。
また、特定のOSやデバイスでしか使えないシステムでは、リモートワークなどの多様化する勤務形態に対応できません。
人事管理システムなど他のシステムと連携できないeラーニングシステム(LMS)の場合は、管理者が別途手作業でデータを移行するなど、管理者の負担も大きくなるでしょう。
【対策】:快適な学習体験と効率的な管理を支えるeラーニングシステム(LMS)の選定
eラーニングを成功させるためには、受講者が快適に学べる環境と、管理者が効率的に運用できる仕組みが不可欠です。そのために以下のような機能を持つeラーニングシステム(LMS)を選定するとよいでしょう。
受講環境の改善
| マルチデバイス対応 | PCだけでなくスマートフォンやタブレットなど、各種デバイスに対応。時間や場所を問わず快適に学習が進められる環境を整備 |
| 直感的で使いやすいUI | 複雑な操作や専門知識が不要で、誰もが迷わず使用できる優れたインターフェース |
運用の効率化
| シングルサインオン対応 | 一度の認証(ログイン)で、複数のシステムにアクセス。 ID・パスワード管理を簡略化でき、受講者・管理者双方の負担を軽減 |
| 既存システムとの連携 | 人事管理システムやタレントマネジメントシステムなどと連携し、データを一元管理。運用負担を軽減 |
eラーニング成功事例に学ぶ課題克服と効果的な活用方法
最後に、eラーニングを導入し人材育成において成果を得た企業の事例を紹介します。
住友商事株式会社:労働災害を“自分ごと化”させるリアルな教材制作
日本を代表する総合商社の1つである住友商事株式会社では、グローバルな事業展開に伴い、国内外の現場における労働災害件数の増加が課題となっていました。
そこで、グループ全体を対象とした安全教育を実施するに当たり、労働災害を「自分ごと化」させるべく、リアルで実効性の高いeラーニング教材を作成しました。
理論的な説明やテキストだけでは受講者が「リアルな危機感」を持ちづらいことから、シナリオベースの動画教材で労働災害の恐ろしさ、緊迫感を忠実に再現しました。例えば、救急車のサイレン音についても世界各国の音を参考にした上で表現するなど、細部まで徹底してリアリティを追求しました。
その結果、受講者から「事故の怖さを実感した」「印象に強く残る教材のおかげで、改めて体系的に整理して理解できた」といった声が寄せられ、高い評価を得ています。
さらに、従業員から労働災害についての問い合わせが増えるなど、全社的に安全や防災に対する意識が向上しています。
企業が、世界各国、さまざまなビジネス分野で事業を拡大していくなかで、労働災害発生リスクも増加しています。大手総…
住友ファーマ株式会社:eラーニングシステム(LMS)のシステム管理者が事実上ゼロに
大手製薬企業の住友ファーマ株式会社では、以前は研究、生産、営業などの各部門が異なるeラーニングシステム(LMS)を導入していました。そのため、部署異動があるたびに新規IDを発行する必要があり、学習履歴などのデータ連携もできませんでした。
また異動した従業員も、操作性が異なる新しいシステムに慣れることから始めなければならず、教育担当者・受講者双方にとって大きな負担となっていたのです。
そこで同社は株式会社ライトワークスのeラーニングシステム(LMS)「CAREERSHIP」を導入し、組織変更や人事異動に関わる対応を完全に自動化しました。その結果、従来は各部門合計10人もの担当者が行っていたシステム管理業務が事実上ゼロになりました。
さらに、企業所有のPCやスマートフォン、タブレットからのみ接続を認める個体認証、社外からアクセスできる教材とできない教材に分けた管理など、利便性・安全性の高い学習環境を実現しました。受講者は、移動中などの空いた時間を有効活用でき、学習効率が飛躍的に向上しました。
eラーニングシステム(LMS)の統一により、教育担当者・受講者の負荷軽減と利便性向上という大きな成果を生み出しています。
社内の人財教育において、細かい業務に時間と労力を取られている担当者の方、実は多いのではないでしょうか?併用していた3社の…
株式会社テンポイノベーション:新入社員の早期戦力化・定着率向上と研修担当者の負担軽減を実現
不動産関連事業を手掛ける株式会社テンポイノベーションでは、新入社員が一人前の営業担当者になるまでに従来は2~3年の期間を要していました。その間に成果が出せず離職する従業員も多く、定着率が低いことが課題でした。
また、研修担当者は、新入社員研修やその後の座学研修、OJT、チームメンバーのサポートなどを行い、その上で自分の業務をこなさなければならず、負荷が大きい状態が続いていたのです。
そこで、同社はライトワークスのeラーニング教材制作サービスを活用して、社内に点在していたノウハウや知識を体系的に整理し、約300本の動画教材を作成しました。これにより、研修の均質化と、研修担当者の時間的な負担軽減につながりました。
動画教材の導入後、新入社員は自分のペースで繰り返し学習でき、早ければ2〜3カ月で営業成績が向上する事例が出るなど、早期戦力化を実現しています。
研修担当者は指導時間を大幅に短縮できたため、新入社員のサポートやケアに時間を割けるようになりました。動画教材の活用により、新入社員の定着率向上と研修担当者の負担軽減を同時に達成しています。
店舗物件の転貸借に特化した不動産事業を展開する株式会社テンポイノベーションは、新入社員の早期戦力化・定着率向上…
まとめ
eラーニングを導入しても十分な効果が得られていない場合は、失敗の原因を特定し、適切な対策を講じる必要があります。この記事では、一般的なeラーニングの失敗原因を整理し、それぞれの解決策を詳しく解説しました。
主にコンテンツを原因とした失敗と、その対策は以下の通りです。
- 原因(1):退屈・一方的な内容で飽きてしまう
- 原因(2):業務内容やニーズとズレたコンテンツ
- 原因(3):コンテンツ制作のノウハウ不足
- 対策:コンテンツの魅力を高め組織課題・学習ニーズに合ったコンテンツを準備する
集合研修と比較したときのeラーニングのデメリットに起因する失敗と、その対策は以下の通りです。
- 原因(1):双方向性・交流の不足
- 原因(2):実践的なスキル習得の限界
- 対策:ブレンディッドラーニングや社内SNS機能の活用
eラーニングの運用・管理に関する失敗と、その対策は以下の通りです。
- 原因(1):受講が従業員任せになり、動機付けがない
- 原因(2):学習進捗や理解度の把握・フォローアップ不足
- 原因(3):学習時間確保の難しさ
- 対策:eラーニングシステム(LMS)で管理者の負担軽減と受講者へのフォローアップ強化
eラーニングシステム・受講環境に関する失敗と、その対策は以下の通りです。
- 原因:eラーニングシステム(LMS)の利便性が悪い、使いにくい
- 対策:快適な学習体験と効率的な管理を支えるeラーニングシステム(LMS)の選定
また、eラーニング導入の成功事例として以下の企業を取り上げました。
- 住友商事株式会社:労働災害を”自分ごと化”させるリアルな教材制作
- 住友ファーマ株式会社:eラーニングシステム(LMS)のシステム管理者が事実上ゼロに
- 株式会社テンポイノベーション:新入社員の早期戦力化・定着率向上と研修担当者の負担軽減を実現
eラーニングはポイントを押さえて適切に運用することで、教育を均質化し、効率的に人材を育成するための効果的なツールとなります。
eラーニングによる学びを定着させ、安定的な運用・管理を行うには、eラーニングシステム(LMS)の活用も検討しましょう。受講者の利便性や意欲を高め、かつ、教育担当者の負担軽減が可能です。
eラーニング失敗のリスクを避け、コンテンツとシステムの相乗効果を得たいという方は、ライトワークスのオールインワンサービス「CAREERSHIP GROWTH」をぜひチェックしてみてください。
- 株式会社パーソル総合研究所「コロナ禍における研修のオンライン化に関する調査」,2021年7月公表,P17,(閲覧日:2025年6月3日) ↩︎