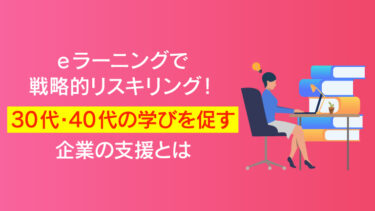近年、働き方の多様化やリスキリングの重要性が高まる中、効率的かつ効果的な人材育成手法としてeラーニングが注目を浴びています。
時間や場所を選ばずに学習機会を提供できるeラーニングは、従業員のスキルアップ、知識の標準化、そして研修コストの最適化に貢献し得る有効な手段です。
しかしながら、eラーニング環境を構築するにあたり「何から手を付ければよいのか」「自社に適した方法は何か」といった点で、導入に踏み切れずにいる教育担当者の方も少なくないでしょう。
この記事では、eラーニング環境を構築するための主要な3つのステップと、それぞれの検討ポイントを簡潔かつ分かりやすく解説します。自社の教育戦略を前進させるための一助となれば幸いです。
企業向けeラーニングシステム10件をポイントごとに比較! ⇒ 「eラーニングシステム徹底比較Book」を無料ダウンロード
「できるだけ安価に、かつ良い教材を取り揃えたい」eラーニングの教材コンテンツの調達を担当されている方は、このようにお考えだと思います。しかし、闇雲にインターネット検索をしてみても、ベンダー各社が提供している教材コンテンツの多さに圧[…]
AIで要約
- まず、eラーニング導入の成否は「目的・対象者・ゴール」を明確にできるかが重要です。
- 次にクラウド型や独自開発など3つのeラーニング構築方法から、自社の状況に合うものを選びます。
- 最後に学習コンテンツを用意し、受講者がストレスなく学べるサポート体制を整えましょう。
ステップ1:eラーニング環境の構築目的と対象者の明確化
自社にeラーニング環境を構築するための最初の、そして最も重要なステップは、「なぜ導入するのか(目的)」と「誰に何を学んでもらうのか(対象者とゴール)」を明確にすることです。これらが曖昧なままでは、期待する効果を得ることは難しくなります。
eラーニング導入で解決したい経営・人事課題の特定
まず、自社がeラーニング導入を通じて解決したい、あるいは改善したい具体的な課題を特定します。例えば、以下のような課題が考えられます。
- 新入社員の早期戦力化と育成プロセスの標準化
- 専門知識・スキルの習得促進による生産性向上
- 全従業員に対するコンプライアンス意識の定着・強化
- 多拠点・リモートワークの従業員への均質な学習機会の提供
学習対象者と具体的な学習目標(ゴール)の設定
次に、eラーニングの対象となる従業員層と、その対象者が達成すべき具体的な学習目標を定めます。例としては、以下のような形です。
【対象者】新入社員
【学習目標】3カ月以内に、自社の主要製品に関する基礎知識テストで80点以上を取得
【対象者】営業部門
【学習目標】新サービスに関するeラーニング受講後、顧客への提案成功率を現状から10%向上
導入目的、対象者、学習目標を具体的に文書化し、関連部署や経営層と共有・合意形成を行うことが、eラーニングの導入を成功させる基盤となります。
ステップ2:自社に適したeラーニング構築方法の選定
目的と対象者が明確になったら、次にeラーニング環境をどのように構築するか、その方法を選定します。主に以下の3つのアプローチが考えられます。それぞれの特徴を理解し、自社の状況に最適なものを選択しましょう。
クラウド型のeラーニングシステム/LMS(学習管理システム)の活用
ベンダーのサーバー上に構築されたeラーニングシステムあるいはLMS(学習管理システム)に、インターネット経由でアクセスして利用する方法です。自社側にサーバー構築や専門知識がなくても、比較的迅速かつ低コストで導入できます。
メリット
- 迅速な導入(契約後すぐに利用開始可能な場合が多い)
- 初期費用を抑えられる(月額・年額の利用料金が設定されているケースが一般的)
- システムの保守・アップデートはベンダーが実施
デメリット
- デザインや機能のカスタマイズに制限がある場合が多い
- ベンダーによるサービス内容の変更やサービス終了のリスクがある
適した企業像
- 早期にeラーニングを開始したい企業
- IT専門の担当者が社内にいない、またはリソースが限られている企業
- 標準的な機能で対応可能なニーズを持つ企業
1,000名以下におすすめ!eラーニング受け放題+LMSのお得なパッケージプラン ⇒ 「CAREERSHIP GROWTH」を詳しく見る
オーダーメイドによる独自システム構築
自社の要件や教育体系に合わせて、オーダーメイドでeラーニングシステムを開発する方法です。
メリット
- デザイン、機能、ワークフローなど、完全に自社の要望に合致したシステムを実現できる
- 既存の社内システム(人事DBなど)との柔軟な連携が可能
デメリット
- 初期開発費用が高額になる傾向がある
- 開発期間が長期にわたる(数カ月~1年以上)
- プロジェクト管理やベンダーコントロールに専門知識が必要
適した企業像
- 独自の教育プログラムや特殊な機能要件を持つ企業
- 十分な予算と開発期間を確保できる企業
- IT部門や人材開発部門などとの連携体制を構築できる企業
オープンソースLMSの活用
ソースコードが公開され、無償で利用や改変ができるオープンソースLMS(例:Moodle)を活用し、自社のサーバーにシステムを構築して運用する方法です。
メリット
- ソフトウェア自体のライセンス費用が発生しない
- ソースコードが公開されているため、理論上は自由にカスタマイズが可能
デメリット
- サーバー構築、インストール、設定、カスタマイズ、セキュリティ対策、保守運用など、高度なITスキルを持つ人材をはじめ相応の人的リソースが必要
- 公式なサポートがない場合が多く、問題発生時は自己解決が基本
適した企業像
- 社内にサーバー管理やシステム開発に長けたIT人材がいる企業
- ソフトウェアコストを最優先で抑えたい企業(ただし、構築・運用にかかる人件費や時間は考慮が必要)
上記3つのアプローチのメリット・デメリットを比較し、予算や導入までの期間、社内のIT体制、eラーニングシステムに求める機能の優先順位などを総合的に勘案して、自社に最適な構築方法を検討しましょう。
ステップ3:学習コンテンツと受講環境の整備
適切な構築方法を選定したら、次はeラーニングの「中身」である学習コンテンツと、スムーズに利用できる受講環境を整備します。
学習コンテンツの準備:内製と外部調達の比較検討
学習コンテンツを準備するには、自社で作成する「内製」と、既製品を購入または制作を外部委託する「外部調達」の2つの方法があります。
内製のポイント
学習コンテンツを自社で作成する「内製」は、自社の業務内容、企業文化、独自のノウハウを反映したオリジナルコンテンツが作成可能です。
また、既存の社内マニュアル、研修資料、PowerPointなどを活用すれば、比較的低コストで準備できる場合も。内容の修正やアップデートが自社で柔軟に行える点も便利です。
外部調達のポイント
学習コンテンツを購入または制作を委託する「外部調達」では、一般的なビジネスマナー、コンプライアンス、専門分野の知識など、質の高い汎用コンテンツを迅速に導入可能です。
また、コンテンツ制作サービスを利用すれば、専門家が自社の要望に合わせて作成した高品質なオリジナルコンテンツを調達することができます。費用や自社のニーズとの適合性などを慎重に比較検討し、自社に適したコンテンツ作成サービスを選定しましょう。
検討のヒント
まずは、社内に存在する研修資料や業務マニュアルをeラーニングに転用できないか検討することから始めてみてください。PowerPointで作成した資料にナレーションを加える、PDF化して共有するだけでも、立派なeラーニングコンテンツとなり得ます。
受講しやすい環境の整備
eラーニング導入を成功させるためには、受講者がストレスなく学習に集中できる環境を提供することも欠かせません。
従業員の中には、デジタル機器の操作に不慣れな人やeラーニングを初めて利用する人もいるでしょう。操作に迷わないかなど、受講者がつまずきそうなポイントを事前に想定し、スムーズに学習を開始・継続できるようサポート体制を構築することが重要です。
導入初期は特に問い合わせが増える可能性があるため、対応のためのリソースを確保しておきましょう。
安定したインターネット環境の確保
特に動画コンテンツを扱う場合、快適な視聴のためには安定したインターネット接続が前提となります。社内のインターネット環境を整えることはもちろん、リモートワークをする従業員の学習環境にも配慮が必要です。
マルチデバイス対応の検討
PCだけでなく、スマートフォンやタブレットからもアクセスできる環境は、学習機会の拡大につながります。eラーニングシステムやLMSがレスポンシブデザインに対応しているか、モバイルアプリを提供しているかなどを確認しましょう。
受講者へのサポート体制の構築
「ログインできない」「操作方法が分からない」といった受講者の疑問やトラブルに対応するため、FAQ(よくある質問と回答)を整備する、社内に問い合わせ窓口を設けるなどサポート体制を構築します。
学習コンテンツと受講環境を準備したら、まずは少人数を対象に試用(パイロット運用)を実施し、受講者視点でのフィードバックを収集・分析しましょう。その結果を基に改善を加えることで、本格導入時の満足度向上につながります。
eラーニングの運用を成功させるための具体的な方法とは? ⇒「 eラーニング大百科」を無料でダウンロードする
eラーニングの運用と効果測定の基本
eラーニングは、導入して終わりではありません。その効果を最大限に引き出し、継続的に高めていくためには、適切な運用と効果測定が不可欠です。
これらを計画的に行うことで、eラーニングは戦略的な人材育成の柱となり得るでしょう。
運用体制の確立
eラーニングシステムを円滑に運用するため、担当者や役割分担を明確にしましょう。運用に関わる業務の例としては以下が挙げられます。
- 学習進捗の定期的な確認
- 未受講者へのリマインド
- 新規コースのアナウンス
- コンテンツの更新管理
- 受講者からの問い合わせ対応 など
効果測定の実施
受講者へのアンケート(満足度、有用性など)や理解度テストを実施し、eラーニングの学習効果を把握します。そして収集したデータやフィードバックに基づき、定期的にコンテンツを見直したり、他の学習手法と組み合わせたりするなどの改善を重ねていきます。
PDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを回し続けることで、より自社や従業員のニーズに合致した、効果的な学習機会の提供につながるでしょう。
eラーニング受講時間の労働時間管理
eラーニング環境を構築し、運用する際には、技術的・教育的観点だけでなく、法的な側面にも十分な配慮が必要です。適切な対応を怠ると、労働問題の発生などリスクを高めてしまう可能性があります。
eラーニングの受講時間を労働時間に含めるべきか、頭を悩ませている教育担当者の方も多いでしょう。以下に注意点や対応策をまとめました。
eラーニング受講が労働時間になる場合
eラーニング受講を「業務命令」とする場合、受講時間は原則として労働時間に該当します。例えば、以下のようなケースが挙げられます。
- 「必須研修」と指示している
- 業務の一環として就業時間内に実施する
- 未受講者に対して上司や教育担当者などが受講を催促する
- 受講したかどうかが人事評価に反映される
eラーニング受講が労働時間になる場合の注意点
eラーニング受講を労働時間として扱うなら、通常の業務同様、労働基準法に基づいた対応が必要です。
労働基準法では、法定労働時間や法定休日が定められています。eラーニング受講が、時間外労働(法定労働時間を超えた労働)や休日労働(法定休日中の労働)、深夜労働(原則午後10時から午前5時までの間)に該当すれば、割増賃金を支払わなければなりません。
また、労働基準法に基づく時間外労働・休日労働に関する労使協定(36協定)を締結している場合、協定で定める労働時間の上限を超えないようeラーニングの受講時間も含めて管理する必要があります。
実務上の対応策
eラーニング受講を労働時間として扱う場合、以下のような対応策が考えられます。参考にしてみてください。
- 受講時間の明示:コース説明に「このコースの標準学習時間は○○分です」と明記する
- 就業時間内受講の推奨:可能な限り、就業時間内での受講を奨励する社内ルールを策定する
- 自己啓発との区別:自己啓発に活用する任意受講のコンテンツと、業務上必須受講のコンテンツを明確に区別する
- 受講時間の上限設定:長時間労働防止のため、eラーニングシステムやLMSで1日当たりの受講可能時間に上限を設定する
人材開発支援助成金の活用法
人材開発支援助成金は、企業が従業員に対し業務に関連した専門的な知識や技能を習得させるための職業訓練を実施した場合などに、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を国が助成する制度です。この制度を活用すれば、eラーニングの導入・運用コストを抑えることができます。
主な助成コース
- 人材育成支援コース:業務に関連した知識・技能の習得、非正規雇用従業員の正社員化を目的とした訓練などを実施した場合に助成
- 人への投資促進コース:サブスクリプション型の研修サービスを利用した訓練などを実施した場合に助成
- 事業展開等リスキリング支援コース:新たな分野で必要となる知識および技能を習得させるための訓練を実施した場合に助成
- 教育訓練休暇等付与コース:有給の教育訓練休暇制度を導入し、従業員が該当制度を利用して訓練を受けた場合に助成
活用のポイント
人材開発支援助成金を受給するためには、訓練の実施や制度の導入・適用の計画届を作成し、管轄の労働局に提出する必要があります。訓練時間数や受講率などの支給要件と必要書類、申請から受給までの流れは必ず確認し、理解しておきましょう。
不明点や不安がある場合は、都道府県労働局や商工会議所に相談する、社会保険労務士に手続きの代行を依頼するなどの方法を検討してみてください。
企業向けeラーニングシステム10件をポイントごとに比較! ⇒ 「eラーニングシステム徹底比較Book」を無料ダウンロード
まとめ
この記事では、eラーニング環境を効果的に構築し、運用していくための具体的な3つのステップ、運用と効果測定の基本について解説しました。以下に、重要なポイントを改めて整理します。
- ステップ1:eラーニングの導入目的と対象者の明確化
- ステップ2:自社に適した構築方法の選定
- ステップ3:学習コンテンツと受講環境の整備
「なぜeラーニングを導入するのか」「それによって何を達成したいのか」という根本的な問いに対する答えを明確にし、社内で共有・合意形成を図ることがeラーニング導入を成功させる基盤となります。
eラーニング環境の構築方法には、主に以下の3つがあります。
- クラウド型のeラーニングシステム/LMS(学習管理システム)の活用
- オーダーメイドによる独自システム構築
- オープンソースLMSの活用
予算、導入までの期間、社内リソース、求める機能などを総合的に検討し、最適な構築方法を見極めることが重要です。
学習コンテンツを準備する方法は、主に内製と外部調達の2つです。まずは、社内に存在する研修資料や業務マニュアルをeラーニングに転用できないか、検討してみるとよいでしょう。
安定したインターネット環境の確保、マルチデバイス対応、受講者へのサポート体制の構築など、受講者のモチベーションを保ちスムーズに学習できる環境を整備することも欠かせません。
また、eラーニングは導入して終わりではありません。適切に運用できるよう運用体制を確立し、定期的にコンテンツを見直すなどの改善を重ねることで、より効果的な学習機会の提供につながります。
この他、eラーニングの受講時間を労働時間として扱うべきかという観点や、eラーニングに関連する公的支援制度(助成金)についても解説しました。
eラーニングの戦略的な導入と運用は、従業員一人一人の能力開発を促進するだけでなく、変化への対応力を高め、ひいては組織全体の持続的な成長と競争力強化に大きく貢献します。この記事が、自社のeラーニング環境構築の参考になることを願っています。